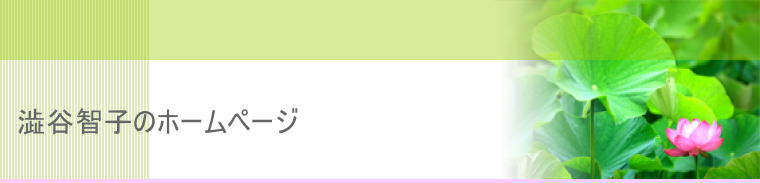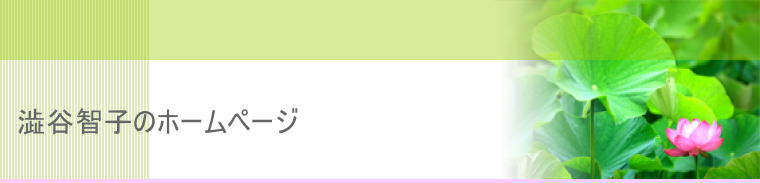|
|
東京外国語大学 言語学特殊講義 (2011年度冬 集中講義)
日本手話と日本語のバイモダル・バイリンガリズム
|
◆授業の目標
手話という視覚言語の特徴を知り、視覚言語と音声言語のバイリンガリズムにおいては、二つの言語の同時産出が可能という現象が起きることを理解する。そして、この現象のために、手話という言語が誤解を受けやすくなる構造があることを学び、音声言語を相対化する視点を持つ。
◆授業の概要
バイモダル・バイリンガリズムの英語論文を読みながら、ろう者のいる家庭や教育現場、手話コミュニティなどにおいて、音声言語と手話がどう接触し、両者の間でどのような抑圧や対立、混交が起きているのかを考える。
◆授業の内容
第1回 イントロダクション――なぜ手話は誤解されるのか、「ろう文化宣言」
第2回 コーダのバイリンガリズム① DVD「コーダ ぼくたちの親はきこえない」
第3回 コーダのバイリンガリズム②
第4回 日本手話実技①
第5回 日本手話実技②
第6回 日本手話の音と形
第7回 バイモダル・バイリンガリズム①
第8回 バイモダル・バイリンガリズム②
第9回 バイモダル・バイリンガリズム③
第10回 バイモダル・バイリンガリズム④
第11回 治療と言語選択①――人工内耳についての問題
第12回 治療と言語選択②――人工内耳についての問題
第13回 手話のコミュニティ
第14回 言語政策と手話、手話言語法をめぐる動き
第15回 教育と手話、まとめ
◆使用文献
・Emmorey, Karen, Helsa B. Borinstein, Robin Thompson and Tamar H. Gollan, 2008, ‘Bimodal Bilingualism’ in Bishop, Michele and Sherry L. Hicks eds., Hearing, Mother Father Deaf: Hearing People in Deaf Families, Washington D.C.: Gallaudet University Press, pp.3-43 (Original published in Bilingualism: Language and Cognition II (I), 2008, 43-61).
・木村晴美・市田泰弘,1995,「ろう文化宣言――言語的少数者としてのろう者」『現代思想』23(3): 354-62.(現代思想編集部編2000『ろう文化』青土社に再掲載)
・木村晴美,2011,『日本手話と日本語対応手話(手指日本語)――間にある「深い谷」』生活書院
・岡典栄・赤堀仁美著,NPO法人バイリンガル・バイカルチュラルろう教育センター編,2011,『文法が基礎からわかる日本手話のしくみ』第一部「日本手話の音と形」
・武居渡,2001,「ろう児はどのように手話を獲得するのか」『手話コミュニケーション研究』41: 4-8.
・丸地伸代,2000,「ろう者と聴者の間で――CODAという名のマイノリティ」『言語』29(7): 88-95.
・松山智,2004,『僕はサイボーグ』新風舎
・ノーラ・エレン・グロース著、佐野正信訳,1991,『みんなが手話で話した島』築地書館.
・財団法人全日本ろうあ連盟,2011,『みんなでつくる手話言語法』財団法人全日本ろうあ連盟
◆使用DVD
・DVD「コーダ ぼくたちの親はきこえない」2011年10月
・ドキュメンタリー番組「音のない世界で」(2001年NHK日本賞受賞作品)
(原題 Josh Aronson 2000 “Sound and Fury”)
・"Sound and Fury Six Years Later"(2006)
Produced and Directed by Josh Aronson
◆成績の評価:平常点で評価する。
◆受講上の注意:授業への積極的な参加が求められる。
授業のページへもどる
|
|