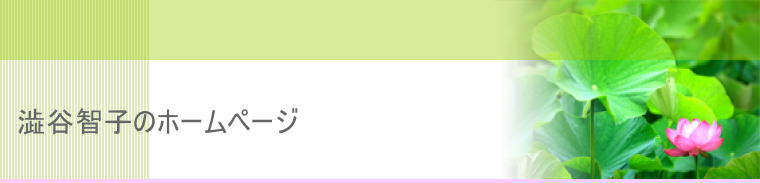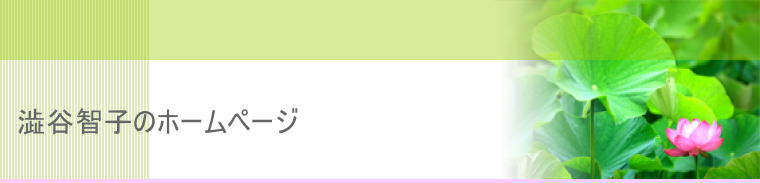|
|
埼玉大学教養学部 社会学Ⅴ(多元化と共生) / 社会学特殊講義Ⅶ
(2004年4月~9月)
|
講義副題「障害と文化」
障害は長いこと、一部の特殊な人々の身体機能の問題と捉えられてきた。しかし、果たしてそうであろうか。障害は障害者本人だけでなく、その家族やまわりの人々の生活や意識を変える側面をももっている。障害は、「健常者」社会との関係において成り立っており、そこには多数派社会の価値観が凝縮されているからである。障害をとりまく問題を見ていくことは、多くの人が暗黙裏に想定している、家族観、ジェンダー意識、マイノリティへのまなざし、能力についての考え方、アイデンティティ意識など如実に浮かび上がらせる。授業では、そのような観点から、障害、家族、文化の関係性を、具体的な場面に照らして考えていきたい。
1.イントロダクション
2.障害のイメージ
――みんなの持っている「障害者」イメージ
テレビドラマや漫画、報道に見る「障害者」の描写
3.障害とは何か
――福祉制度の中の「障害」(種類や手帳など)
「障害」の定義
「障害」とスティグマ(ユニークフェイスの例など)
4.歴史における障害観の変遷
――因果応報的な見方
優生学
戦後の優生思想(女性の産む権利と「青い芝の会」の主張、
福祉国家との関係など)
5.障害と家族1 障害者の家族
――出生前診断と個人にかかってくる選択
障害の告知
専門家と親との関係
「母親」役割とジェンダー(訓練と「母親の愛」など)
障害児をもつ働く母親
6.障害と家族2
――親の会の活動
障害児をもつ父親の関わり方
障害をもたない子(きょうだい)と親との関わり
7.障害児教育
――障害児教育の歴史
統合教育と分離教育の是非
障害児の放課後の問題
8.当事者とは誰か1 障害者の自立生活運動とボランティア
(『こんな夜更けにバナナかよ』第3章を中心に)
――「脱施設化」の流れ
親との葛藤
ピア・カウンセリング
9.当事者とは誰か2 介助者のリアリティ
(『こんな夜更けにバナナかよ』第2章を中心に)
――「障害者」とのコミュニケーションにおける緊張
「ボランティア」のイメージ
10.障害者の性
――身体障害者の性のタブー化
障害者の「性に対する自信のなさ」
身体障害者の性生活、障害者の結婚
障害者の出産・育児
11.ろう文化と人工内耳
――人工内耳とは何か、
『音のない世界で』(NHK2001年日本賞受賞作品)
12.ろう教育と言語権
――『音のない世界で』を見ての意見交換
手話による教育を選んだ聴者の親たち
ろう児のためのフリースクール
13.ろう者の生活 ろう者のゲストと手話通訳者をお迎えして
――声のつかない手話サークルの様子
Kさんのお話
質疑応答
14.能力と仕事
――能力主義について(学歴や文化資本の継承など)
障害者雇用の問題
15.まとめ
授業のページへもどる
|
|