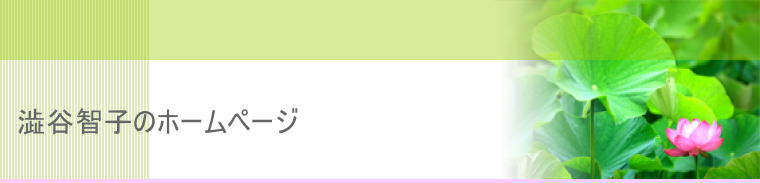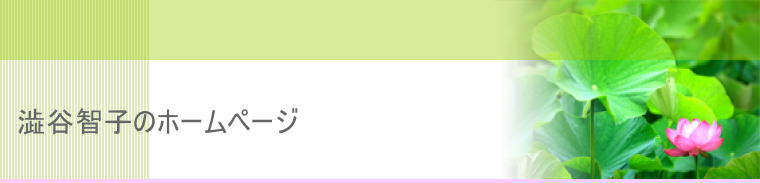|
日経新聞 2009年11月22日 読書面 「あとがきのあと」欄

「コーダの世界」 彼らと話すのが楽しくて
コーダ(CODA)とは「Children of Deaf
Adults」の略で、聞こえない親を持つ子供たちのこと。本書は「聴文化」と「ろう文化」の境界線上にいるコーダから聞き取りを重ね、その豊かな世界をひもといている。
まず印象的なのは、コーダたちの話がとても生き生きと魅力的なことだ。「私も、彼らと話すのはいつも演劇を見ているように楽しかった。そこにひかれて研究を続けたところもある」という。聞こえない親とコミュニケーションのために、コーダたちは身ぶり、手ぶりを駆使して表情豊かに、まるで映像を再現するように話すことが習慣になっているからだ。相手の目を見て、ストレートな物言いをすることも特徴だ。物まねが上手な人も多い。「彼らと話していると、とても『人間』を感じる」。
大学時代に流行した、ろう者が登場するドラマで手話に関心を持った。「ミーハーです」と照れるが、早くも卒論でろう文化を取り上げる。しかし聴者である自身がろう文化にどう迫ればいいか、などと迷う中で気づいたのがコーダの存在だ。おそるおそる、あるコーダ女性に会うと「いきなり焼き肉のタレをお土産にくれて、初対面でここまで?というくらい、いろいろ教えてくれた」。
むろん、彼らには苦労もある。聞こえない親と社会との「通訳」の役割を求められ、幼いころから銀行などとの交渉を経験する人もいる。でも、本書に登場するコーダの話には、悲しみの中にも温かさがある。聞こえない親の、滑舌の良くない「声」を大切に思うエピソードは典型だろう。
10年近くの研究の中で、自身も2人の娘の母となった。「ママ友」のコーダも多く、「次は何を書くの?」と尋ねられたりもするが、今度は少し広げて、働く女性の格差問題の研究を考えているという。(医学書院・2000円)
|