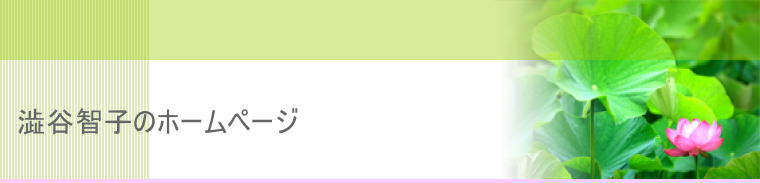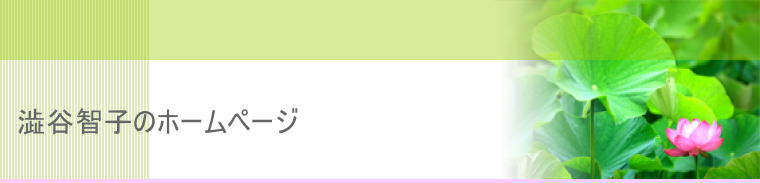「コーダに関するアンケート」
この資料は、2006年春に実施したアンケート調査の結果を
調査協力者の方々に報告するために書かれたものです。
2006年8月に約50人に配布されました。最終的には
博士論文の付帯資料集となりましたが、もともとは、
このように、調査協力者の方々に向けて書かれ配布された
資料であることを、最初に明記しておきたいと思います。
調査者: 澁谷智子
はじめに
「コーダ(CODA)」とは、「Children Of Deaf Adults」を短くした言い方で、
「聞こえない親を持つ聞こえる子ども」を意味します。
アンケートの方法と回答者の範囲について
このアンケートは、2006年3月18日から5月14日までの期間に、「コーダの会」のメーリングリストや調査者が今までに関わってきたコーダの方々の紹介を通して、80人近くの方に配布したものです。そのうちの40人から回答を頂きました。
当初はアンケートにご協力頂く方の条件を「聞こえない両親を持つ15歳以上の方」としていました。「15歳以上」としましたのは、親子関係に関して中学生以下のお子さんに質問をすることの倫理的な問題と、15歳未満の方が大人向けに作成したアンケートに答えられるかどうかという問題を考慮したためです。また、「聞こえない両親を持つ」という条件については、両親が聞こえない場合と片親が聞こえない場合では通訳の経験やコーダにかかってくる責任の大きさに違いが出てくるだろうという予想の基に設定しました。しかし、実際にアンケート回答が集まってみると、お答え下さった40人の方の中には、14歳の回答者が1人、聞こえるお父さんと聞こえないお母さんを持つ回答者が1人含まれていました。後者の方の回答は、他の回答と比べて特徴を持っていると思える点もありました。そのような点は、この報告書の中で明らかになると思います。ただ、全体としてみれば、この方の回答はそれ以上に他の回答者と同じ点が多く、わざわざこの回答を除外して集計する必要性をあまり感じませんでした。また、14歳の方の回答は、15~20歳の方のアンケート回答とほとんど変わりませんでした。
そのようなことから、この調査の集計では、これらの方々の回答も含めています。コーダの年齢がかなり若い時(親元で保護されている状態にある時)と成人してからではどのような違いが出るのか、両親が聞こえない場合と片親のみが聞こえない場合でどう違ってくるのかに関しては、今後、さらに別の調査を行って見ていきたいと思います。
アンケートのまとめ方について
アンケートは、主に「「はい」/「いいえ」式の質問」と「自由記述式の質問」の2種類に分かれています。
<「はい」/「いいえ」式の質問や、数字で表せるようなデータの場合>
こうした質問の集計からは、回答者のうちのどれぐらいの人数がどう答えたのかがわかります。結果は、表とグラフで表しています。1人の回答者の答えが1つの時(単数回答の時)には、円グラフを使ってそのパーセンテージ(%)を表しました。1人の回答者の答えがいくつかある場合(複数回答――つまり「○はいくつでもOK」という場合)には、棒グラフでその答えの多さ少なさを表すようにしました。補足の説明は※で入れてあります。
しかし、今回は中間報告ということもあって、統計的な分析(クロス集計やカイ2乗検定など)はまだ充分に行なっていません。その点はご了承頂けると幸いです。
<自由記述式の回答の場合>
今回のアンケートで力を入れたのは、こうした自由記述の欄です。コーダの皆さんにとって、どういう体験が印象的なものとして捉えられているのか、どう感じたのか、どういう時にそう思ったのかなど、お一人おひとりの体験に即してご自分の言葉で書いて頂きました。
このような自由記述をまとめる時には、似たような記述同士をまとめてグループに分類し、そのグループに合う見出しをつけていくという方法を取りました(社会学で「修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ(M‐GTA)」と呼ばれる方法です)。一人の回答者がいくつかのグループにまたがるような内容を書いて下さった時には、記述を分けて、それぞれのグループに分類しました。こうした方法では、それぞれの方が書いて下さった文章のつながりが壊れてしまうため、自分の答えがバラバラになってしまったような印象を持たれる方もいるかもしれません。その点についてはお詫び致します。でも、その代わり、どんな答え(たとえば「…」など)についても、必ず細部まで載せることにしました。そのほうが、それぞれの方の思いが正確に伝わると思ったからです。また、この方法では、答えの数から回答者の人数を割り出すことはできません(特に箇条書きで書いて下さった回答の場合はそれが顕著です)。今回は、コーダの方々の中から出てくる言葉を丁寧に見ていって全体的な傾向を探るという目的があったため、自由記述に関しては、答えた方の人数よりも、どのような答えの種類が出てきたのかを重視してまとめました。これらの点をご理解頂けると嬉しいです。
表記にあたりましては、調査者の解説を添える場合には、そこをイタリック体で表しました。また、考察部分は、アンケート結果だけでなく、アンケートに先立って行ったインタビュー調査の結果と合わせて行っているところがあります。この報告集は、私が今行っているコーダ研究の中間報告という性格も持つため、こうした考察の方法にさせて頂きました。
2006年8月 澁谷 智子
アンケート結果の概要
<回答者の方々の傾向とこのアンケートの意義>
今回のアンケート回答者の傾向として顕著なのは、10代~30代の若い人が大半を占めること、「コーダの会」を知っている人が8割を超えること、子供の頃に家の中で中心的な通訳の役割を担っていた人が6割もいること、両親とも学校教育はすべてろう学校で受けた人がほとんどであることだった。また、家族や親戚に両親以外で聞こえない人がいる/いたという人は半数近くにのぼり、そのうちの2人には聞こえないきょうだいがいた。おそらく、今回の回答者は、全国的なコーダの平均よりも、手話やろう関連の情報に触れている度合いが高いということが推測できる。それは、このアンケートの配布方法が、「コーダの会」のメーリングリストや、「コーダの会」を通して調査者が知り合った方々の紹介によるというところが大きく働いているだろう。
しかし、このような偏りはあるものの、今回のアンケートは、日本のコーダの意識を明らかにする上で、一定の貢献をするものと思われる。というのも、今の段階では、コーダ個人が自分から「コーダ」と名乗ることはそこまで多くなく、ある程度組織に関わっていなければ見つけ出すのも難しいという状況があるからである。また、アメリカの場合と違って、日本のコーダのネットワークもまだ大規模には発展しておらず、一部の人たちが個人的なつきあいをしているという程度に留まっている。そのため、コーダ個人が他の大勢のコーダと自分の体験を比べて、自分の経験してきたこととコーダであることがどの程度関わっているのか整理する機会は、あまりないようである。その意味で、今回のアンケートは、40人もの日本人コーダの記述を並べて分析する初めての試みであり、回答者からも、アンケート結果に対する高い関心が寄せられている。
<両親とのコミュニケーションや言語について>
両親とのコミュニケーション方法がほとんど手話だけだったという人は全体の22.5%だけで、大半の人々は、手話のほかに、口話、身振り、声、筆談など、さまざまな手段を用いていた。全体的な傾向としては、父親よりも母親のほうが声を使うケースが多かった。特に、母親はコーダに対して「声つき手話」や「声(手話なし)」を使いコーダは「口話」を使用することが多いこと、父親は主に「手話」を使いコーダも父に対してはあまり「口話」を使わないという状況が、はっきりと浮き彫りになった。
自分の気持ちを最もよく表せる「自分の言語」は何かという質問に対しては、回答者の半数近くが「日本語」、5分の1が「手話」、3分の1近くが「手話と日本語の両方」と答えた。しかし、どの言語が使いやすいかは、内容や状況によっても変わると指摘した人も多かった。手話や日本語に対する苦手意識の有無を尋ねた質問では、3分の2近い人が「手話に苦手意識がある」と答え、半数以上の人が「日本語に苦手意識がある」と答えた。両方の言語への苦手意識を合わせて集計すると、「手話にも日本語にも苦手意識がある」と答えた人が34%、「日本語にはないが手話に苦手意識がある」人が30%、「手話にはないが日本語に苦手意識がある」人が20%という結果になった。手話に対する苦手意識は、自分の言いたいことが相手に伝わっていないと認識したり、通訳がうまくできないという思いを持ったりした時に感じられることが多かった。また、「家族以外のろう者」とのやりとりや、「手話をする聴者」との比較が、手話に苦手意識を持つコーダにプレッシャーとなってかかっている面があることが窺えた。日本語に対する苦手意識は、子供の頃には理解や発音や文章力などの点で、思春期以降にはうまく話せないとかタイミングを逃してしまうといった発言上の困難などで、さらに社会人になってからは職場や通訳の場で適切な言葉の使い分けが難しく思えることなどで、認識されるようだった。こうした中には日本語のモノリンガルでも感じるであろう表現上の困難も含まれているが、それを「日本語が苦手」という解釈と結びつけて考えやすいところに、コーダの特徴が出ていると言える。また、「日本語が苦手」という時の日本語のレベルは、「手話が苦手」という時の手話のレベルよりも高くなっているようだった。ここには、日本社会において、手話は少数派言語であり日本語は多数派言語であるという言語状況が反映されていると思われる。
手話に関しては、多くの回答者の場合、それを普段使う相手が両親のみになってしまっていた。そのような状況では、目にする手話の内容も限られてしまい、「生活言語」のレベルを超えた高度な内容を手話で話せるようになるためには、手話の力をステップアップさせる必要が出てくるようだった。しかし、日本語の場合には、学校教育によって「生活言語」から「学習言語」のレベルへ移行させる流れができているが、手話の場合には、子供がそのように言語力を磨いていく機会が作られていない。日本語と手話のこうしたギャップは、思春期頃になると、親子間のコミュニケーションの不全感として現れてくることも多いようだった。実際、「親と深くコミュニケーションできていないという思いがあったか」という質問に関しては、半数を超える人が「ある」と答えている。思春期には、子供の頃に比べて話の内容も幅も広がってくるが、それを話せるだけの手話の力を身につけたり、聞こえる人向けの話し方と聞こえない人向けの話し方の使い分けを知識として知ったりする環境が、コーダの年齢に合った形で用意されていないのである。こうした状況を受けて、自分に説明できないことは親に対する説明そのものを省いてしまうという方法をとるコーダも、けっこういるようである。
手話の勉強をしたことがあるかという質問に対しては、回答者の70%以上が「ある」と答えた。やはりその動機として多かったのは、「親ともっと深く話せるようになりたい」というものだった。また、「通訳の技術を身に付けたい」とか「親以外のろう者とも話せるようになりたい」という答えも多かった。こうした人たちが手話を学ぶ場は、地域の手話講習会や手話サークル、専門的な手話通訳養成機関などだった。やはり、ある程度の年齢になってから、手話通訳養成を最終的な目標とした成人向けの手話学習の場に行って勉強するという形が多いようである。
<通訳について>
子どもの頃の通訳の体験に関する質問では、自分は通訳を「かなりした」もしくは「時々した」と認識している人が全体の4分の3を占めた。また、家の中で一番通訳したのは自分であるという意識を持っている人も6割近くいた。行なった通訳の内容としては、日常生活に関すること(買い物や電話、親戚との連絡・・・)や、学校関係の行事(面談や家庭訪問)など、「子ども」という立場と馴染むものが多かった。しかし、医療や行政、金融や親の仕事関係の通訳など、「子ども」が担うには重過ぎる通訳を経験していた人も少なくなかった。こうした場での通訳は、交渉や接客、取次ぎなど、単に通訳するだけでなく、判断や話術が必要であり、しかも失敗した時に重大な結果をもたらしてしまうというプレッシャーがかかってくる。通訳派遣制度がある程度整うようになる以前には、「子ども」という立場でこうした状況に対処してきたコーダがかなりいたようである。
通訳の体験は自分にとってどのようなものだったかという質問に対しては、「嫌だった」「子どもには難しい」など、否定的に答えた人が多かった。日常生活に関する通訳などは、「面倒くさい」ものとして感じられたようである。しかし、その一方で、通訳をするのは「あたりまえのことだった」とか「特に何も思うことはない」と書いている人もずいぶんいた。おそらく、回答者の大半にとって、子供の頃には通訳するのは「あたりまえ」だったが、自分の気持ちとしては「あまりやりたくなかった」というのが正直なところなのであろう。しかし、当時は嫌だったが、大人になってから振り返ると「いい体験」だったと書いている人も複数いた。
親に対する通訳と一般のろう者に対する通訳は同じだと思うかという質問に対しては、「違うと思う」と答えた人が全体の4分の3を占めた。親に対する通訳では、自分の主観や感情が入る反面、普段から接している時間が長いために、親がわかる方法で通訳できるし変更もきくという安心感があるようだった。
コーダが手話通訳者になることに関しては、内外から強い期待がかかっているのが示された。「手話通訳者になったら?」という言葉は、「ろう者」(親、親の友達のろう者、ろうの友人)や「手話をする聴者」(手話通訳者、手話学習者)だけでなく、「一般の聴者」からもかけられていた。こうした期待を受けて、自分自身も手話通訳者になることを考えたことが「ある」と答えた人は、全体の67%にのぼった。ただし、自分の持っている手話の力や聞こえない親と暮らした経験をスキルとして評価するようになるのは、ある程度年齢がいってからと言えそうである。すなわち、他の一般的な聴者と比較したり能力について考えたりしていく中で、自分の経験や環境を「生かす」という気持ちも働き、他の人よりは手話ができるし聞こえない人の気持ちがわかるということを、自分の利点として認識するようになっていくようだ。しかし、そのような気持ちを持って手話の勉強はしても、実際に職業的な手話通訳者になるかどうかはまた別で、半数以上の回答者は「自分は手話通訳者ではない」と答えていた。その中には、自分の今の仕事と絡めながら、聞こえない人と関わるということを大切にしている人もかなりいるようだった。
<親が聞こえないことと聞こえる社会との関係について>
うちはほかと違うという意識を持っていたかという質問に対しては、67%の人が「持っていた」と答えた。そうした意識は、聞こえる人の反応(手話や親の声、フラッシュベルなどに対する反応)や、聞こえる人のやり方との比較(友達の家の親子関係や生活習慣との比較、親(のやり方)が一般的な聞こえる人の中で浮いて見えること)、普通は親がすることを子供の自分がしたりすることなどからもたらされていた。しかし、親が聞こえないことでいじめられた経験を持つ人は回答者の3分の1に留まった。また、何か問題が起きると親が聞こえないせいにされるという意識を持っていたのも、3分の1程度だった。
逆に多かったのは、まわりの聞こえる大人から「大変ね」「かわいそう」「あなたががんばるのよ」と言われた経験である。85%もの人が、そうした言葉をかけられた経験が「ある」と答えた。そうしたことを言うのは、「親戚」や「近所の人」、「学校の先生」が多かったが、その一方で、あまり深い関わりを持っていない一般の人も多かった。こうした言葉を言われた時の思いとしては、自分の感覚とは合わないと感じた人が大半だった。それは、不思議さや違和感として表現されたり、「自分は人からはそう見えるのか~」という外部の視点の発見として語られたり、実情を知らないままいろいろ言われることへの反発として語られたりしていた。
親が聞こえないことを自分からまわりに言っていたかどうかという質問では、「機会があれば話していた」に○をつけた人が半数以上にあたる22人、「隠しているという意識はないが、特に言わなかった」に○をつけた人が11人という結果になった。しかし、親が聞こえないことを人に言うかどうかは、時期によって変わってくる面も大きいようだ。実際、子供の頃にはあまり言わなかったけど今は機会があれば話すようにしているという人はかなり見られた。
両親が聞こえる人と一緒の時に自分が音に敏感になることはあるかという質問に対しては、半数以上の人が「ある」と答えた。それは、親の出している音を他の聴者に変に思われないようにするという場合と、親に音の情報を知らせなければ(音の意味を通訳しなければ)という場合の2つがあるようだった。前者に関しては、声の大きさや物を食べたり飲んだりする時の音、ドアの開閉、携帯の着信音など、聴者であれば立ち居振る舞いやマナーとして捉えられるものが多く挙がった。後者としては、呼びかけられたり(声、ベル)、物が落ちたり、車が近づいていたりといった周囲の状況を気づかせるという面と、放送のように音声で流された情報を説明するという面が挙げられた。
思春期の頃に親を一般の聴者より低く見てしまったことはあるかという質問には、半分以上の人が「ない」と答えた。「ある」と答えたのは45%に留まった。しかし、「ある」と答えた人たちに具体的な点を尋ねると、日本語や文章力の不足、情報の不足やそこから来る「常識」の不足、学力、生活水準などが挙がった。こうした事柄は、「聞こえないこと」を取り巻く環境とも密接に結びついていると言える。そのため、コーダが反抗期を過ぎて、ろう教育の実情を知ったり自分が社会に出て経験を積んだりしていくと、制約を受けながらも生きてきた親を評価し、積極的にサポートする方向へと変わってくることが多いようだった。
<コーダであることの認識について>
親が聞こえないことや自分の体験について他のコーダやきょうだいと深く話したことがあるかという質問に対しては、67%の人が「ある」と答えた。そのようなことを話した時期としては、10代後半から30代にかけての若い時期が多かった。多くの回答者は、コーダと話をすることに、自分だけではないという安心感を覚えたり、共感したりしてもらえたりする嬉しさを感じたり、プラスの意味を見出していた。コーダであることの話は、コーダ同士では笑い話になったり盛り上がったりするが、一般的には関心を持たれなかったり、逆に重く響きすぎて誤解を招いてしまったりする。そのため、なかなか表に出てきにくい構造があるようである。しかし、コーダ個人にとっては、他のコーダとの共通点や相違点を知ることは、自分の状況を客観的に整理したり自分と親の関係を見直したりする手がかりとして役立っているようである。
聞こえない人のやり方と聞こえる人のやり方は違うとか「ろう文化」といった情報を知っていたかどうかという質問では、全体の87%にあたる35人が「知っていた」と答えた。その時期としては、高校卒業後~20代前半が最も多く、「手話の勉強をする中で知った」とか「ろう者から聞いて知った」というケースが多かった。「ろう文化」の考え方は1990年代になって日本に紹介されたものであるため、親から教えられるというよりは、体系的な手話学習などを通して知識として知ったり、若い世代のろう者やコーダとのつきあいから情報がもたらされたりしているようである。しかし、「ろう文化」とほぼ同時期に紹介された「コーダ」という言葉に関しては、他のコーダから聞いた(外国のコーダやきょうだいを含む)とか本を読んだとか、「ろう文化」よりももっと個人的な人脈や体験を通して情報が入手されている。その傾向は、「コーダの会」に関する情報の場合にはさらに顕著で、それらはほとんどコーダ同士の口コミを中心に伝達されている。
同年代のろう者やコーダとのつき合いに関する質問では、それぞれ半数程度の人が、「プライベートでもやりとりがある」と答えた。また、回答者のうちの3人は「聞こえない配偶者がいる」と答えた。しかし、全体的に見て、同年代のコーダと出会うのは同年代のろう者と出会うよりもさらに機会が限られていると言えそうである。ろう者とは手話の学習や通訳活動などを通じて出会うこともそれなりにあるが、コーダはろう者ほど組織化されておらず、「コーダ」と名乗りをあげている人も少ない。そのため、「プライベートでやりとりがある」といっても、コーダ同士のつきあいは各回答者間で重なっている度合いが高く、実際には特定の場(「コーダの会」やろう者の教会、手話通訳養成の場など)を通して知り合ったコーダ同士が一部で密な付き合いをしていると見るのが妥当ではないかと思われる。
異性とつき合う時に相手が聴者かろう者かを意識するかという質問に対しては、4分の3の人が「意識しない」と答えた。また、ろう者との交際を「想像できる」と答えた人は40人中30人、コーダとの交際を「想像できる」と答えた人は32人で、回答者の多くは、交際相手が聴者かろう者かコーダかということにあまりこだわっていなかった。しかし、聞こえないことに関する理解や手話に関する面で結婚相手への希望はあるかという質問に対しては、62%の人が「ある」と答えた。この質問の場合、結婚相手として想定されたのは「聞こえない人とあまり接点を持ったことのない聞こえる人」であったようで、具体的には、「少しでもかまわないので手話を覚えてほしい」といったものが多かった。また、「どんな方法でもかまわないので親と直接話そうとする気持ちを持ってほしい」とか、「聞こえる人の場合と同じように接してほしい」、「理解してほしい」という答えも見られた。
今回のアンケートで、コーダの傾向がかなりはっきり出たと思われるのが、人工内耳に対する態度である。質問では、「人工内耳をどう思うか」という問いのほか、比較のために、体内に機械を埋め込む他の技術(たとえば心臓を補助するためのペースメーカーなど)をどう思うかを尋ねた。これらの質問に対し、回答者のうちの16人は、人工内耳もペースメーカーも同じ医療技術として捉え、両方に同じ態度(両方にマイナスの印象を持ったり、両方に対して特に何とも思わなかったり、両方を評価したり)を示した。しかし、回答者の半数近くは、人工内耳に対する態度とペースメーカーに対する態度が明らかに異なり、人工内耳をペースメーカーよりも否定的に捉えていた。ここからは、医療技術全般はある程度評価しながらも、人工内耳についてはマイナスの印象を持つ人がかなりの数いることが指摘できる。一方、もし自分の子どもが聞こえなかったら人工内耳をつけさせるかどうかに関しては、57%の人が「つけさせたくない」と答え、30%の人が態度を留保した。つけさせたくない理由としては、「自然なままがよい」、「人工内耳のリスクや代償(不安定なアイデンティティの問題も含む)への懸念」、「聞こえない子を否定したくない」というものが多かった。態度を留保する理由としては、本人の意志や聞こえの状況、その時の人工内耳の技術水準を見て考えたいという答えが多く挙がった。このように、人工内耳に対して慎重な態度をとる人が多いということ自体、一般の聞こえる人の反応と対照的であると言える(澁谷は大学で授業をする際によく人工内耳の問題を問いかける。一般の聞こえる学生は、「ろう文化」を尊重したいと考えつつも、自分の子供が聞こえないとなると、人工内耳をつけさせる方向に傾く傾向にある。それは、「子供の世界を広げてあげたい」という親の愛情として語られる)。
聞こえない親を持つことの特性とはどういうことだと感じているかという最後の質問に対しては、複数の文化にまたがって育つことに着目して記述した人が多かった。それは、二つの言語や文化を知ることで世界や体験が広がったり、多様性や異なる文化を受け入れやすくなったりしたというように、肯定的に語られることが多かった。また、洞察力やコミュニケーション能力にすぐれていることにふれた人、特に意識することはなく普通だと思っていると答えた人もいた。
アンケートの集計結果
質問1 当てはまる性別を教えて下さい
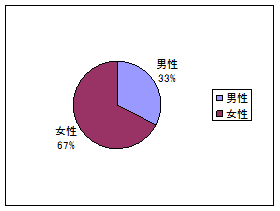
質問2 当てはまる年齢区分を教えて下さい
|
|
N=40
|
|
14歳
|
1
|
|
15-20歳
|
3
|
|
21-25歳
|
6
|
|
26-30歳
|
8
|
|
31-35歳
|
13
|
|
36-40歳
|
2
|
|
41-45歳
|
2
|
|
46-50歳
|
1
|
|
51-65歳
|
2
|
|
無記入
|
2
|
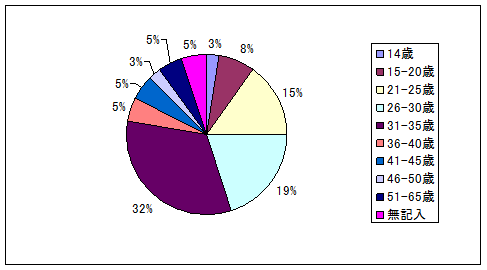
考察
回答者の性別は、男女比が1:2であった。年齢別に見ていくと、20代と30代が多く、これらの人々が全体の7割を占めている。概要でも述べたように、性別や年齢層に偏りが見られるのは、このアンケート調査が、主に「コーダの会」のメーリングリストや、調査者が「コーダの会」で知り合ったコーダの紹介を通して行われたという調査方法と関係があると思われる。さらに大きな要因としては、男性よりも女性のほうが手話に関わる活動をすることが多いという状況、そのために女性のほうが「コーダ」として自認したり名乗りをあげたりする機会が多いということも関わっていると考えられる。
質問3 自分の育った家庭の家族構成について教えて下さい
きょうだい関係
|
|
N=40
|
|
一人っ子
|
5
|
|
ろうのきょうだいがいる
|
2
|
|
聞こえるきょうだいがいる
|
30
|
|
無記入
|
3
|
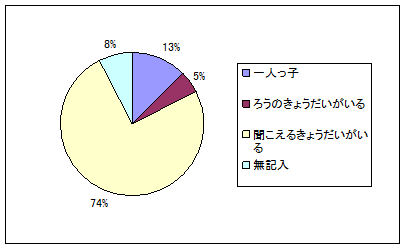
長子である人:21人
長女である人:17人
2人きょうだいで姉がいる人:7人
考察
家族構成としては、親と子どもから成り立つ核家族が多数派だった。質問8も合わせると、祖父母と同居していた(一時的な同居や部分的な同居も含めて)と書いたのは、全体の5分の1にあたる8人だけだった。
きょうだいに関しては、全回答者の4分の3には、聞こえるきょうだいがいるという結果になった。「ろうのきょうだいがいる」と書いた回答者は2人、「きょうだいはいない」と答えた回答者は5人だった。さらに細かく見てみると、回答者の半分は長子(一番上の子ども)だった。また、長女である人(必ずしも一番上ではなく、兄がいる場合も含む)は、17人だった。アメリカの150人のコーダにインタビュー調査を行ったポール・プレストンは、『聞こえない親をもつ聞こえる子どもたち』という本の中で、コーダの中で家族の中心的な通訳を務めることが多いのは、下の子よりは上の子であり、男の子よりは女の子であると指摘している。調査者の今までのインタビュー調査では、その傾向は日本の場合でもかなりの程度当てはまるのではないかと思われる。
なお、このアンケートの回答者の中には、きょうだいが5組(それぞれ2人ずつ)含まれていることにもふれておきたい。
質問4 家の中の通信機器などについて、当てはまるものに印をつけたり記入したりして下さい
<電話>
|
|
N=40
|
|
生まれた時から
|
13
|
|
小学生以前(6歳以下)
|
5
|
|
小学生期(7-12歳)
|
11
|
|
中高生期(13-18歳)
|
4
|
|
19歳以上~20代前半
|
1
|
|
20代後半~40歳未満
|
0
|
|
40歳以上
|
0
|
|
その他
|
1
|
|
不使用
|
0
|
|
無記入
|
5
|
書き込みのある回答
・ はっきりは覚えていないが、物ごころついた時にはありました(←「その他」にカウント)
・ 5歳(母方の祖父母の隣に住むようになった)
<FAX>
|
|
N=40
|
|
生まれた時から
|
5
|
|
小学生以前(6歳以下)
|
2
|
|
小学生期(7-12歳)
|
14
|
|
中高生期(13-18歳)
|
9
|
|
19歳以上~20代前半
|
3
|
|
20代後半~40歳未満
|
1
|
|
40歳以上
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
不使用
|
2
|
|
無記入
|
4
|
<携帯メール>
|
|
N=40
|
|
生まれた時から
|
0
|
|
小学生以前(6歳以下)
|
0
|
|
小学生期(7-12歳)
|
0
|
|
中高生期(13-18歳)
|
7
|
|
19歳以上~20代前半
|
8
|
|
20代後半~40歳未満
|
12
|
|
40歳以上
|
1
|
|
その他
|
0
|
|
不使用
|
3
|
|
無記入
|
9
|
書き込みのあった回答
・ 20歳 最初は父その半年後ぐらい後が母
・ →親は持っていない。
・ 親は使用なし
・ 33歳(母親)
<インターネット>
※「使う」と答えた12人のうち、4人は「父のみ」「父親のみ」という書き込みをしていた。
書き込みのあった回答
・ 使わない(携帯では使ってるようです)
考察
家の中の通信機器の存在は、コーダの通訳の体験とかなり関わっている。どんな通訳をしたかに関する質問19でも、「電話通訳」を挙げた人が9人いた。インタビュー調査では、家に電話が来る前に、小銭を持って公衆電話に行って通訳をしたという経験を語った人も見られた。このアンケートでも、60代のある回答者は、通信機器のすべてに無記入で「無し」と書き込みをしている。時代が下り、ファックスや携帯メールがある程度普及してくると、今度はコーダが文章のチェックや説明をしたり、親が自分で連絡をとったりすることが増えてきたようである。しかし、携帯メールに関しては、20代後半~40歳未満の時に親が使うようになったと答えた回答者が最も多かった。おそらく、携帯メールは回答者が実家を出てから親が使うようになったケースも多く、今回の回答者の通訳体験にそこまで影響していないとも言えそうである。
インターネットを使う親は、全体の3分の1以下に留まった。また、母親は使わないが父親は使うという書き込みがなされたケースが4例あった。しかし、きょうだいの回答者の回答を比べてみると、親がインターネットを使うかどうかはきょうだいで違っていることもあった。インターネットの普及はかなり最近のことであるので、親が実際にどこまで使っているのか、親と同居していない場合にはわかりにくいのかもしれない。
質問5 両親の小学校~高校の教育環境について、教えて下さい。
<父>
|
|
N=40
|
|
小学部から高等部までろう学校
|
31
|
|
小学部から中等部までろう学校
|
2
|
|
ろう学校と普通校
|
2
|
|
その他
|
3
|
|
無記入
|
2
|
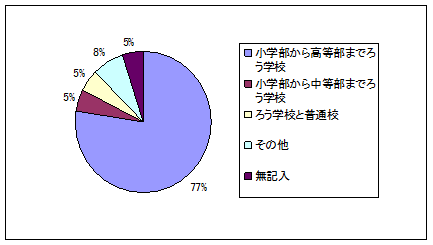
※選択肢には入っていなかったが、何人かの回答を受けて、「小学部から中等部までろう学校」のカテゴリーを作成した。具体的なろう学校の名前を記入した回答者もいたが、集計にあたっては、その部分は載せないことにした。
「その他」の答え
・ 小学部の途中から高等部までろう学校
・ 聴者のため、普通校(←父親が聞こえる回答者)
・ 未就学
書き込みのあった回答
・ 小学部から高等部までろう学校(教育を受けたのは大正から昭和にかけての年代です)
・ 小学部から高等部までろう学校(小1は普通校に入学、小2に上がるときに聾学校小学部1年に改めて入学)
・ ろう学校と普通校(小学5年生からろう学校、それまでは普通校)
<母>
|
|
N=40
|
|
小学部から高等部までろう学校
|
33
|
|
小学部から中等部までろう学校
|
2
|
|
ろう学校と普通校
|
2
|
|
その他
|
1
|
|
無記入
|
2
|
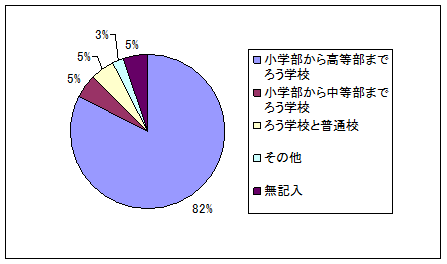
「その他」の答え
・ 小学校~中学校まで普通校
書き込みのあった答え
・ ろう学校と普通校、その他(学校に通えなかった時期もあるようです)(←この回答は「ろう学校と普通校」に入れ、「その他」のところに関しては書き込みをそのまま載せるという形をとりました。そのため、「その他」としてはカウントしていません)
・ 小学部から高等部までろう学校(教育を受けたのは大正から昭和にかけての年代です)
・ 小学部~中学部までろう学校(10年前の心理判定で「知的障害あり」との判定←私自身は経験不足からくるものだと認識しています)
考察
父親も母親も、学校教育は一貫してろう学校という回答者が圧倒的多数だった。これは、ろう者コミュニティがしっかりと存在している中で手話や聞こえない人のやり方(人間関係や会話の仕方、価値観なども含めて)を身につけた親を持っている人が多数派であることを意味している。一方で、この質問の回答からは、今回の回答者の親の世代では、ろう者が教育にアクセスしたり高校以上の高等教育を受けたりすることのできる環境が充分に整っていなかった面があることも窺えた。こうした状況は、世代によって変わってきそうである。最近の若い世代では、聞こえなくてもろう学校に行った経験のない人が増えているため、今後のコーダの経験は変わってくる面があることも予想される。
質問6 両親は、ろう協やろう者の団体に関わっていますか?近いと思うものに○をつけたり記入したりして下さい。
<父>
|
ほとんど関わっていない
|
9
|
|
行事などに行っている
|
6
|
|
運営や企画にもかなり関わっている
|
14
|
|
その他
|
12
|
|
無記入
|
1
|
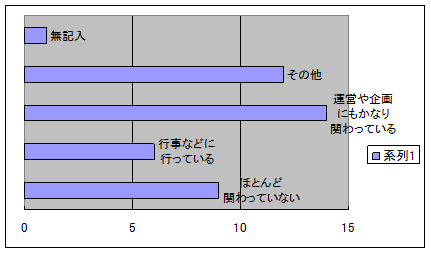
「その他」の回答
・ 旅行好きなろう者が集まり、年に何度か一緒に旅行に行ったり、飲み会など開いています
・ 講習会講師等
・ 聴覚障害者の共同作業所に通っている。地域の手話サークルに参加している。
・ 聴覚障害者の理容師団体に関わっている
・ 聾者のクリスチャン教会に行っている
・ 聾者のクリスチャン教会に行っている
・ ずっと前は深く関わっていましたが現在は関わっていません
・ 過去に運営や企画にもかなり関わっていた
・ 亡くなる前は活動をしていた
・ 昭和59年死亡
・ 聴者のため、関わっていない(←お父さんが聴者という回答者)
・ わかんない
書き込みのある回答
・ 運営や企画にもかなり関わっている(神奈川県、横浜市のろう協、設立の中心的役割を果たした)
・ 運営や企画にもかなり関わっている(ろうあ協会会長)
・ 運営や企画にもかなり関わっている(今はあまり関わっていないが)
<母>
|
ほとんど関わっていない
|
12
|
|
行事などに行っている
|
10
|
|
運営や企画にもかなり関わっている
|
13
|
|
その他
|
8
|
|
無記入
|
1
|
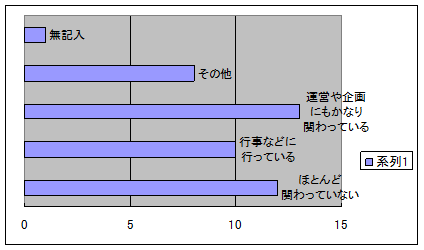
「その他」の回答
・ 父と同じグループに(←「父」の欄の「旅行好きなろう者が集まり、年に何度か一緒に旅行に行ったり、飲み会など開いています」という答えを受けて)
・ 講習会講師等
・ 父と同じ作業所に通っている。作業所が参加する行事にだけ行く。
・ 聾者のクリスチャン教会に行っている
・ 亡くなったが、生前クリスチャンの教会に行っていた
・ 過去に運営や企画にもかなり関わっていた
・ わからない!
・ わかんない
書き込みのある回答
・ 運営や企画にもかなり関わっている(婦人部部長)
考察
ろう協やろう者の団体と親がどういう関わり方をしているかは、まちまちだった。しかし、全体的に見て、「運営や企画にもかなり関わっている/関わっていた」と答えたり、職業関係や宗教関係のろう者コミュニティに関わっていると答えたりした人は、全回答者の半数近くを占めていた。ろう者が集まるコミュニティに深く関わっているということは、ろう関係の情報がそれなりに入ってくる立場にいたと考えてよいだろう。おそらく、もっと若い世代(現在20代ぐらい)のろう者の場合には、そのように、ろう者団体に組織的な関わりをする人の割合はもっと少なくなっているのではないかと思われる。
質問7 家族や親戚に両親以外に聞こえない人はいますか?
|
|
N=40
|
|
いる/いた
|
19
|
|
いない
|
19
|
|
無記入
|
2
|
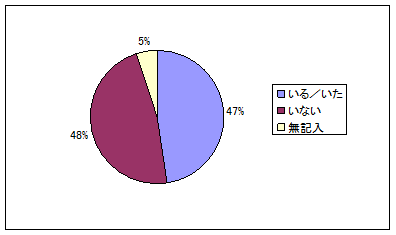
「いる」と答えた方は、具体的に何人か、自分から見てどういう立場の方か教えて下さい
(←集計するにあたって、「具体的に何人か」という質問は不適切だったとみなし、集計からはずしました。というのも、既に亡くなった人を数えるかどうか(特に、自分があまり関わる前に亡くなってしまった場合などは判断が難しかったようです。きょうだいでも人数が違っているケースがかなり見られました)、親戚の範囲をどこまで広げるか(「義理のきょうだい」などについてはカウントする人としない人がいました)、それぞれの回答者の判断にゆだねられてしまい、答え方がバラバラになってしまったからです。質問の後半の「どういう立場の方か」の部分に関しては、具体的に書かれた回答をそのまま載せることにしました。)
|
叔父・叔母(または伯父・伯母)
|
17
|
|
いとこ
|
2
|
|
祖父母
|
4
|
|
自分のきょうだい
|
2
|
|
義理のきょうだい
|
1
|
|
いとこの子供
|
1
|
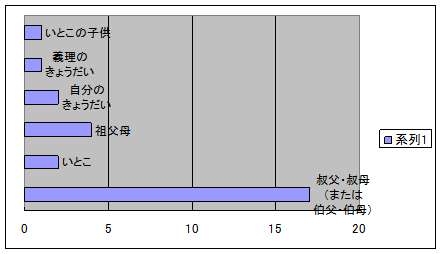
考察
親戚に聞こえない人がいると答えた人の中では、叔父・叔母(もしくは伯父・伯母)が聞こえないというケースが圧倒的に多かった。自分の親のきょうだいとその配偶者がろう者という場合もかなりあるようで、このような回答者は、自分の家庭以外にろう者の家庭やコーダのいとこを見てきた経験を持っている。質問26と合わせて見ると、こうした体験は、自分の家庭を相対化する(自分の家だけではないと知る)上で、大きな役割を果たしているのではないかと考えられる。
親以外の聞こえない人が自分のきょうだいであると答えた2人の回答者の場合には、家庭の中で、聞こえるのは自分だけという状況だった。アメリカのポール・プレストンのコーダ研究やオーストラリアのコーダの映画(「国のないパスポート」)に出てくる例も考え合わせると、このような場合には、聞こえる自分だけ仲間に入りきれないような面(「聞こえない」という体験そのものは持っていないことや、聞こえるという立場ではろう学校関連やろう者中心の話のやりとりなどについていけない面があること)もあったのではないかと思われる。それは、きょうだいを持たない一人っ子コーダについても言えることだが、一人っ子コーダの場合には、「親=聞こえない」「子供=聞こえる」のように「親」と「子供」という対立軸で考えられる面もあるのに対し、ろうのきょうだいがいるコーダの場合には、聞こえる自分の存在がよけいに浮き立ってしまうと言えそうである。
質問8 自分が小学校頃までのおじいさん・おばあさんとの関わりについて、教えて下さい。
|
|
N=40
|
|
聞こえない祖父母がいる/いた
|
4
|
|
聞こえない祖父母はいない
|
34
|
|
無記入
|
2
|
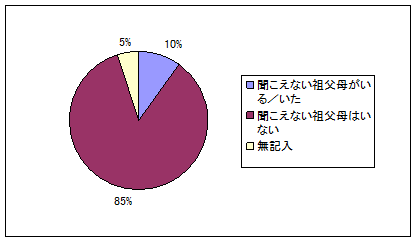
おじいさんおばあさんとは、 一緒に生活していた
ほとんど毎日会っていた
一週間に1回ぐらい会っていた
月に数回会っていた
ほとんど会わない
もう亡くなっていた
(←この質問についても、質問の仕方が「父方」と「母方」に分かれておらず、回答者の方々の混乱を招いてしまいました。そのため、集計も整理するのが難しいという状況です。ここでは、細かい具体的な内容を書き込んで下さった方の書き込みを紹介するに留めます。)
具体的な書き込みのあった回答
・ 一緒に暮らしていた(母が理容業を営んでいる関係で、父方の祖母が主に経営者として接客・経理などを担当してくれていた。父方の祖父母には別宅があった為、営業時間のみ祖母がお店に通っていた状態。小学6年生の時に祖父がなくなり、それからは同居している。)
・ 一緒に生活していた(母方の祖母を両親は引き取り)
・ 一緒に生活していた(母方の祖父母、6歳まで)、ほとんど毎日会っていた(6歳~12歳まで)
・ ほとんど毎日会っていた(家が隣)
・ おじいさん もう亡くなっていた
おばあさん 一緒に生活していた 保育園入園後、言葉の遅れを指摘されてから、17才まで。“無償の愛”を私に教えてくれた人。祖母がいなければ今の私はいなかったと思うくらい大きな存在だった
・ ほとんど会わない。田舎が遠い為、里帰りの時くらいしか会わなかった。
・ 聞こえる父方の祖母とはほとんど毎日会っていた、聞こえない母方の祖父とは、年に数回会っていた
お詫び
この質問は、それまで調査者がコーダやろう者の方々から断片的に話を聞いてきた中で、「子どもの日本語環境を作るため聞こえる祖父母が同居するケースが多いのだろうか?」という予測を立て、作った質問でした。しかし、今回の集計から見てみると、祖父母と同居していたと答えた8人の中には、祖父母の高齢化による介護のためとか、それ以外の要因も含まれているようでした。また、祖父母との関わりの頻度にしても、単に遠いからあまり会わないとか、同居はしていないけど頻繁に会うなど、調査者の予想を基に作った選択肢自体が無意味でした。質問13との絡みでも、祖父母との関わりが日本語の苦手意識を左右するということはなさそうでした。
仮に、聞こえる祖父母との同居がコーダの日本語環境にどの程度関わるかをしっかり見ていこうとするならば、祖父母と幼少時から同居していたという人を何十人も集め、生活の形態(食事を一緒にしているか、接点がどれだけあるかなど)や年齢、聞こえる姉や兄の影響なども考慮した上で、発する言葉の数や種類を分析していくという、気の遠くなるような実験が必要になりそうです。その意味で、今回は、質問の作成の仕方に問題があったことをお詫びしたいと思います。
質問9 家の中でのコミュニケーション方法について教えて下さい。
<自分→母>
|
声
|
9
|
|
口話(声なし)
|
20
|
|
身振り
|
19
|
|
手話単語
|
20
|
|
手話
|
34
|
|
筆談
|
9
|
|
その他
|
3
|
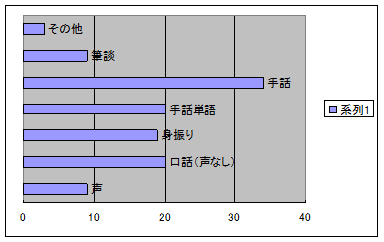
「その他」の答え
・ はっきりした口話(単語のみ)
・ 姉やお父さんの通訳を挟んで
・ 空書
現在と昔の違いを書き込んだ回答
・ 昔 口話 今 手話・口話
(←同一人物の回答なので、量的な集計では「口話:1」「手話:1」としてカウント)
<母→自分>
|
声(手話なし)
|
18
|
|
身振り
|
13
|
|
声つき手話
|
26
|
|
手話
|
22
|
|
筆談
|
4
|
|
その他
|
3
|
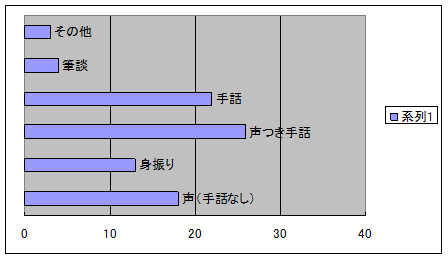
「その他」の答え
・ はっきりとした口話(単語のみ)
・ その他(ふつうにしゃべっているけど、ちょっとだけ手話がつく)
・ その他(手話単語)
書き込みのあった回答
・ 手話(姉か父の通訳つき)(←「手話」としてカウント)
・ 声つき手話(ホームサイン)(←「声つき手話」としてカウント)
現在と昔の違いを書き込んだ回答
・ 昔 声(手話なし) 今 手話(声あったりなかったり)
(←同一人物の回答なので、量的な集計では「声:1」「手話:1」としてカウント)
<自分→父>
|
声
|
8
|
|
口話(声なし)
|
11
|
|
身振り
|
16
|
|
手話単語
|
21
|
|
手話
|
31
|
|
筆談
|
6
|
|
その他
|
4
|
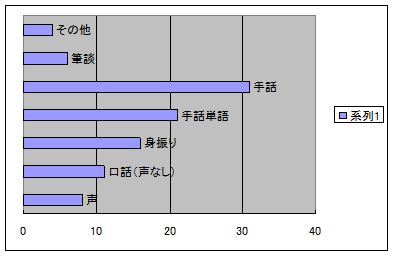
「その他」の答え
・ はっきりとした口話(単語のみ)
・ その他(姉の通訳を挟む)
・ その他(聴者のため、声)(←父親が聴者の回答者)
・ 「手話」と書いて上から×で消している回答
現在と昔の違いを書き込んだ回答
・ 昔 口話、手話単語 今 手話
(←同一人物の回答なので、量的な集計では「口話:1」「手話単語:1」「手話:1」としてカウント)
<父→自分>
|
声(手話なし)
|
13
|
|
身振り
|
12
|
|
声つき手話
|
16
|
|
手話
|
30
|
|
筆談
|
5
|
|
その他
|
6
|
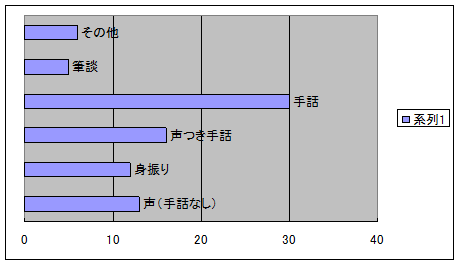
「その他」の回答
・ はっきりとした口話(単語のみ)
・ その他(姉の通訳を挟む)
・ その他(聴者のため、声)(父親が聴者の回答者)
・ 手話単語
・ 手話単語
・ 手話単語
現在と昔の違いを書き込んだ回答
・ 昔 身振り、手話 今 手話
(←同一人物の回答なので、量的な集計では「身振り:1」「手話:1」としてカウント)
両親とのコミュニケーションに関する書き込みのあった回答
・ 両親ともに手話サークルや作業所に通い始めてから、コミュや生活力、情操的なものが格段にアップした。高齢になっても成長し続けることが可能であるということを日々実感している(この経験が、私自身が仕事でケースに関わる際のスタンスにかなり影響していると思う)。
考察
回答者の家の中でのコミュニケーション方法は、かなり多様だった。もちろん、中には手話が基本であったという人もいる。自分と両親の間のコミュニケーションはすべて「手話」だったと答えた人は6人いた。また、自分から父母に対しては「手話」で、父母から自分に対しては「声つき手話・手話」と答えた人は3人いた。このように、全回答者のうち9人(22.5%)は、ほとんど手話だけで親とコミュニケーションをとっていたと言える。しかし、その他の人々は、手話の他に、口話や声、身振り、筆談など、さまざまな手段を駆使していた。
興味深いのは、自分と母との間のコミュニケーションと、自分と父との間のコミュニケーションで、違いが見られたことである。全体的に、母とのコミュニケーションのほうが、声、声つき手話、口話が使われることが多かった。具体的には、自分から母に対しては「口話(声なし)」が多く(母に対しては20、父に対しては11)、母から自分に対しては「声つき手話」(母からは26、父からは16)と「声(手話なし)」(母からは18、父からは13)が多かった。一方、父から自分に対しては「手話」(母からは22、父からは30)が使われることが多かった。
以上のことをまとめると、母はコーダに対して「声つき手話」や「声(手話なし)」を使う割合が高く、コーダも母に対しては「口話(声なし)」を使用することが多いこと、父はコーダに対して「手話」を使う割合が高く、コーダは父に対してはそれほど「口話(声なし)」を使わないことがわかる。
<聞こえるきょうだいと自分の間のコミュニケーション>
(非該当者(聞こえるきょうだいがいない人)は7人←質問3と質問9、インタビュー調査などを合わせた結果)
|
|
N=40
|
|
声のみ
|
22
|
|
その他
|
2
|
|
無記入
|
9
|
|
非該当
|
7
|
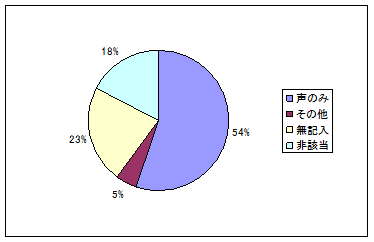
「その他」の答え
・ 声、手話、指文字
・ 声、たまに手話
<自分と聞こえないきょうだいの間のコミュニケーション>
(該当者(「聞こえないきょうだいがいる」と答えた人)は3人。そのうちの1人は義理のきょうだい)
・ 自分からは「口話や手話」、きょうだいからも「口話や手話」
・ 自分からは「口話(声なし)、身振り」、きょうだいからは「声(手話なし)、身振り、声つき手話」
・ 自分からは「手話単語」(義兄に対して)、義兄からは「手話」
<同居している聞こえる家族(祖父母など)と自分のコミュニケーション>
|
|
N=40
|
|
声のみ
|
14
|
|
声、声つき手話
|
1
|
|
無記入
|
25
|
書き込みのあった回答
・ 両親と祖母、私で話すときには両親とのやり取りを祖母に通訳したり、祖母とのやり取りを両親に通訳したりする。声付きの手話はやりにくいのであまり使用しない。
考察
聞こえるきょうだいと、聞こえる同居家族についての質問は紛らわしく、他の質問より「無記入」が多い結果になってしまった。質問に対する回答者の判断もまちまちで、「聞こえるきょうだい」と「同居している聞こえる家族(祖父母など)」の質問の両方に聞こえるきょうだいを含めた人が4人、「聞こえるきょうだい」の質問のところでは書き込まずに「同居している聞こえる家族」のところで聞こえるきょうだいのことを答えた人が2人いた。その他、同居はしていないが毎日会う祖母とのコミュニケーションについて、「同居している聞こえる家族」に含めた回答者もいた。この点については、質問の仕方が悪かったと反省している。
ただ、こうした紛らわしい質問ではあったが、回答者の記入からは、やはり家族の中での聞こえる人とは声のみによるコミュニケーションが圧倒的に多いことが浮かび上がった。
質問10 親はどういう状況で声を使っていますか?
<父>
|
普通に日本語を話している
|
10
|
|
手話に声をつけている
|
14
|
|
単語だけ声を出している
|
12
|
|
自分の名前を呼ぶときに声を出している
|
24
|
|
その他
|
6
|
|
無記入
|
3
|
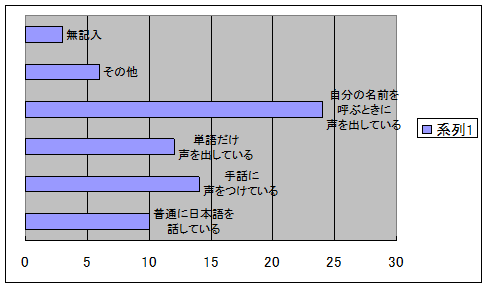
「その他」の回答
・ 「はいわかりました」何か決定した時によく声をだす。「分かりました」「ありがとう」のときも
・ すべての人に対して、ほとんど声は出さない
・ 家にいる時だけ声をだしている。→家族のみ。
・ 口話教育は受けていない。手話での教育
・ 殆んど声は出しません・離れた所にいる人を呼ぶ時、少し声を出していたと思う。・父は私が子供の頃、毎朝近くのパン屋さんに食パンを買いに行くのが日課でした。その時は「パン」の発音はとても上手であった事を憶えております。
・ 自営業なので、お客様には声をだしているが、はっきりとした言葉にはなっていない。結局は、筆談になってしまうが
書き込みのあった回答
・ 遠くにいる自分の名前を呼ぶときに声を出していた。家族以外の人に声を使っているのは見たことがない(←「自分の名前を呼ぶとき」にカウント)
・ 自分の名前を呼ぶときに大きな声を出して呼ぶこともある。はっきりとした言葉にはなってない(←「自分の名前を呼ぶとき」にカウント)
・ 手話に声をつけている:(すべての人)に対して(あまり気にしたことがないので、本当にこうなのかわかりません。たぶんです。)
・ 普通に日本語を話している(自分や姉弟)に対して(他では絶対に声を使わない)
誰に対してか
普通に日本語を話している 10の内訳
・ 相手に関係なく 2 (すべての人に対して1、無記入1)
・ 一般的な聴者に対して 4 (ふつうの人に対して1、ろう者以外の人に対して1、手話のわからない人に対して1、聴者に対して1)
・ 家族に対して 3 (祖父母、自分、弟に対して1、自分や姉弟に対して(他では絶対に声を使わない)1、自分に対して怒っているとき1)
・ 父は聴者 1
手話に声をつけている 14の内訳
・ 相手に関係なく 4 (すべての人に対して3、無記入1)
・ 聴者に対して 4 (一般人に対して1、聞こえる人に対して1、僕を含めた健聴者に対して1、娘や聞こえる人に対して1)
・ 家族に対して 5 (家族に対して1、自分・弟に対して1、私に対して1、祖母・自分に対して1、母・母がいるときに自分・弟に対して1)
・ 聞こえない人に対して 1 (母・ろう者の人に対して)
単語だけ声を出している 12の内訳
・ 相手に関係なく 2 (すべての人に対して2)
・ 一般的な聴者に対して 3 (一般人に対して1、家族以外の健聴者に対して1、聴者と話すときなど1)
・ 聴者に対して 2 (娘や聞こえる人に対して1、手話初心者に対して1)
・ 家族などに対して 5 (私・姉に対して1、弟に対して1、母以外の聴者の家族に対して1、身近な人に対して1、自分に対して怒っているとき1)
自分の名前を呼ぶときに声を出している 24の内訳
・ 自分に対して 23 (無記入21、上の書き込みの回答欄で紹介した回答2)
・ きょうだいも含めて 1 (私や姉を呼ぶ時に声を出す1)
<母>
|
普通に日本語を話している
|
17
|
|
手話に声をつけている
|
23
|
|
単語だけ声を出している
|
15
|
|
自分の名前を呼ぶときに声を出している
|
27
|
|
その他
|
6
|
|
無記入
|
1
|
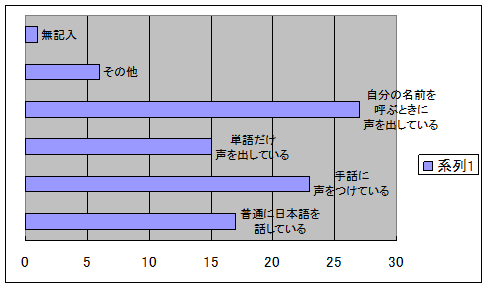
「その他」の回答
・ 父と同じく(←「はいわかりました」何か決定した時によく声をだす。「分かりました」「ありがとう」のときも)。
・ 手話のできない人に「ありがとう」や「はい」など。しかし、明瞭な発音ではない。
・ 家でも外でも声をだしていた。
・ 口話教育は受けていない。手話での教育
・ 殆んど声は出しません
・ 自営業なので、お客様には声をだしているが、はっきりとした言葉にはなっていない。結局は、筆談になってしまうが
書き込みのあった回答
・ 自分の名前を呼ぶときに大きな声を出して呼ぶこともある。はっきりとした言葉にはなってない(←「自分の名前を呼ぶとき」にカウント)
・ 普通に日本語を話している(自分と祖母に対して)、手話に声をつけている(自分に対して)、単語だけ声を出している(自分と祖母に対して)、自分の名前を呼ぶときに声を出している。※いずれも、家の中等、周囲に自分や祖母以外の聴者がいないとき
誰に対してか
普通に日本語を話している 17の内訳
・ 相手に関係なく 8 (すべての人に対して4、誰にでも1、無記入3)
・ 一般的な聴者に対して 6 (ふつうの人に対して1、ろう者以外の人に対して1、手話のわからない人に対して1、聞こえる人に対して1、ご近所・お客様に対して1、 近隣の聞こえる人たちに対して1)
・ 家族に対して 3 (自分と祖母に対して1、祖父母・自分・弟に対して1、父以外の聴者の家族に対して1)
手話に声をつけている 23の内訳
・ 相手に関係なく 3 (すべての人に対して1、無記入2)
・ 一般的な聴者に対して 2 (一般に対して1、手話の分からない聴者と話すとき1)
・ 聴者に対して 3 (手話受講生に対して1、手話がわかる人に対して1、自分・弟を含む聴者に対して1)
・ 家族に対して 13 (家族に対して2、姉に対して1、私・姉に対して1、私・妹・弟に対して1、祖母・私に対して1、私に対して1、自分に対して1、時々、自分に対して1、自分たちに対して1、娘に対して1、自分に怒っているときに対して1、父・父がいるとき自分・弟に対して1)
・ 聞こえない人に対して 2 (父・ろう者の人に対して1、聴覚障害者の人に対して1)
単語だけ声を出している 15の内訳
・ 相手に関係なく 3 (すべての人に対して1、無記入2)
・ 一般的な聴者に対して 3 (一般に対して1、家族以外の健聴者に対して1、会社の人に対して1)
・ 聴者に対して 1 (近隣の聞こえる人たち・自分に対して1)
・ 家族などに対して 7 (家族に対して1、家族全員に対して1、聞こえる家族に対して1、姉と私に対して1、自分と祖母に対して1、弟に対して1、娘・母の兄弟に対して1)
・ 聞こえない人に対して 1 (聴覚障害者の人に対して1)
自分の名前を呼ぶときに声を出している 27の内訳
・ 自分に対して 27 (無記入26、上の書き込みの回答欄で紹介した回答1)
考察
質問9で挙げたコミュニケーション方法の中で、特に「声」に注目したこの質問では、聞こえない親の声の使い方の傾向がかなりはっきりと出た。親が声を使うケースとして最も多いのは、子どもの名前を呼ぶときだった。これは父でも24、母は27という値が出ており、全回答者の半数をかなり越える人が、親は「自分の名前を呼ぶときに声を出している」と答えたことになる。しかし、「普通に日本語を話している」(父は10、母は17)と「手話に声をつけている」(父は14、母は23)という項目では、父親の場合と母親の場合でかなり差が出た。誰に対してかという内訳を見てみると、母の場合、「手話に声をつけている」のは「家族に対して」が群を抜いて多かった。全体的な傾向として、父よりも母のほうが声を使うケースが多く、中でも、手話と併用する形(「手話に声をつけている」「単語だけ声を出している」)は家族に向けて使われることが多いということが言える。
質問11 自分の気持ちを最もよく表せる「自分の言語」は何ですか?
|
手話
|
8
|
|
日本語
|
18
|
|
手話と日本語の両方
|
12
|
|
その他
|
5
|
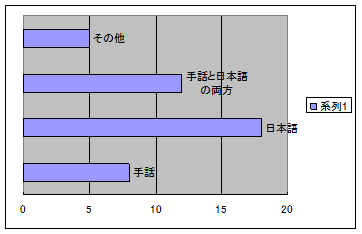
書き込みのあった回答など
・
日本語、その他(具合の悪い時や、日本語にあてはまる言葉がないなど、ふとしたときに手話)
・
日本語(ただ、手話のときは『本当の自分』のような気もする・・)
・
手話、日本語(その時伝えたい内容、感じている気持ちにもよる)
・
手話、手話と日本語の両方、その他
・
手話と日本語の両方、その他(たまにどっちでもない)
・
その時によって。。手話と日本語の両方
・
その他(感情的には手話 論理的には日本語)
・
その他(状況による。基本的に表すのは苦手)
・
その他(手話でも日本語でもない。絶対に“手話”では自分の気持ちを表すことはできない)
考察
回答に書かれたものをすべて計算したところ、上の表のような結果になった。やはり、日本社会において多数派言語である日本語を「自分の言語」と答える人の方が、手話よりも多い結果になっている。年齢に注目すると、10代などの若い世代のほうが「日本語」と答える率が高くなっているようである。
しかし、回答者の書き込みからは、実際には手話と日本語はかなり混ざり合っており、内容や状況によってどちらのほうが使いやすいかが変わってくる面もあることが伝わってくる。回答者の中には、どちらの言語でも自分を充分に表しきれないと感じている人もいた。
質問12 手話に対する苦手意識はありますか?
|
|
|
N=40
|
|
ある
|
ない
|
よくわからない
|
|
26
|
13
|
1
|
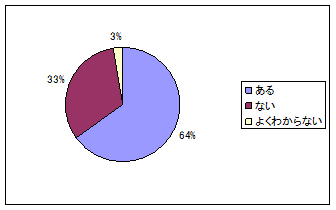
(「ある」と答えた人に対して)手話が苦手だと自覚するようになったのはいつ頃ですか?
・ ずっと
・ 物心ついた時から
・ 物心ついた時
・ 幼い頃(今は苦手ではなくなった)
・ 幼い頃、親の友人たちに「姉はうまいが妹はできない」といわれ意識するようになった
・ 幼稚園のときから
・ 小学生の頃
・ 小学校頃から。
・ 小学生高学年のころ
・ 人前で手話をするのが恥ずかしいと思うようになった頃から。たぶん小学生のときからだと思う。
・ 12歳で両親と同居するようになったとき
・ 中学や高校時代から。進路等で自分の意思や考えがうまく伝わらなかったり、通訳等で伝わったと思っていたことも後に誤解されていたことが分かったりした経験が重なって。
・ 高校生の時に手話サークルに入って、手話に上手い下手があるのを知って。人と比較して。
・ 上京したてのころ(18歳)
・ 19才の頃から!?
・ 20才ぐらいの時
・ 大学入学後
・ 大学に入って他のろう者と接した時
・ 親以外のろう者と会話する時
・ 24歳くらい(家族、家族の知り合い以外のろう者や、手話を理解する聴者と出会い、その方々に、コーダだから手話が分かるはずだろうという目で見られてから)
・ 最初は、高校生の頃にNHKの手話ニュースキャスターが話しながら手話をしているのを見て、“これが手話通訳のあるべき姿なんだ”と思い込んでしまい、それができない自分に自信がなくなった。次は、派遣の仕事に慣れ始めた20代前半、日本語と手話の変換作業に行き詰った時。
・ 周りの通訳者と対等に話せるようになった時
・ 社会人になった23歳くらいから。勤務先のアルバイトの子が偶然手話を習っていて、うちの両親と楽しそうに話しているのを見た時に、「これはやばい」と思いました。
・ 現在(←手話通訳勉強中の回答者)
・ いつ頃かはよくわかりません。
・ ?(←いつかはわからないという意味)
どういう時に苦手だと感じますか?
<言いたいことが通じない時>
・ 言いたいことがうまくいえない時
・ 自分の言いたい事が親父に言えなかった時
・ 自分の言いたいことを相手にちゃんと細かいところまで理解してもらえないとき
・ 意志を伝えたくても正確に伝わらない
・ 複雑に込み入った話をうまくできないとき
・ 自分なりに手話も交えて話しているが通じないとき
・ 親に怒られて理由を求められた時手話で説明が出来ず悔しかった
<通訳をする時>
・ 通訳しなければならなくなったとき
・ 手話通訳をしている時
・ 手話通訳をすることになったときの手話語彙のなさを痛感して
・ 日本語に変換する通訳を頼まれた時
・ TVを見ていて、両親に通訳して欲しいと言われた時(ニュースとかドラマetc…)。
・ 現在では、事務処理的な様々な手続き、親戚中が集まったりするような場での会話の通訳、会話の中で聴者の常識であることを含めて通訳しなければいけないような時には苦手意識を感じる
・ 多くの人の前で注目されている時
<家族以外のろう者と話す時>
・ 家族以外のろう者に対しての通訳時
・ 家族以外のろう者に会って、その人があまり声を出さず早く話す時(手話を使えることが当然と考えている方々)
・ 母以外のろう者と話をする時
・ 東京のろう者が自分の知らない手話単語を使うとき
・ 手話とホームサインを混同した時
<手話を読み取れない時>
・ 相手の手話を読み取れない時
・ 聾者の手話が読み取れない時
・ ろう者同士の話の読み取りの時、口話が付かないと読み取れない
・ 今でも、表出されている手話を正しく理解しているのか不安に思うことがある
・ わからない手話がある
<手話の表現がスムーズにできない時>
・ 聾者みたいに滑らかにできない時
・ むずかしい表現ができない
・ 口だけが先走り手話と口がついていけない時がある!!
<その他>
・ コーダは特別だと思う人がいるとき
・ 性格なのか、codaだからなのか、微妙なニュアンスの違いに妥協できない時がある
・ 覚えるのが面倒くさい
考察
回答者40人のうち、3分の1の人は「手話に苦手意識はない」と答え、3分の2の人が「手話に苦手意識がある」と答えた。「ある」と答えた人の中でも、手話に苦手意識を持つようになった時期は人それぞれ違っていた。コーダが「自分は手話は苦手なのかも」と感じるようになる際に意外と大きな役割を果たしているのが、「家族以外のろう者」と「手話をする聴者」の存在である。実際に「手話が苦手」と感じる場面としては、自分の言いたいことが細部まで相手(特に親)に伝わっていないことを認識したときや、通訳という高度な言語変換作業をうまくこなせなかったという思いを持ったときが多かった。また、親のように日頃からよく接しているわけではないろう者の話を読み取ったり、そのようなろう者と話したりするときには、自分が理解できる手話の範囲や自分の手話が通じる範囲(ホームサインなどの場合も含めて)が限られていることに気づき、それが苦手意識につながっているという傾向も見られた。
質問13 日本語に対する苦手意識はありますか?
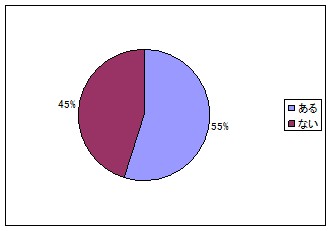
(「ある」と答えた人に対して)日本語が苦手だと自覚するようになったのはいつ頃ですか?
・ 覚えていない
・ 保育園に通っていた頃から
・ 小学校に入ってから
・ 小学校入学以来
・ 小学生の時
・ 小学生の頃
・ 小学生の頃から。
・ 小学生の頃、『さ行』『は行』がうまく発音できなくていじめられた時。
・ 中学
・ 中、高くらいから
・ 高校生くらいから
・ 高校生のとき
・ 二十歳頃?はっきりとは覚えていませんが。
・ 大人になって、
・ 就職してから
・ 社会人になってから
・ 社会人になってから
・ 社会人になってから、強く感じた。
・ 結婚してから
・ CODAと会ってから。
・ つい最近。手話の勉強を始めてから
どういう時に苦手だと感じますか?
<自分の語彙の少なさを感じる時>
・ ことばを知らない時
・ 自分だけ知らずほかの人が知っている言葉があるとき
・ 周りの友達と比べ、自分の語彙力の少なさに気づかされるとき
・ 今は特に苦手と感じる事は減ったが、言葉をあまり知らないと気づかされる時。
<相手の言っていることを理解できない時>
・ 数人での会話の内容が分からない時
・ 小学校に入った時、あまり周りの言っていることが分からなかった時があった。今は、日本語に対する苦手意識はなくなりました。
・ 授業や説明を受けている時。
・ 子どもの頃、授業があまりにも理解できず、「自分は知的障害かも?」とずっと思っていた。
・ すぐに理解できないことから、自分に自信が持てなかった。
<説明がうまくできない時>
・ とっさの一言がいえない
・ 今も自分の思いにぴったりくる日本語が出てこなかったり、言葉の意味が漠然としか理解できていなくて、使い方でつまづくことがある。
・ 言いたい事を適切な日本語で表せない。
・ 様々な場面で…。自分が今どう感じているのか、という微妙な気持ちを表そうとする時…など
・ すごく言いたいことがあって、すぐにでも相手に伝えたいのに、うまく頭の中でそれがまとまらず、何を言ってるのか自分でも分からなくなる時
・ 友達としゃべっていて、自分の身におきた出来事を説明しなくてはいけない時、細部までちゃんと説明できない時。友達はとっても細かく説明してくれますが、私はだいたいしか説明できません。あと、たくさんの友達でしゃべっている時に聞き役に徹してしまう時。これは最近思ったのですが、たくさんの人の中で自分の意見をいうという状況が他の人よりも私はとても少ないため、緊張してあれやこれや考えてしまって、しゃべることができないようです。小さい頃、その日にあった出来事を母親に報告した記憶がなく、弟に話した記憶もないので、「自分の身におきた出来事を説明する」という行動はずっとしてこなかった。だから、今やろうと思っても、なかなか難しいんだと思います。
・ 大学以降――友人や同僚と意見を交すことが多くなったが、自分以外の人が発言したことを理解して、自分の意見にするまでにすごく時間がかかり、発言しようとする頃には話題が変わっていて何も言えなくてツラかった。
・ 話している時に相手が分からないという表情をしたとき、どうやらうまくいえないのだと思う。
・ 思った事をストレートに表現出来なかった時など
・ スピーチや全体で話すとき、また、普段の友人との会話でもうまく話せないことがあったので
・ 日本語よりも手話のほうが自分の思っていることを表現できると思うとき
・ 説明等する時、手を動かさず人に説明することが出来ないことがある。
・ 会社で物事の説明する際に感じた。
・ 自宅にいる時の会話すべて(←「いつ頃?」という上記の質問に対して「結婚してから」と答えた回答者)
<手話から日本語に変えるのに困難を感じる時>
・ 最近は特に読み取り通訳をしているときとても感じる
<文章が苦手>
・ 話したり、文章を書くとき
・ 文章を書くのが苦手。
・ 長文読解問題の意味がなかなかつかめなかったり、要約や読書感想文が苦手であった。
<その他>
・ むぅ~…。
考察
全回答者の半分以上(22人)が日本語に苦手意識が「ある」と答え、18人が「ない」と答えた。いつ頃から苦手意識を感じるようになったかという質問に対する答えを見ると、大まかに分けて、「小学生の時」、「思春期」、「社会人になってから」という分類ができそうである。主に「小学生の時」と答えた人は、友達や先生の言っている内容(授業の内容を含めて)で自分に理解できないところがあると認識したこと、文章を理解したり書いたりするときに難しさを感じたこと、発音の違いを友達に指摘されたことなどを挙げている。聞こえる子供の集団におけるやりとりや、日本語を使った教育が始まった時、内容の理解や発音、文章といった面で、自分はまわりの子供よりも遅れているという意識を持つのかもしれない。「思春期」には、友達との比較ややりとりの中で、自分がうまく話せない、言いたいことがうまく伝えられない、タイミングを逃してしまうことなど、発言する際の困難が自覚され、それが苦手意識につながっている。「社会人になってから」以降では、職場や通訳の場、結婚後の人間関係などにおいて、場や状況に合った言葉の使い分けが求められるようになった時、「適切な」言い方ができないという意識として出てくるようである。
質問12、13を合わせた結果
質問12と13を両方見てみると、次のような結果になった。
|
|
N=40
|
|
手話にも日本語にも苦手意識はない
|
5
|
|
手話に苦手意識がある(日本語にはない)
|
12
|
|
日本語に苦手意識がある(手話にはない)
|
8
|
|
手話にも日本語にも苦手意識がある
|
14
|
|
日本語に苦手意識はないが、手話はよくわからない
|
1
|
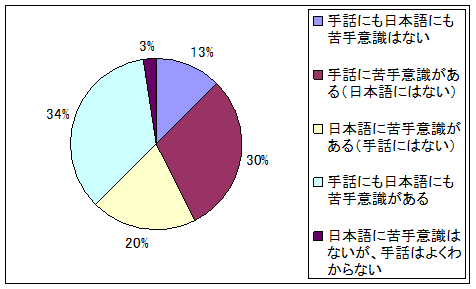
考察
この集計では、「手話にも日本語にも苦手意識がある」人が最も多かった。コーダにバイリンガル的な面があるという認識が広まって、意識が先鋭化してくると、「そういえば・・・」と思い当たる経験が出てきて、苦手意識が補強されるのかもしれない。日本語に関して言えば、スピーチや仕事関係の説明、手話から日本語への読み取り通訳の難しさ、文章に対する苦手意識などは、日本語のモノリンガルでも感じることである。おそらく、「日本語が苦手」という時の日本語のレベルと「手話が苦手」という時の手話のレベルには違いがあり、手話では「通じるか通じないか」が焦点となるのに対して、日本語では「その場の状況や内容、タイミングにぴったりと合った言い方ができるかできないか」というレベルで、苦手意識が形成されるようである。それは、今の日本の社会において、日本語が圧倒的な多数派言語であり、手話が少数派言語であることと結びついている。その意味で、コーダが感じる「日本語への苦手意識」は、日本語への高い関心ともとれる面があることを付記しておく。
「手話にも日本語にも苦手意識がない」と答えた5人は、60歳以上の回答者全員(3人)と、20歳未満の人2人(うち1人は「14歳」と書き込みがある回答者)だった。インタビュー回答者の大半が20代、30代であることを考えると、この世代的な偏りは気になるところである。今回のデータでは、世代差まで考察するにはサンプル数が足りないが、いずれ「なぜ年配の世代では苦手意識を持たない人が多いのか」も考えてみたい。なお、「手話にも日本語にも苦手意識はない」と答えた未成年世代に関しては、苦手意識を持つようになる局面にまだ出会っていないということも考えられそうである。
質問14 手話を親から教えられたという意識はありますか?
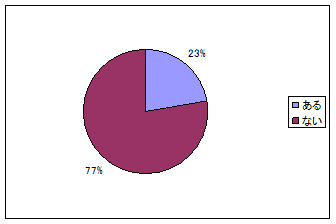
(「ある」と答えた人に対して)どういうふうに教えられましたか?
・ 無意識の内に、日本語と同じ感覚だと思う。
・ 強制的ではないが、自然と親との会話から覚えた様な感じ。(こうゆう場合は「ない」の方が正しいのかな・・・?(汗))
・ 会話中
・ 母が、自宅に集まるろう者のお客様たちとの話を、かいつまんで通訳することを繰り返して
・ たとえば、幼少期に父親とお風呂につかっているときに、都道府県を手話で全部言えるまで上がれない、というような遊び?をしていた
・ この表現はわかる?と聞かれた
・ 表現できない時
・ 指文字、手話。とにかく、使うように仕向けられた?!
・ 小学生前から、1日最低1時間の練習があった
考察
回答者の4分の3が親に手話を教えられたことは「ない」と答えた。「ある」と答えた場合でも、会話や日常生活に沿った場面で教えられることが大半だった。このアンケートから直接導き出されることではないが、インタビュー調査などでは、親がかなり手話を使う場合でも自分は手話の語彙が少ないと語る人が何人か見られる。「食事」「おふろ」といった生活に密着した言葉はわかっても、進路や細かい感情の襞を伝えるのにぴったり来る手話、政治や経済、社会のことなどを伝えるときにどういう手話を使えばいいのかまでは、子供が親からは教えられる機会はあまりない。きょうだいや親戚にろう者がいない場合には、親以外のろう者から手話を教えられる機会はさらに少なく、目にする手話の内容も限られてしまう。このように、手話は、日本語の場合と違って、子どもが「生活言語」から「学習言語」にステップアップさせる機会がない。思春期になって話が複雑になってくる時に細かいところまで説明できないと感じるコーダが多いのは、こうした要因も関わっていると思われる。
質問15 手話を勉強したことはありますか?
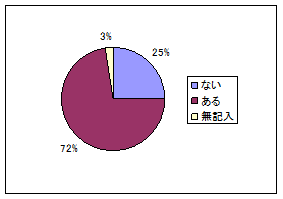
(「ある」と答えた人に対して)どこで勉強しましたか?(○はいくつでもOK)
|
地域の手話講習会
|
17
|
|
手話サークル
|
14
|
|
専門的な手話通訳養成機関
|
10
|
|
その他
|
4
|
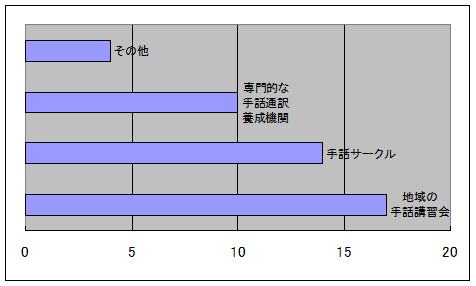
「その他」の回答
・ ろう者の友達をたくさん作るようにした
・ 手話講習会(中級)に参加しようとして、そのテストを受けたことがある
・ 手話通訳事の変換法等
・ NHKの手話講座をたまに見た
手話を勉強してみようと思ったきっかけについて教えて下さい
<親ともっと深く話せるようになりたい>
・ 難しい話をしたときに、親と満足に話せないとわかったときから
・ 大人になって、親に伝えたい事が複雑になり、自分の進路の事など議論した時に限界を感じたから
・ 母ときちんと話ができるようにしておきたいと思ったから
・ お母さんとちゃんと通じるようになりたかった
・ 親父に自分の言いたい事を伝えたかったから。
・ 親とちゃんと話そうと思ったから
・ 親ともっと色んな話しがしたかったから
・ 親とのコミュニケーションの促進、両親の話を、より深く理解したいと思って。
・ 子供の頃(小1)、親との会話に苦労して、講習会へ通いました(6年間)。
<親以外のろう者とも話せるように>
・ 大学時代にろうの学生がいてコミュニケーションを図りたかったから
・ 大学院に入り、ろう者の方との関わりが増えた事がきっかけではあるが、結局そのような場での手話の学習よりも、同じ研究室にろうの学生が入ってきたことで手話を使用する機会や会話の幅が広がった
・ 子育てがひと段落して、地域に聴障者との交流が増え、ちゃんとした(親だけでなく)手話を覚えようと思った
・ 親との会話では、独自の家族内でしか伝わらないオリジナルな手話を使っていたので、他の聴覚障害者と話せるようにもなりたいと思い、高校生の時に手話サークルへ通うようになった。
・ 親以外のろう者と話す時に基本的な手話は理解しても単語力がなかったので、新しい単語を覚えようと思った
<通訳の技術を身に付けたい>
・ 通訳の専門技術を身につけたかったから。
・ 将来の事を考えた時、手話関係の仕事がしたいと思い、その為には、家族だけの手話だけではなく、幅広く勉強する必要があると思い、勉強し始めました。又、手話通訳ができる男の人が少ないということもあったのが、きっかけのひとつです。
・ 通訳者になりたく、手話だけではなく、専門的な(通訳士試験に出るような問題)知識や振舞いを勉強したく。
・ 手話通訳が増えていく時点で
・ 初めは通訳の勉強の為に始めたが、語源を全く知らなかった事で、改めて1から勉強しようと思った部分も有る
・ 通訳というものや手話言語について勉強したかったから
<手話言語について勉強したい>
・ 手話サークルで手話がとても素晴らしい言語と気づき。
・ 日常会話では使わないような手話単語(e.g.政治・経済用語等)を学びたかったから。
<自分は手話をあまり理解していないと気づいた>
・ 24歳の時、家族以外のろう者、手話を理解する聴者と出会い、自分がいかに手話を理解していないか知ったこと。
<なんとなく、いつかは覚えようと思っていた>
・ なんとなく。
・ 大学2年生になった時、なんとなく自分の気持ちにも時間にも余裕ができたから。
・ 親はまったく私達に手話を教えなかったので、いつかはちゃんと覚えようと小さい頃から思っていました。たまたま親が関わっている手話サークルの福祉事務所の職員の方に市主催の講習会があることを聞いてやってみようと思いました。
<特技が欲しかった>
・ 特技が欲しいと思った。社会に入り、ろう者や手話に対する見方も変わった。自分も大人になったのかも?!
<親の勧めや友人の誘い>
・ 友人が手話を学びたいので一緒にサークルに通わないかと声をかけられた。
・ 両親に勧められて。
<その他>
・ 父親の死をきっかけに、思った
・ NO.33で答えた変化(←両親の友だち以外のろう者と知り合いになるまでは「ろうだからできない」「ろうだから理解できない」と思っていたが、そうではないことがわかり、親の見方が変わった)がきっかけで、もっと「ろう者」や「手話」のことが知りたくなった。
考察
全回答者の4分の3近くが、手話の勉強をしたことがあると答えた。コーダが手話を学ぶ場として多かったのは、地域の手話講習会(17人)や手話サークル(14人)だった。また、専門的な手話通訳養成機関と答えた人も10人いた。
手話を勉強してみようと思ったきっかけに関しては、「親ともっと深く話せるようになりたい」という理由を挙げた人が最も多かった。これは、質問32の「自分の気持ちとして、親と深くコミュニケーションできていないという思いはありましたか」という問いに対し、半数を超える22人が「ある」と答えたこととも関係していそうである。また、両親以外の聞こえない人と接点を持つようになった人の場合には、親との会話で使う手話だけでは通じないという認識を持って手話の勉強を始めていた。このように、コミュニケーションの限界を意識して手話を学んだというケースの他、通訳という仕事を念頭に置きながら手話を勉強し始めたという答えもかなりあった。これは、手話を技術や特技として見る見方が社会の中で少しずつ広まってきているという背景も影響しているようである。
質問16 手話で寝言を言ったり、夢の中で登場人物が手話をしたりしていることはありますか?
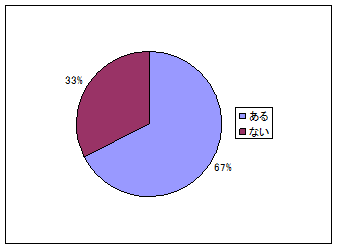
書き込みのあった回答
・ ある(日本語、手話、どちらで話していたのか普段はあまり覚えていない)
・ ある(はい、はっと気がつくと手が動いてたこともありますし、手話している人もでてきたこともあります。)
・ ある(父母や知り合いのろう者)
・ ある(かなりお酒で酔っ払っていても、手話を使って話していたよう。)
・ ない(と思う)
考察
回答者の約3分の2は、手話で寝言を言ったり夢の中で手話が出てきたりすることが「ある」と答え、3分の1は「ない」と答えた。しかし、この結果を質問11~13と合わせてみると、手話の夢を見るかどうかは、その言語に対する自分の思いとあまり関係はなさそうである。生活の中でかなり手話を使っている人や、「自分の言語」は「感情的には手話」と言っている人の場合でも、手話で夢を見ることはないという回答は複数あった。反対に、「自分の言語」は「日本語」と答えた回答者でも、手話で夢を見ることがあるというケースもあった。
この質問は、日系ブラジル人の文化的アイデンティティに関する研究で「夢言語」を尋ねる項目があったのを参考にして作った質問だったが、調査者自身、自分があまり得意とは言えない言語で夢を見たことがあり(単語しか出てこなかったが…)、夢を見たから/見ないからといって、その言語が得意/不得意ということにはならないように思う。夢は無意識の範疇ではあるが、それもまた、多様な言語使用の一端を映し出すに過ぎないのではないだろうか。(ただし、一般の聴者に対しては、「手話で寝言を言う」とか「手話で夢を見る」という話は、コーダのバイリンガル性を納得させる上で強烈な効果があることを付記しておく。)
質問17 子どもの頃、家の中で一番通訳をしたのは誰ですか?
|
|
N=40
|
|
自分
|
24
|
|
姉
|
8
|
|
兄
|
1
|
|
自分・姉
|
1
|
|
自分・弟
|
2
|
|
その他
|
2
|
|
無記入
|
2
|
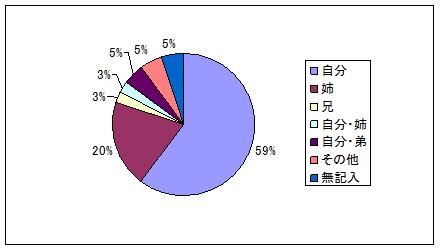
※「自分」の中には「しいて言えば自分」という回答も含めてカウントしました。
「その他」の回答
・ 兄弟姉妹なし
・ 通訳しない
※その次の質問「一番通訳したのは、きょうだいの中で何番目ですか?」は文章が紛らわしかったようで、「年齢が何番目か」と捉えた回答者と「通訳量が何番目か」と捉えた回答者が混在していました。そのため、数値的な集計は行わず、質問17として書き込みのあった回答を紹介することにしました。
書き込みのあった回答
・ 自分・姉 同等くらい
・ 自分・弟 4人とも同じ位(←弟が3人いる回答者)
・ 自分と弟(双子なので平等に扱われたと記憶してます)
・ 姉 2・3・4番目 私が物心ついた時には長女は嫁いでいましたし
・ 自分 4番目と5番目 すぐ上の姉が仕事でいなくなり、次は私と年の順番で必要な時に通訳していたので、誰と断定できませんが、一番長く両親と居た妹と思いますが。
・ しいて言えば自分
考察
全回答者の60%近くが、家族の中で最も通訳したのは「自分」と答えた。今回のアンケート回答者の全体的な傾向として、家の中で中心的な通訳をしていたコーダが多く参加しているということは言えそうである。もちろん、この中には、一人っ子コーダや聞こえないきょうだいのみを持つコーダ(家の中で聞こえるのは自分だけというコーダ)も含まれている。しかし、聞こえるきょうだいがいる場合(回答者の4分の3にあたる30人)でも、きょうだいよりも通訳をした、またはきょうだいと同程度通訳したと感じている人が多かった。そもそも、「コーダの会」や手話関連の活動に関わっているコーダは、子供の頃に家の中で通訳役割を担っていた確率が高いのかもしれない。
回答者のうちの20%は、家の中で一番通訳したのは「姉」と答えていた。また、書き込みのあった回答を見ていくと、必ずしもきょうだいの順序が問題となるわけではなく、きょうだいで同程度に通訳したケースや、上のきょうだいが家にいなくなるにつれて通訳の役割が下のきょうだいに移っていったケースもそれなりにあることがわかる。
質問18 自分は通訳をしましたか?自分の認識に近いものに○をつけて下さい。
|
|
N=40
|
|
かなりした
|
16
|
|
時々した
|
15
|
|
あまりしていない
|
5
|
|
ほとんどしていない
|
3
|
|
無記入
|
1
|
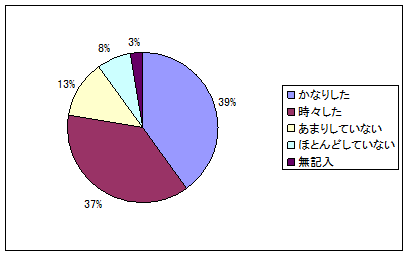
考察
「かなりした」と答えた人が16人、「時々した」と答えた人が15人で、それなりに通訳をしたという意識を持っている人が全体の4分の3を占める結果となった。「ほとんどしていない」と答えた3人の中には、片親が聞こえる人と、12歳まで親と別居していた人が含まれている。「あまりしていない」と答えた5人には、全員姉がいる。これは、前の質問とも関係してくる問題であろう。
質問19 どんな通訳をしましたか?印象に強く残っているものを書いて下さい
<日常生活>
・ 日常生活全般。
・ 一緒に出掛けてる時に接触する人との通訳
・ ふつうの人に対して
・ 比較的、母は口話が上手だったので、母が話して伝わってないなと感じる時に。
・ 父は中途なので、発音がはっきりしている為、ほとんどなかったが(意図が大幅にズレている時くらい)、母は先天性なので、母が話した言葉を、買い物に行った時、店員さんなどに伝えたこと。
・ 店員さんとのやりとりなどもやりました。
・ デパートやスーパーで
・ 買い物の際の通訳等
・ セールスの通訳
・ 来客(集金など含む)
・ 簡単な通訳。新聞の集金や電話など
・ 宅急便への連絡
・ 出前
・ ファミレスでの注文
・ 電気屋など
・ テレビドラマの通訳
・ テレビ
・ テレビ
・ テレビ
・ TVを一緒に見ている時
・ テレビ・コマーシャルの通訳
・ 放送とか
・ 簡単な電話通訳
・ 電話通訳。例えばタクシーを呼ぶ、親戚と連絡をとる。
・ 電話の取り次ぎ
・ 電話通訳(手話通訳を依頼するため)
・ 電話通訳
・ Tel通訳
・ 電話
・ 電話
・ 田舎の親戚などに電話通訳
・ 親戚が集まる場(帰省した時)
・ 親戚で集まった時
・ 親類達との会話
・ 親戚間の通訳等
・ 祖父母、いとことの連絡
・ 家族以外の健聴者に対して、すべて通訳をしていた。特に母方の兄妹(伯父、叔母)や祖母の間に入り、窓口をしていた。
・ 近所の人との会話
・ 近所の人からの連絡
・ 近所付き合い
・ 近所の人(回覧板、町内会費回収など)
・ 兄弟間での他愛もない会話の通訳等
・ 公共交通機関
<学校関係>
・ 学校
・ 学校(先生)
・ 幼稚園や学校の先生
・ 特に家庭訪問や父母会は子供なのに間に立つのが辛かった記憶があります
・ 家庭訪問
・ 家庭訪問など
・ 学校の3者面談
・ 学校の三者面談
・ 学校の3者面談等。
・ 学生の頃の三者面談
・ 学校の進路相談や個別面談、家庭訪問
・ 中学生のとき。担任の先生と私と母とで進路の話をしたとき。
・ 学校の行事(授業参観や面談)
・ 代筆代読→学校関係の書類
<一般に大人がすると想定されていること>
・ 印象に残っているのはホテルを電話で予約した時の相手の応対の様子。←子供がホテルを予約するのはやはり変ですよね
・ 保険会社の人との通訳。市の職員の話を壇上で通訳した
・ 病院や区役所、銀行
・ 病院・警察・区役所
・ 病院での通訳、役所での通訳
・ 行政、医療機関
・ 公的機関
・ 店員との交渉
・ 親戚の葬式
<親の仕事関係>
・ 父と母は洋服の仕立て職人なので仕事の依頼に来られる方の通訳、さらにその際の電話通訳
・ 父が仕立て屋をしていましたので来客が多かった為
・ 自営業でしたから、御客様に対しての話
・ 父が会社を休むとき
・ 電話・・・両親の仕事関係
<その他>
・ ろう協やサークル関係の人、通訳者との連絡
・ ろうあ協会の活動関係
・ 教会での通訳
<特にない>
・ 特にありません(←親の一方が聞こえるために「ほとんど通訳をしていない」と答えたケース)
・ 毎日が通訳しているので余り印象がない
・ ない
考察
多かったのは、やはり日常生活に関することだった。具体的には、買い物をする際の通訳、テレビや電話の通訳、親戚や近所の人との通訳を挙げた人が多かった。また、学校関係の通訳にふれた人もかなりいた。しかし、学校関係の通訳は、日常的にというよりも、家庭訪問、面談(進路相談を含む)、授業参観といった特定の行事と結びついていることが多いようだった。こうした日常生活や学校に関係することは、当事者なのに通訳をしなくてはいけないという「面倒くささ」と絡んでくる面もあるが、家族の中での「子ども」という立場と馴染んだ事柄であるとも言える。一方、病院や役所、金融関係の通訳や、店員との交渉、お葬式の通訳、親の仕事に関する通訳など、「子ども」が担うには重過ぎる通訳を経験していた人も少なくなかった。こうした場での通訳は、交渉や接客、取次ぎなど、単に通訳するだけでなく、判断や話術が必要であり、しかも失敗した時に重大な結果をもたらしてしまうというプレッシャーがかかってくる。手話通訳の制度がまだ充分に整っていなかった時代には、コーダの他にそれができる人もいなくて、子どもでありながらこのような状況に対処しなくてはいけなかったコーダがずいぶんいたようである。手話通訳派遣制度の充実と、コーダに対する認識が広まりつつある今日では、聞こえない親の側も、子どもの年齢に合った責任の課し方を配慮できるようになってきているのではないかと思う。
質問20 通訳の体験は、自分にとってどういうものでしたか?
<子供には難しい>
・ 仕事上の会話や大人の会話を子供のボキャブラリーで通訳するのはとても頭が疲れました。
・ とっても緊張して、子供なのに大人にならなくちゃいけなくなる時間だと思ってました。やらなくてはいけないと思っていたけど、好きではなかったです。
・ とても嫌だった。子供にはかなり無理。
・ 複雑な内容を頭の中で簡潔にまとめ直してわかりやすく伝えなければならないので言葉に対する認識が子供にしては深くなったかな?と思います
<嫌だった、面倒だった>
・ 楽しくはない。嫌だった。
・ 嫌だった。
・ 嫌だった記憶しかないかも・・・?面倒というか?
・ 面倒くさい、仕方ない、義務感で
・ めんどう。できればやりたくないこと。
・ あまりしたくないもの
・ 今は、通訳することはなんとも思わないが、小さい時は、正直面倒くさくてたまらなかった。
・ 深く意識した事は無いが、正直小さい頃は面倒だと思う事が多々有った
・ 幼いころは面倒くさい、やりたくないこと
・ 小学校の頃がとても多く、とても嫌で何でしなあかんねんやろ?と、いつも思っていた
・ 勉強の場でもあったが、嫌な思い出もある。
<プレッシャーだった>
・ もともと手話がうまくなかったので、相手が分からないという顔になるとプレッシャーだった。意味が分かっても通訳できないことが多かった。
・ 満足にできなかったので苦痛だった。
<人の目が気になった>
・ その頃は正直恥かしかったです。
・ わからなくて、だん上を下りたら、「何でもいいから手を操(←すみません、字が読めませんでした)れ!」とだん上に戻されて、はずかしかった
・ 『通訳をした』という感じはないが、高校生ぐらいまでは、聴覚障害者に対する世間の目が冷たく、この子は何をしているの?と嫌な顔をされた事が多かった。人の目を気にするという性格はそこからきているのかもと思うことがしばしば。
<今振り返ると、良い体験>
・ 今、手話通訳という仕事をしているので、早くから色々と経験出来てよかったと思います
・ あの頃は苦しかった。今は体験できて良かったと思う
・ 今、思えば良い体験だと思うが、当時は嫌で嫌で仕方なく通訳してた
・ 良い体験
・ 貴重
<当たり前のこと>
・ ごく自然な、当たり前のこと(葬式の通訳等で大勢の前に立たされたときはさすがに、恥ずかしい/嫌だ、という気がしたが、それ以外の場面では、日常的で特に否定的な感情(e.g.やりたくない)等は持たなかった。)
・ 学校での通訳については、小学校の高学年からはそういった場での通訳が当たり前になっていたので特に何も感じていなかった。ただ、ドラマの内容や兄弟間での他愛もない会話の通訳では、面倒くささを感じることがあった。
・ 当たり前のもの
・ あたり前の事と自然に受けとめていた
・ 自分しか伝える人がいない(妹もいるが)ので、当然のことと感じていた。
・ 当たり前のことだったが、時々苦痛におもえた
・ やるのが「あたり前」だったけど、じゃまくさかったり、自分のペースが崩されるという点がイヤだった。
<特になし>
・ 特に思うところはありません
・ 特になし
・ 特に何も。
・ 親に対しての通訳は自然の成り行きなので、特別に感じる事はありませんでした。ろう者の役に立てると言う意味では、もっとやりたいと思います。
・ 特別な経験というわけではないので、自然のことだったと思う。
<家族との関係を深めるもの>
・ 姉弟の元
・ 親のお手伝い。
<気分がよかった>
・ 自分が思ってないことでほめられるのでなんだか自分は特別なのかと一時的に気分がいい。
<その他>
・ 通訳してはいけないと思うことは自然に通訳せず、知らん顔した。いつも、親がばかにされないようにという意識があった。
考察
通訳は「当たり前のこと」だったけど、自分の思いとしては「面倒」だし「嫌だった」という答えが多かった。「苦痛」や「苦しさ」は、やはり、大人の会話を子どもの語彙で通訳しなくてはいけない難しさとか、がんばって手話で表しても相手に通じない苦痛とか、人の注目を浴びる恥ずかしさなどと、結びついているようである。しかし、回答の中には、「特に何も思うことはない」という答えも一定数あったことにも注意しておきたい。
質問21 親に対する通訳と、一般のろう者に対する通訳は、違うと思いますか?
(「違うと思う」と答えた人に対して)どういう点で違いますか?
<親に対しては自分の主観が入る>
・ 身内だから自分の意見や主観が入る
・ (親の場合には)自分の意見を入れてしまう。
・ (親の場合には)私情や主観が入ってしまうと思う
・ 親に対してはつい主観や自分の意見を混ぜがちだったが、他のろう者に対しては何も加えずにそのまま通訳する点
・ 親の時はある程度自分の判断で決定しているがほかの人の時は私情などは入れないようにしている。
・ 身内意識が強すぎて「保護者感覚」かも?それと、親に対してのほうが厳しい。冷静でいられない。
・ 私情を挟んでしまう点。中立で通訳ができない
・ 公共性、中立性
・ やはり親なのでこちらの考え等がいいやすかった
・ 他人だと感情を抑えなくてはと意識するから
・ 親と話す時は、つたない手話だけどかなりがんばって通訳しているのにどうしてわかってくれないの?とよく思ってしまいます。一般のろう者の方にはそのように思うことはありません。
・ 親に対する通訳は面倒だと思ってしまうけど、一般のろう者に対してはそのようなことは思わない。
<親だと慣れているので通じやすい、気が楽>
・ 親ならなんとなく何が分からないかを顔に出してくれやすい。何が分からないのかなんとなく分かる。たとえが出しやすい。
・ 親が理解しやすい言い回しにできる。←私自身が楽。
・ 個人の癖や考え方がわからないと、通訳できないし知っている日本語の種類がバラバラ。親はもうわかっているから通訳できるけど、他のかたは難しい。
・ 家で使っているホームサインは通じないから。又、両親だと色々なバックグラウンドを把握しているので、手話通訳はやりやすいが、一般の聾者だとバックグラウンドとかを知らないので、手探りの状態で通訳する必要がある。その他、責任の重さが違う。両親だとごめんとすまされることも、一般の方だとごめんだけではすまされないと思う。
・ 身内の場合は修正ができるから
・ 他のろう者に対しては、音声でいうところのいわゆる「タメ口」では話せない。丁寧な接し方にしなければならない
・ 慣れていない時は相手の表出を確認しなければならない
・ 親の場合:いつものスタイルで会話していれば良いという安心感が有る。
一般のろう者の場合:ごく一般的な手話を使わなければ・・・というプレッシャーが掛かる。
・ 親の伝えたいことは親が手話を使っていなくても分かるし、親も、私が伝えたいことをよく分かってくれた(カンがいいとも…特に母)が、こうしたことは家族だからだと、他のろう者と接していて気が付いたので。
・ しらない人だから
・ 同じようで、違う。親の場合、きちんと理解してもらえたかどうかわかりやすいが、一般のろう者は理解したふりをして、話をそらされてしまう事がありそれ以上は追求できないことがある。
<表現の仕方の違い>
・ 感覚、間
・ はっきり違うとはいえないが、家の中では昔の手話単語を使っていることもあるので、両親に対する通訳よりも、手話単語に気を遣ったり、指文字を多用する点で違いがあるかも知れない
・ あやふやな手話は使わない(誤解などを招かないため)
・ 手話のやり方
・ 手話の種類と速さ
<1対1と大勢の通訳では違う>
・ 1対1の通訳は、どのぐらい語彙を共有しているかという問題を除けば基本的に同じだと思うが、1対多の場合は、手話の見せ方(e.g.大きく見せる)等で、大きく異なると感じる。
<内容が違う>
・ その内容によって
<その他>
・ 特に母親がアメリカ人だったので、通常の手話単語もかなり噛み砕いて通訳をしなければならなかった点
・ 私には一般のろう者の方に通訳する機会はほとんどありません。ただ花屋で働いているので、ろう者の方が来られた時は手話通訳をします。手話ができる店員がいるということでかなり好意的に見てもらっているので、私のつたない手話でもなんとか通じているという状況です。
・ むぅ~・・・。
・ 一般のろう者には仕事として通訳をするのでそこが異なる。親に対しては仕事の感情はない。
考察
親に対する通訳と一般のろう者に対する通訳は「違う」という答えが、全回答者の4分の3以上を占めた。違う点として多く挙がったのは、「親に対しては自分の意見や感情が入ってしまいがちだが、一般のろう者に対しては中立的な立場で通訳する」という点、「親だと慣れているので通じやすいし(←背景知識や手話の方法も含めて)、何がわからないかを理解しやすかったり修正できたりという安心感がある」という点だった。やはり、親に対する通訳では、一緒に過ごしている時間が長いという親子関係ならではの心情的・感覚的な近さがあると言える。しかし、単に親子関係を背景とする通訳という意味では、聞こえる親が手話を覚えて聞こえない子どもに通訳するというケースもありうる。でも、この場合には、聞こえる側が「親(子どもを育てる役)」という立場と「通訳をする側(情報を伝える役)」という立場を兼ね、「保護」傾向が強くなってもあまり葛藤を起こさないのに対し、コーダの通訳の場合には、「子ども」という立場での親への甘え(親にこうあってほしいという欲求や実際にそうでないことへの反発、自分が決定したり意見を言ったり失敗したりしても親は許してくれるだろうという予測など)と「通訳者」としての倫理性(中立性・公共性)が葛藤を起こす面があるとも言えそうである。
質問22 誰かから「手話通訳者になったら?」と言われたことはありますか?
※ 「非該当」は、この質問に対する答えでなく、別の質問への答えを書いてしまったケース
(「ある」と答えた人に対して)誰から言われましたか?(○はいくつでもOK)
|
親
|
11
|
|
親の友達のろう者
|
16
|
|
ろうの友人
|
11
|
|
コーダの友人
|
5
|
|
手話通訳者
|
13
|
|
手話学習者
|
14
|
|
一般の聴者
|
15
|
|
その他(親戚)
|
3
|
|
その他(親戚以外)
|
2
|
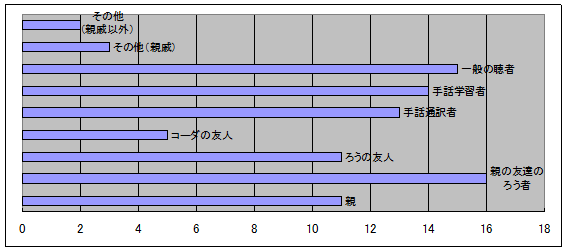
「その他」(親戚以外)の回答
・ 親の友人の手話学習者や通訳者
・ 学校の友達
書き込みのあった回答
・ ない(言われる前に通訳活動を始めていたのかも)
・ その他(親戚から)(余談ですが、中学・高校の教員免許をもっていることから、手話通訳者よりも「ろう学校教員になったら?」と言われることの方が圧倒的に多い)
・ 非該当(両親が幸せだと話しているのを見て外の人にも分けてあげたいと思って(←質問23への答えをここに書いたと判断し、「非該当」としてカウントしました。)
考察
全体の4分の3に近い人が、「通訳者になったら?」と言われた経験が「ある」と答えた。
どのような人から言われたかという点では、「親の友達のろう者」、「一般の聴者」、「手話学習者」、「手話通訳者」、「親」、「ろうの友人」といった選択肢のほとんどで、10以上のかなり高い値が見られた。コーダが手話通訳になることへの期待は、聞こえない人や手話に関わる聴者だけでなく、手話をそこまで知らない一般の人からも寄せられていることがわかる。ろう者や手話に深く関わっている人の中には、「コーダなら普通の人よりもろう的手話ができるのでは?」「コーダならろう者の気持ちや聞こえないことについての理解が深いのでは?」という期待を込めてそのように言う人も多そうだが、もっと一般的な聞こえる人の場合には、「コーダなら当然手話ができる」という前提でこうした発言をする人が大半なのではないかと思われる。
質問23 手話通訳者になることを考えたことはありますか?
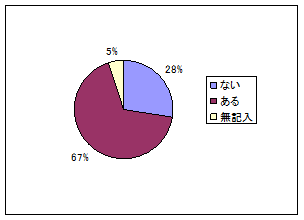
「ない」と答えた人の理由
<手話通訳者になろうと考える前に実際に通訳者としての仕事が始まった>
・ 今、実際通訳をしていますが、きちんと考える前にバタバタと仕事が入っていったような…
<目指しているものが違う>
・ やりたい事は手話通訳者ではないという事です
・ 手話通訳者になれる位の手話技術を身に付けたいと考えることはある。また手話通訳者の方でろう者のような手話をされている方がいるとうらやましくはなるが、手話通訳者になろうと考えたことはない。その理由として、手話が得意ではないこと、また目指しているものが明確に違うことが関係していると思う。
・ 自分が手話通訳者として見られることに抵抗がある。
<手話に対する苦手意識、消極的な思い>
・ 手話をすることがそんなに好きではないから
・ 簡単な手話しかわかんないから
・ 手話は難しいから
・ 手話しないから
<その他>
・ 特にない!?
・ いやだから
「ある」と答えた人の理由
<使命感、聾者の求めるような手話通訳者が少ないから、役に立てればという思い>
・ 幼い頃から通訳者を見てきたし、通訳してきたので、自分の役目として漠然と通訳になることを求められてるのではないかと思った。
・ コーダとしての使命と思う
・ 聾者が分かるような通訳が少ないから
・ 昔、通訳が嫌で逃げていたら父が地元の通訳者に通訳を依頼した結果、全く分からなかったと言っていた。父が亡くなった後、そういう人が多いことを知り、なりたいと思った。
・ ろう者の気持ちが把握できるから
・ 自分の親を見ていて手話通訳者の必要性を感じて、自分も助ける立場になりたいと思った。小学生の頃のことですが…
・ 手話がわからない人への情報保障として
・ 親によって身についた手話で社会貢献したい
・ 身に付いた言語をどこかで役立てればという思いから
・ 両親と、もっとしっかり話をするために手話は必要だと気が付き、ほかのろう者の方々と交流させて頂く中で、自分には、ろう者と聴者の仲立ち(繋ぐ役割を担う者)が出来るのではないかと感じた為。
<自分の能力や経験を生かしたい、特技や技術にしたい、他の人に比べて有利>
・ あまり努力せずに自分の能力を活かせるかもと思った(全くの間違いだったが)
・ 自分のバックボーンを生かせるし、それが使命と考えた時期もありました(笑)。なにより、なんというか自分の世界?故郷?という心地が手話世界にある事ですかね?
・ 小学生の頃:親が喜ぶと思ったから
大学生の頃:せっかくのスキルなので役立てたいと思ったから
・ 自分の特技として生かしてみようと思ったのと、興味があったから
・ 30歳を迎えたにも拘らず、自分には何の技術も無いと焦り始めた為
・ 母が手話話者であり、一般の人よりは手話への馴染みがあると考えたため
・ 自分に出来ることかもしれないから
・ 自分に出来るものを生かしたいと思った
・ せっかくこのような家庭環境に生まれたから
・ 聞こえない親に育てられたのでそれが生かされる職業かなと思い。
<自分の性格に合う>
・ 自分に向いていそうだったから。通訳の仕事に興味を持ったから
<両親のことをもっと知ることができるのではと思った>
・ 今、実際に手話通訳をしているのですが、やはり、手話通訳者になることによって、両親の事をもっと知られるのではないかと思ったから。その他の理由として、聴覚障害者の事を良く知っている者例えば、コーダや兄弟に聴覚障害者がいる人のような人が、聾者の求める手話通訳者になれるのではないかと思ったから。
<いろいろなろう者と会話がしたい>
・ もっと色々なろう者と会話がしたい。
<手話が魅力のあるものだと気づいた>
・ 自分が感じていた手話の世界が違っていた為、やりたいと思い始めた。
<その他>
・ ただまわりに流されていただけ
・ 通訳養成の学校に通ったから
・ 現に横浜市で行っています
考察
手話通訳者になるという選択肢については、回答者の67%にあたる27人が考えたことが「ある」と答えていた。質問22の結果からも、コーダに対しては、通訳者になるという内外のプレッシャーがあることがわかる。その背景としては、コーダ自身、手話通訳者は必要であるという認識を持っており、しかもろう者の言いたいことを充分に伝えられる通訳者が少ないという現状を知っていることが影響していそうである。このようなことから、コーダに対するまわりからの期待やそれに応えたいという思いが主流になると考えられる。
手話通訳者になることを考えたことがないという人は、手話通訳者以外になりたいものが明確にあったり、手話は苦手だしそれほど好きではないというように手話との距離を言語化して認識している人であったりするようだ。また、若い10代の回答者の割合も高かった。若いうちは、親の通訳をする/しないの延長上に、職業としての手話通訳者になるという選択肢が置かれるのか、「いやだから」「手話しないから」という理由が挙げられている。
実際、自分の持っている手話の力や聞こえない親と暮らした経験をスキルとして考えるようになるのは、少し年齢がいってからと言えそうである。他の一般的な聴者と比較しながら自分を位置づけたり、その能力について考えたりしていく中で、やはり自分は手話に慣れているとか、聞こえない人の気持ちが分かるということを、客観的に捉えるようになっていく。そして、自分の経験や環境を「生かす」という考え方も強く働かせながら、それは役に立つものであり、他の人より自分に利点がある、と認識するに至るようだ。
質問24 自分の手話通訳者としての活動の有無について、合うものに○をつけて下さい。(当てはまるものが二つ以上ある場合には、○は二つ以上でもOK)
|
自分は手話通訳者ではない
|
21
|
|
手話通訳者になるために勉強中
|
6
|
|
登録手話通訳として活動している
|
6
|
|
登録はないが、実質的に手話通訳として活動している
|
5
|
|
登録は持っているが、実質的に手話通訳として活動していない
|
3
|
|
手話通訳士の資格を持って、活動している
|
4
|
|
手話通訳士の資格を持っているが、実質的に手話通訳として活動していない
|
1
|
|
無記入
|
2
|
|
その他
|
1
|
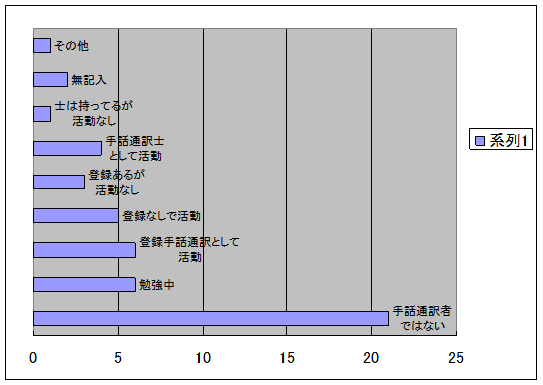
「その他」の回答
・ 私は40年近く通訳をしていますが、手話通訳士の資格をとる必要性を感じない(←どの選択肢にも○はつけていない回答者)
考察
回答者の半数以上の人は、「自分は手話通訳者ではない」と答えている。「登録手話通訳として活動している」と答えた6人のうち、3人は「手話通訳士の資格を持って活動している」にも○をつけ、別の2人は「市の専任通訳である」という旨を書いていた。「登録は持っているが、実質的に手話通訳として活動していない」と答えた人が3人、「登録はないが、実質的に手話通訳として活動している」と答えた人が5人いることも考え合わせると、有償ボランティアである「登録手話通訳」という身分の不安定さが示唆される。手話通訳を職業とする人にとっては「登録手話通訳」は中途半端であり、手話通訳士か行政の専任通訳という身分が必要とされる。一方で、他に仕事を持ったり他の活動に従事したりしている人は、登録は持っても時間的に余裕がなく、実質的に活動はできていない。また、家族や友人、知人のために通訳をするのなら、わざわざ「登録手話通訳」という身分を持たなくても、信頼関係に基づいて通訳を依頼される。そのような意味で、コーダであることと「登録手話通訳」という身分は、折り合いが悪いのかもしれない。
質問25 手話通訳以外で、聞こえない人に関わる職業につくことを考えたことはありますか?
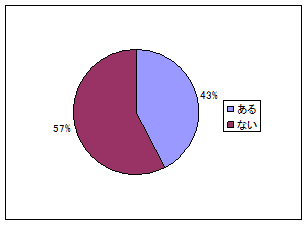
(「ある」と答えた人に対して)具体的には?
<ろう学校の先生>
・ 子どもの頃はろう学校の教師
・ 聾学校の教員
・ ろう学校教員
・ ろう学校の教師
・ ろう学校教師
・ 聾学校幼稚部
<聞こえない人が利用する施設の職員>
・ ろう児施設職員
・ 「いこいの村」で高齢のろう者と関わりたかった(祖母が亡くなったことも影響。また、聞こえる人は死ぬ直前意識がなくなってもまわりの声は聞こえると聞いたことがある。では「ろう者はどうなるの?」と考えたら涙が出てきた。寝たきりになったろう者のお見舞いに行ったのがきっかけ)。現在は、京都市の手話通訳専従職員として働いている。
<聞こえない人が多い職場や聞こえない人が多く利用するサービスでの仕事>
・ 過去はハンズサインセンター、今は会社の中で聞こえない人が働く環境をよくするような仕事。
・ 聞こえない人が多く働く職場での仲介的役割
・ 今は、聴覚障害者用の機器を扱っている会社で働いている。
・ 役所などの相談業務(スカウトされた)
<手話や聞こえないことに関する研究>
・ 手話の言語学的な研究
・ ろうの遺伝子の研究とか
<自分の就いた仕事と絡める形で聞こえない人と関わる>
・ 正確な職業としてではないのですが、ろう学校でお絵描きの課外授業を行っています。できるかぎり今後も続けていきたいと思っています。
・ 就職先で手話が活かせる場があれば程度
・ 現にCS障害者放送統一機構とビジネスをタイアップしております。
<手話を使うパフォーマンスなど>
・ 手話劇とか、パフォーマンス的な分野で多くの人を楽しませる事が出来たらいいなと思った。
考察
全回答者の半数以上の人は、手話通訳以外で聞こえない人に関わる職業につくことを考えたことは「ない」と答えている。「ある」と答えた17人のうち、具体例として最も多かったのは、「ろう学校の教師」だった。「ろう学校の教師」は、「手話通訳」と並んで、子どもの立場でもイメージしやすい職業なのかもしれない。聞こえない人に関わるその他の職業は、ある程度の年齢になってからでないと見えてきにくいようである。実際に働き始めたりスカウトされたりという経験を通して、「あぁ、こういう関わり方もある」ということが発見され、具体的にイメージされたり実践されたりしていくという面があるようだ。
質問26 自分自身、うちは他とは違うという意識を持っていましたか?
|
|
N=40
|
|
持っていない(「あまり持っていない」という回答も含む)
|
11
|
|
「うちだけが」とは思わないが、違いの意識は持っていた
|
2
|
|
持っていた
|
27
|
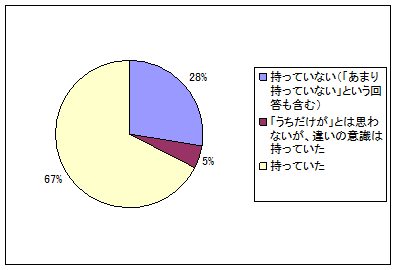
「「うちだけが」とは思わないが、違いの意識は持っていた」人の記述
・ 漠然と、家庭はそれぞれ違う、と思っていました。「うちだけが」ではなく「それぞれ違うもの」と。
・ 持っていましたが、それは「うちだけが違う」というものではなく「うちはここが違う」というものです。
(「持っていた」と答えた人に対して)いつ頃、どういう体験を通して持つようになりましたか?
<家と外でコミュニケーションの取り方が違う>
・ 親に連れられていくところ全部が家とは違うコミュニケーションのとり方だから。幼稚園の先生が自分の言っていることを理解してくれなかった。
・ 小学校の頃、家に帰ったら「ただいま」というかえって来る言葉がないと気づいたとき。
<聞こえる人の反応>
手話や親の声、音への反応(街の中での人々の反応)
・ みんなが親と会話してる時じろじろ見たとき。親が行動する音、何か落としたり開けたり、親の声といった音に聞こえる人が反応した時。
・ 外出時、父の手話を物珍しそうに見られた時。
・ 幼い頃、電車に乗ってて親と話をしただけでじろじろ見られるということが、他の人と違うんだなと思った。
・ (「あまり持っていない」と回答した人の書き込みで)ただ、町なかを父母と歩いていると、時折、視線を感じるので、うちは珍しいのだろうな、という意識はある。
フラッシュベルなどへの反応(遊びに来た友達の反応)
・ 小学生の時友人が遊びに来て、フラッシュベルを見て不思議がられた時、親との会話をみて驚いてた所
・ 小学校4年の時。友達が家に遊びに来た時に、「お前んち、ピンポンって押したら光るなんてめずらしいな」と言われてから。
授業参観の体験(学校での体験)
・ 小学校低学年の頃、授業参観で母親が手話通訳者と一緒に来て、クラスの子たちが手話ばかりを見て授業にならず、「恥ずかしい」と思った体験から。
・ 小学校の授業参観
・ 小学校の頃、授業参観など
先生や友達の発言・態度(学校での体験)
・ 小学生くらいから、友達に言われたり先生に言われたりしたから、違うんだ~と。姉の友達は親に付き合わないように言われていたらしい。
・ 小学校2年生の時いじめられてから
<聞こえる人のやり方との比較>
友達の家との比較
・ 物心つくのと同じ感じ、外の親子を見て
・ 小学生の時。友達の家に遊びに行って、友達のお母さんがしゃべっているのを見た時に。うちは共働きだったので友達が遊びに来ても母がもてなしてくれることはなかったのでなおさらそう感じたんだと思いますが。
・ 小学生の頃、友達の家に遊びに行った時、友達とお母さんが普通に音声言語で話しているのを見た時。他人の親子関係の話を聞いた時など。
・ 友達の親をみて自分は違うんだと感じた。
・ 幼稚園のとき、家では手話を使うことや生活習慣が友達の家と違うことを知った。
・ 小・中校。まわりの親は全て健聴者。
親の様子から
・ 保育園時代(年令はよく覚えていない)に、周りの大人とは(先生や祖父母)声で話せるのに、父母の声は聞き取りにくく、変だと感じていたから。保育園の日記に母ではなく祖母が書いていたから。
・ 小さい頃から。参観日に母が来ていたけど、他の親とは話せないのを見て。
・ 小学校の低学年の時から(もしかしたらもっと前から)。外出している時、母は他の人に対して聞こえない仕草をしていた。外出すると母はいっさいしゃべらない。
・ 小学1年生当時、家に電話が無かったこと。学校で配られる緊急連絡網に自宅の電話番号が載っていなかったこと。学校の保護者会には母親の参加が一般的だが、全て父親が参加していた(←この回答者は父が聴者であるため)。例えば、遠足等で弁当を持参しなければならない時、友達の弁当は凝った盛り付けがしてあるのに対して、私の弁当はこども受けするような中身ではなかったこと。途中からは弁当箱を開けるのが恥ずかしかった。
・ 家での様子。食事中に話をしないで食べる。風呂は毎日沸かさない。大声で歌ってうるさく騒いでも怒られない。
・ (耳が聞こえないから)理解がおそい
<親と子の立場の逆転>
・ 4歳か5歳頃、親の代わりに電話をするようになって
・ 親が聞くような質問を、子供の自分がしなければならないような時。
・ 筆談が学校の先生と通じなかった時、自分のほうが親より知っていた時。
考察
「うちはほかと違うという意識を持っていなかった」人が11人、「「うちだけが」とは思わないが、違いの意識は持っていた」人が2人、「うちはほかと違う」と思っていた人が27人という結果になった。
「うちだけが」と思わないが、違いの意識は持っていた」とわざわざ記述した2人には、両方ともろう者のおじ・おばがいる。もちろん、親戚にろう者がいる人は他にもたくさんいるが、こうした記述は、自分の家以外に身近にろう者の家庭を見ていたこととも関係があるのかもしれない。
違いの意識を持たせるものとしては、聞こえる人の集団である保育園、幼稚園、学校といった場やそこの人間関係が大きな影響を与えていることがわかる。学校では、主に授業参観が、自分の親が他と違うことを意識させる機会となっている。また、遊びに来た同年代の友達の反応も大きい。親の手話や声、聞こえない人が使っている道具などは、その中で生活している自分にとっては当たり前だが、外の人にとってはそうではないと、街の聞こえる人や友達の反応を見て知るようである。より直接的には、友達とその親の関係を見て、自分の家のあり方が他と違うと感じる面もある。
また、親の様子を聞こえる人のふるまいと比べることで、違いの意識が出てくることもある。ただ、中にはおそらく聞こえる人の家庭でも見られるのではないかと思われる例(お弁当やお風呂など)も挙げられている。そのことが「聞こえないこと」と結びついた違いとして理解されるのは、興味深い。
「普通は親がすること」を子供の自分がしたり知っていたりすることも、違いの意識を強くもたらすようである。
質問27 親が聞こえないことでいじめられたことはありますか?
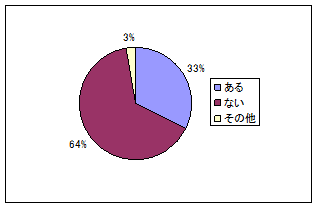
<「ある」と答えた人の書き込み>
・ からかわれていたが当時は気づかなかった
・ 大人にいじめられた
<「ない」と答えた人の書き込み>
・ 友達と口ゲンカになった時、つい口走られたことはある
・ いじめられた経験はあるが、親が聞こえないという理由ではない。
<「ある」にも「ない」にも○をつけなかった人の書き込み(=その他)>
・ 今はイジメという印象の残り方ではなく、悔しさのほうが大きい。最近では、病院がコミュがとれないという理由で術後のICUに「受け入れられない」と言われたのが最も悔しかった(※親が手術を受けた時の話)。
考察
全回答者の3分の1ぐらいの人は、親が聞こえないことでいじめれた経験があると答えている。3人に1人がいじめられた経験があるというのは、一般に比べれば確かに高い確率かもしれない。しかし、「親が聞こえないことで子どもがいじめられるのではないか」と心配する親が多いことを考えると、コーダ回答者の3分の2はそうした経験を持っていないという点にも注意を向けるべきだと思われる。
質問28 まわりの聞こえる大人から、「大変ね」「かわいそう」「あなたががんばるのよ」などと言われたことはありますか?
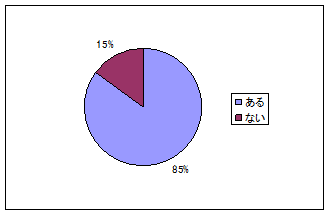
(「ある」と答えた人に対して)どういう人から言われましたか?
|
親戚
|
21
|
|
近所の人
|
13
|
|
学校の先生
|
8
|
|
自分の友人
|
2
|
|
親の友人
|
4
|
|
手話に関わっている聴者
|
4
|
|
ろう者
|
2
|
|
街の人
|
9
|
|
その他
|
8
|
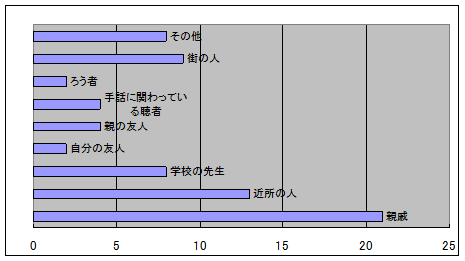
<親戚>
・ 祖父
・ 祖父母
・ 祖父、祖母
・ 親類
・ 親戚(←こう書いた人は14人)
・ 親せき
・ 親せきの人から
・ 叔父・叔母
<近所の人>
・ 近所の人(←こう書いた人は7人)
・ 近所(←こう書いた人は2人)
・ 近所の方
・ 近所の大人
・ 近所のお節介なオバ様達。
・ 隣人
<学校の先生>
・ 先生(←こう書いた人は3人)
・ 学校の先生(←こう書いた人は3人)
・ 担任の先生
・ 学校の担任
<自分の友人>
・ 友人
・ 学校の友達
<親の友人>
・ 親の友人
・ 父や母の健聴者の友人
・ 母の職場の人
・ 母の周りの聴者
<手話に関わっている聴者>
・ 手話に関する活動を行っている人
・ 地域の手話学習者
・ 手話学習者
・ サークルの人
<ろう者>
・ ろう者
・ 聾者
<街の人>
・ 買い物に行った先での店員さん
・ お店の人
・ 大井町の八百屋のオヤジ
・ どっかの相談機関の人
・ 奨学会の面接官
・ 友人の母
・ 友達の親
・ 友達の母親
・ 学校の授業参観で母親に作文を読むような場面があり、手話を使ったことから、クラスメイトの母親などからそのように声を掛けてもらったことがある。
<その他>
・ ありとあらゆる人。
・ 大概の人から
・ 父親の親戚以外のすべての大人から言われた。
・ 経験ない人から。特に年寄り
・ 聴者
・ 親がろう者と知った聴者の方
・ 年配の健聴者
・ 長男と言う立場でいろいろと言われた事がある
考察
そのようなことを言う人としては、「親戚」が最も多く、次いで、「近所の人」、「学校の先生」となった。質問19と合わせると、「親戚」「近所の人」「学校の先生」というのは、コーダが親との通訳をする相手であることも浮かび上がってくる。その意味で、これらは、コーダと親との関係やその家庭を近くから見ている人の発言と言える。
しかし、その一方で、あまり関わりが深いとも言えない人々(「街の人」など)からもかなりこうした言葉が出ていることにも注目する必要があるだろう。それは、「障害を持つ親を手伝っている子供」に対し、それほど深い関係でなくても、気軽にこうした言葉を口にする社会風潮があることを示唆している。
それに対してどういう気持ちがしましたか?
<そうなんだーと思った>
・ そうなんだーと思った
・ 漠然と「そうなんだー」と他人事のようだったのかも。
・ そう見えるんだ~。うちの親は普通だから大丈夫だけど。
・ へぇ~、そうなんやぁ。きたきたきた。など
・ 「なぜ頑張らなければならないのか」というような反抗心や「私が頑張らなければいけない」というようなプレッシャーは感じなかったような気がする。強いて言えば、「自分の存在は周りからみるとそうなんだ」という気持ちの方があった
<不思議に思った、違和感を覚えた>
・ 不思議な気がした。「ズレてるな」とよく違和感を覚えた。自分にとっては、親がろうである環境は「普通」のことで、特に大変だとかみじめだとか思っていなかったからだと思う。時に、そう同情する人に対して「だましている」かのように思えて、逆に申し訳なく思う事さえあった。
・ 何が大変?何が可哀相?何を頑張るの?と不思議だった
・ 頑張らないといけないのかな?頑張るというより、それがうちでは当たり前なんだけどな。苦労してるねって言われるけど、苦労したと思ったことはない、不便だって思うことはあっても。
・ 自分にとって聞こえない両親はごくごく当たり前のことだったので、なにが大変なのか?なにをがんばるのか?わからなかった。
・ 周りが思うほど、あまり大変ではない。
・ 「別に大変じゃないよ」という気持ちと、「そうなの、私ってかわいそうなの」という気持ち。
・ 違う・・・言ってもわからんだろうな。自分の基準でしか見ない。これ以上はなすともっと勘違いされるから話すのやめよう
<大きなお世話だと思った、嫌だった、腹が立った、悲しかった>
・ 余計なお世話!!!
・ 大きなお世話だと思った
・ 余計なお世話。両親がろうということに大変さはあまり感じていなかったけどそういう風にいわれることに嫌悪感を抱いていた。
・ うるさいなぁ、とか、かなり不快な気持ちでいっぱいでした。
・ いやだった
・ 漠然と「そういうこと言う人はあまり好きじゃない」というか、それ以上はあまりお近づきになりたくないなぁ、という感じでしょうか
・ 腹がたちました。特に大変なことはないし、かわいそうでもない。ただ単に両親が聴覚障害ということだけと思いました。
・ 反発。別段かわいそうとも大変とも思っていなかった
・ 腹立たしく悲しくなった
・ はらが立つけど一言(?)話します。経験がありますかと聞くとない返事です。
・ 「大変」とか「かわいそう」は、うちの家族のことをよく分かってもいないのに無責任だと腹立たしさ&悲しさを感じたが、今は、そういった目で多くの人々は見るのだと理解している(別にあきらめているわけではなくて、少数派だから、ちゃんと多数派に理解してもらえるように、説明が必要なんだと感じている)。
・ 父や母が社会的に弱い立場の人間だと言われているようでなんだか悲しかった
<交錯した思いを持った>
・ うざい、面倒くさいと思う反面、悪い気もしなかった
・ 言われた際の精神的な状態もありますが、情けないのと、承知してるのと交合。
・ 同情と、理解の交錯
<がんばらなければと思った>
・ がんばらなければいけないと思った。
・ 『うん、がんばる!』とちいさい時は思っていた
・ 小さい時は、「うん、がんばるっ!!」って。
・ 幼い頃は、「あなたがしっかりしなくちゃ」と言われた時、頼られているようで、誇らしげに感じることもあった。ある程度成長すると、少しプレッシャーを感じた。
・ 素直に『がんばらなくちゃ』と思った。両親を助けることは自分の役目だと思っていたので『うん、そうだよね』と再確認した感じです。「かわいそう」と言われたおぼえはないです。同じ兄弟なのに、私と弟は全然違う感じ方をしていたことを知った時、正直おどろきました。
・ ほとんどのcodaはイヤみたいだったが、私の場合、励みになった。「もっと頑張らなくっちゃ」と活力になった。また、そう言われることによって、「この人は私のしんどさを分かってくれているんだ」と思っていたのかも。(付記として)親戚の対応も様々だが、親戚の何気ない言葉に感動して泣くことがたまにある。例①「頑張りすぎや。そんな頑張らんでいい」、②「お前に万が一のことがあった時は2人の面倒はみるから」
<その他>
・ 優えつ感があった
・ 何とも思わない!!
考察
質問では、「大変ね」「かわいそう」「あなたががんばるのよ」を同じように並べて訊いてしまったが、回答を見ると、「大変ね」「かわいそう」と言われた時と、「あなたががんばるのよ」と言われた時とでは、感じ方が異なっているらしいことが窺えた。「大変」や「かわいそう」は、自分の家族とあまり関わりもない状態で、勝手にそういう見方を押しつけられたような印象が強いのかもしれない。一方、「あなたががんばるのよ」は、多少関わりのある人が口にする言葉であるとも言える。それが不快に感じるか励みになるかは、その相手と自分の家族の関わり方や、言われた時の年齢によって変わってくる。全体的に、小さい頃は素直に「がんばろう」と思えるようだが、大きくなるにつれて負担に感じられる面も出てくるようである。
このような言葉を言われた時の思いとしては、自分の感覚とは合わないと感じた人が大多数だった。それは、不思議さや違和感として表現されたり、「自分は人からはそう見えるのかー」という外部の視点の発見として語られたり、実情を知らないままいろいろ言われることへの反発として語られたりしていた。
質問29 何か問題が起きると、親が聞こえないせいにされるという意識はありましたか?
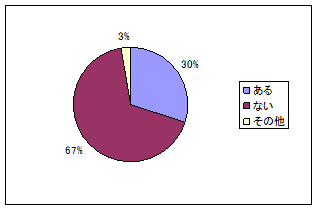
「ない」と答えた人の記述
・ 親のせいにされて欲しくなかったため、努力はした
「その他」の回答
「ないというかあるというか…」
→自分では思っていなかったが、コーダの先輩が「常識に欠ける行動をすると親が聞こえないからと言われる。だから行動には注意するように」と言っていた。
(「ある」と答えた人に対して)もしよかったら、具体例を書いて下さい
・ 父がたの祖母は僕の行儀が悪いと「親が聞こえないからしつけができていない」と言いました。小学校の先生は僕の態度が悪いと「親が障害者で誰もが同情すると思っていい気になるな」と言いました。
・ 親のことをバカにする同級生や上級生に暴力で対抗したら、先生からよく「親が聞こえないとこうなのか?」と言われた。
・ 内容はともかく、トラブルの元が家に関わっていると、「聞こえないんだからしょうがないか」とか言われる事に腹が立っていた
・ 私が自宅に居ない時に学校から電話がかかってきた時。
・ 親のコミュニケーションの失敗で自分にまで影響が及んだ時
・高額のローンを組まされて生活が厳しくなった
・近所付き合いが上手く行かず、近所の人から苦情を言われた(町内会活動等)
<「親が聞こえないから」と言われないよう気を使った>
・ 親が聴こえないから、躾が出来ていないと言われないように躾が厳しかった分、外ではいい子でいるように気を使った
・ 言動等(親の躾がなっていないと思われるのではないか)
・ 絶対に不良にはならないぞ!と思っていた。
・ そもそも、なるべく問題を起こさないようにした
<具体例は忘れた>
・ 忘れた。言葉遣いがうまくできない時
・ 忘れた。
考察
何か問題が起きると親が聞こえないせいにされるという意識を持っていたのは、全体の3分の1ほどの人で、大多数はそうした意識を持っていなかった。しかし、そのような意識が「ある」と答えてくれた人の自由記述からは、「親が聞こえないから躾ができていない」というように、「聞こえないこと」と「子どもに対する親の教育能力」が結びつけて考えられるような風潮があることが窺える。そのような見られ方を意識して、問題を起こさないようにしたりいい子でいるよう気を遣ったり、コーダが自分の行動を自分で律している面もあるようである。
質問30 親が聞こえないことを自分からまわりに言っていましたか?自分の認識に近いと思うものに○をつけて下さい
|
できるだけ隠すようにしていた
|
6
|
|
隠しているという意識はないが、特に言わなかった
|
11
|
|
機会があれば話していた
|
22
|
|
いつもまわりに言っていた
|
6
|
|
その他
|
2
|
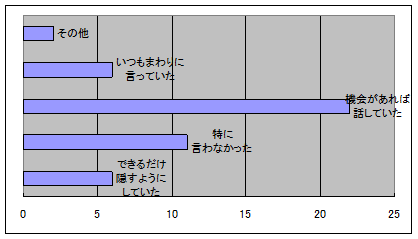
「その他」の回答
・ 学校の先生にも皆にもよく言っていた
・ 高校生時代の彼氏に何故か言えなかったが、後に彼が手話に関心を抱いていた事を知り、それからは付き合う人には最初に言う様にしていた。
書き込みのあった回答
・ 隠しているという意識はないが、特に言わなかった(学生時)、機会があれば話していた(大人になってから)
・ できるだけ隠すようにしていた(他の家とは違うと思い始めてから祖母が亡くなるまで)
考察
この質問では、複数の選択肢に○をつけた回答者が何人かいた。親が聞こえないことを他の人に言うかどうかは、時期によって変わってくる面も大きく、そのために、複数の○をつけることになったようである。明確に、「隠しているという意識はないが、特に言わなかった(学生時)、機会があれば話していた(大人になってから)」と、時期によって違うと書いている人もいた。また、「できるだけ隠すようにしていた」に○をしつつ、「他の家とは違うと思い始めてから祖母が亡くなるまで」というように、そのような態度をとっていた時期を限定して書いた人もいた。全体的に、大人になるにつれて、積極的に話そうとする方向へ動いてくるようだ。
質問31 両親と聞こえる人が一緒の時、自分が音に敏感になることはありましたか?
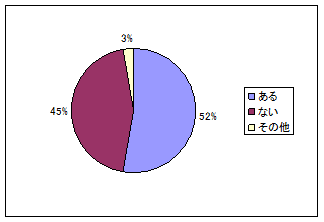
「ない」と答えた人の記述
・ 日常的に音には敏感であるような気がするので、輪を掛けて敏感になるようなことはないと思う
・ あるのかもしれないけど、敏感になってるかどうかは自分ではわからない。
「その他」の人の回答
・ むぅ~…。
(「ある」と答えた人に対して)もしよかったら、具体例を書いて下さい。
<親の出している音が周囲の注目を集めないようにする>
・ 親の発声を出来るだけ抑える
・ 親が声を出した時。昔は親が声を出してそれを聞こえる人が見てその時の顔を親が見ないように気を使った)
・ 母の声に敏感であった。とても嫌いだった。
・ 声を大きく出していたり、物を噛む時の音、ドアの開閉とか。。。
・ 話す声の大きさとか、物を置く時の音など
・ たとえば、外食しているときに、手話の音(口のpaという音や手が当たる音)がなるたびに周り客から注目されるとき。
・ 周りの人が気になるような音出していないかな?昔、両親と劇場に行った時、父親の呼吸音がうるさく、注意しようかどうしようか大変悩んだ。「息しないで」とはいえないしなぁ・・
・ 親が物を食べている時の音や、足音、携帯の着信等
・ ものを食べるときの音、息遣い
・ 食事をしているときなど、「フォークがお皿に触れてカチャカチャいってるよ」や「声が大きいよ」など。
・ スープを飲む音や物を動かすときの音などは気をつけて親に知らせていた。
・ ずっと団地に住んでいるので、生活音全般、特に近隣に響くような音には敏感。(足音、ドアの開閉、夜中の掃除、日曜大工など)
・ 親が入院している時
<親に音の情報を伝える>
・ やはり、両親は聴覚障害者なので、私と両親が一緒にいる時は、両親の耳代わりにならなければと思っていたから。
・ 自然と周りの状況を伝えなければと意識の中で
・ 何の音かも両親に伝える事が大切と考えるので細かい事も通訳しました。例えば、・今ドアが開いたよ。・車が止まった。・ベルが鳴る。
・ 車等の音を伝えたり、注文の通訳
・ 駅の放送で、「電車が遅れる」といったアナウンスがあって、周りの人が動き出していた時、両親に周りの変化のわけを説明しようと感じる。
・ 放送などを通訳してたかも。おぼろげですが。ないという選択肢は当てはまらないとおもいなんとなくあるにした程度です。
・ 物とかがおちたりするときはある。
・ 声で呼ばれたり、声をかけられたりする時
<その他>
・ 忘れた
考察
全回答者の52%が、両親と聞こえる人が一緒の時に音に敏感になることは「ある」と答え、45%の人が「ない」と答えた。「ある」と答えた半数の回答者の答えを見ていくと、音に敏感になるのは、親の出している音を他の聴者に変に思われないようにするという場合と、親に音の情報を知らせなければ(音の意味を通訳しなければ)という場合の2つがあるようである。前者では、声の大きさ、物を食べたり飲んだりする時の音、ドアの開閉、携帯の着信など、聴者であれば、立ち居振る舞いやマナーとして捉えられるものが多く挙がっている。また、不明瞭な発音や呼吸の音などは、親としては自然の状態であるので、言うかどうか迷う局面があるのかもしれない。後者としては、呼びかけられたり(声、ベル)、物が落ちたり、車が近づいていたりといった周囲の状況を気づかせるという面と、放送のように音声で流された情報を説明するという面があると言える。
質問32 自分の気持ちとして、親と深くコミュニケーションできていないという思いはありましたか?
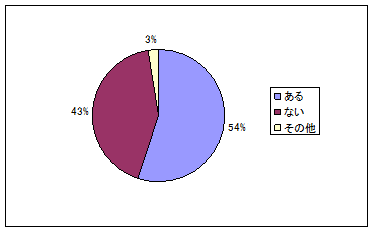
「ない」と答えた人の記述
・ 世間並だと思う
「その他」の回答
・ あるような、ないような
(「ある」と答えた人に対して)どういう時にそう思いましたか?
<自分の言いたいことを親に伝えられていないと感じる時>
・ 自分の言いたいことを十分伝えられない。
・ 言いたいことがうまくいえないとき。
・ 言いたい事がうまく伝わらない
・ 悩みを相談したくても、手話でどう表現するかわからない。いつも忙しく、夜も遅いし、甘えたくても甘えることが許されなかった
・ 手話は苦手だったけど、父に一生懸命手話で話をしたのに、ちゃんと理解してもらうことができなかったとき。
・ 一生懸命話しているのにわからないといわれるときなど
・ 話していても或る程度まで行くと言葉が通じてない・・・と思い、諦めてしまう時
・ おこった時に、うまく気持ちが伝えられなかった
・ 喧嘩になったとき。感情的になった時。
<進路や思春期の話が伝わらない>
・ 将来の話しをしている時
・ 中学・高校の時は進路の話をするときや、友達から親との喧嘩話を聞くときなどに、そう感じたことがあった。
・ 手話が苦手なまま思春期に入った時。
<筆談や口話、ホームサインの限界を感じる時>
・ 自分の気持ちや将来の進路、考え方など、複雑な話をしようとすると、筆談や口話では、伝わりきれない部分がある(自分の気持ちをぴったりと表わし、それを両親に伝える手段が足りない)と感じた時。
・ 小学生~中学生。口話と手話単語、ホームサインなどだったので込み入った話は通じていないことが多かった。
・ 母親が口話で話すのをみて、無理しているだろうと思える。
<親の対応を見て>
・ 論理的に話を構築しても理解されない。特に善悪で判断出来ない内容を話し合う時に苦労した
・ 例えが伝わらない時。つまり親がその例えの内容を知らない。情報を知らない時。
・ 誤解されて怒られている時。
・ なぜそういうことをしたのか?言ったのか?を問うても2人が答えられなかった時
・ 親が聞こえる人にするみたいにわたしに適当に相槌打っていたとき。
<日常的にあまり深い話ができていなかった>
・ 説明する事が面倒だったので、ほとんどは表面的な事での会話が多かった。ただ、母親は私達兄弟の顔色は顔付きで察した事が多々ありました。
・ 自分の言いたいことをきちんと親に伝えられない時。日常起きたことなどを親に報告したりしないから。
・ 日々常々
<その他>
・ 親同士や親と親のろう者の友人が話している手話が読み取れない
・ TVで、どんな内容なのかを訊かれ、それに満足に応えられなかったり、議論できなかったりする時
・ 姉に通訳してもらってるとき。
・ 分からない
考察
回答者の54%の人が、親と深くコミュニケーションできていないという思いが「ある」と答え、43%の人が「ない」と答えた。「ある」と答えた人がそう思う具体的な場面として多かったのは、自分の言いたいことが親に伝わっていないと感じる時だった。ここでは便宜的にいくつかの項目に分けたが(「自分の言いたいことを親に伝えられていないと感じる時」「進路や思春期の話が伝わらない」…)、これらの項目同士は実際にはかなりつながっていると考えられる。つまり、どこをクローズアップするかによって語り方が異なるというだけで、人によって「伝わっていない」と認識した自分の感覚が前面に出される形で表現されたり、進路といった話の内容や、口話などのコミュニケーション方法や、親の対応や日常の関わり方などが中心的に語られたりしていると言えるだろう。
ちなみに、深くコミュニケーションできていないという思いがあるかどうかと、親とのコミュニケーション方法がどのようなものであったのか(質問9)は関係があるのかと考えて見てみたが、この二つには特に目立った関連は見られなかった(ただし、統計的な処理はまだ行っていない)。コミュニケーション方法に関係なく、親とのコミュニケーションの不全感を持っている人は持っていたし、持っていない人は持っていなかった。
質問33 中学・高校生の頃、親を一般の聴者より低く見てしまった時期はありますか?
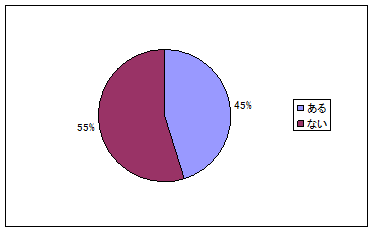
「ない」と答えた人の記述
・ 文章を書くことにおいて、小学校の時から両親の代わりに文章を書くことがあった為、「なぜ文章が書けないのか」を不思議に思うことはあったが、当たり前になっていたことで「低く見てしまう」というようなことはなかったように思う。また、小学校の高学年で両親からつらい口話教育の話を聞いたこともそれに起因していると思う。
・ 但し、小学生の時、設問26の弁当の件(←友達の弁当は凝った盛り付けがしてあるのに対して、自分の弁当は子ども受けするような中身ではなかったこと)で、世間知らずだなと思った
(「ある」と答えた人に対して)それはどういう面に関してですか?
<日本語や文章力の不足>
・ 日本語・文章の理解力が乏しい事で
・ 学校の先生や市役所などで、筆談するときに日本語の文章がちゃんとしていない。
・ 文章のチェックをしてほしいと頼む時。文章が読めない時。
・ 両親の書いた文を自分が見直しているとき。
・ 文章力
・ 漢字の読み書きができない
・ 新聞を読んでも「この意味は何?」と聞いてきたこと(しつこかった)
<情報の少なさ、一般常識の不足>
・ 世間の情報について知らない時
・ 流行語が伝わらない時
・ 自分の情報量が少ないということを、母親は耳が聞こえないせいにしていた。すごくがっかりした。
・ 情報不足からくるものの知らなさ。
・ 一般常識の欠如
・ 「聴者と比べて/ろう者だから」ということを意識していたかは分からないが、母親の常識のなさに対して反感/抵抗感を持っていた(父親に対してはなかった。)
・ 勉強の事や社会についてや常識面等
・ 学力、一般常識
<勉強や進路を自分で解決しなければいけない>
・ 親は受験などの知識がないので、自分で塾や学校など調べなければならなかったとき。勉強など教えてくれたことがない。
・ 進路を決めるとき親には相談できないと思った
<論理的な話や哲学的な話が伝わらない>
・ 論理的な会話が成立できないこと
・ なにか哲学的なことを話すと分かってもらえなかった時→今思うと聾者特有の例えが自分から提供できずうまく伝わらない。手話で話しても話の起承転結が聴者だと伝わらない
<生活水準>
・ 周りの家庭との生活水準の格差
・ 貧乏といつも言ってたから(笑)
・ 給料が安かったこと。(漢字の読み書きや新聞を読んで意味を聞いてきたという項目と合わせて)→ とにかく反発心。「なんでだよ」という感じです。
・ 教養、生活・・・
<その他>
・ 親と自分を比較していたように思う。なので、「小学生の私でもこんなこと知っている(できる)のに」と思ってしまうこと全て。
・ 他の子は当たり前のように、親からいろんなことを教わってきているのに、私には知らないことが多すぎると気づいた時。
・ 親と聴者が話している場面で聴者同士が雑談のなかで馬鹿にされている姿を聞いてしまったとき。<親本人は気づいていない>
・ 弟はいろいろ悩んでいたようですが、私はまったく思ったことがありませんでした。弟の専門学校の時のコーダについての授業の時のスピーチの原こうを読んで初めて、そういう考え方もあるんだと知りました。本当にびっくりしました。「助けてあげなければいけない人」=「劣っている人」のイコールの図式は、私の中には生まれてくることはありませんでした。でも、もしそう思ってしまったら、それはつらいことだと思います。
・ めんどい所
・ ・・・
その思いはその後、どう変わっていきましたか?
<大人になったら、案外普通だった>
・ 大人になってみたら、普通だった。逆に人間的にも精神的にも純粋で向上心ゆたかで尊敬できました。
・ 一般常識は普通にあるんだと思った。文章力もあるほうだと思った
・ 一般的な「ウチの親はしょうがないな」と変わらないと思う。
<親のことを理解するようになった、サポートを心がけるようになった>
・ 一般の教育とろう者への教育方法が違うのだと本で読んで知ってから、必然のことだとわかったので、今は仕方ないことだと思っている。日本語の能力がないことがイコール学力のないということではないとわかった。
・ いわゆる反抗期が過ぎ、また、ろう者の教育・言語背景に関する知識が増えたのに伴って、母親の常識のなさに対する反感は消え、今はむしろ、できるかぎりサポートしたいと思うようになった。
・ 何とも思わなくなった。逆に、不快ではなく、覚えてほしいなぁとか、分かってくれたかな?と思うようになった。
・ ろう者としてのアイデンティティを認めれるようになった。情報不足は仕方がない。社会資源を利用していかに生きるかが大切と思うようになった。同時にコーダとしての自覚も目覚めてきた。
・ 論理的な会話については半ば諦めつつも噛み砕く会話を心がけるようになった
・ 両親から手話をもらったぶん、自分は、分かることは、両親に教えてあげたい。
<親を肯定的に見るようになった>
・ 生活水準に関しては自分が社会に出た時にここまでの安い給料で育ててもらえたことに尊敬の念を覚えた
・ 通訳を志す少し前から、自分が親よりも劣っている事が沢山有ると気付いた時から知識云々よりも自分より強く生きてきた親に感心した
・ 素敵だ。低く見ることを取ったら、母と父の個性が見えてきた。それは本当に素敵だった。私の戦友→すれ違いのつらさを一緒にすごしてくれた戦友??みたいな同士みたいな
<その他>
・ 一般常識は少しずつ前進するしかないと覚悟した
・ あきらめました。期待をしても無駄だと分かった時
・ 両親の友だち以外のろう者と知り合いになるまでは「ろうだからできない」「ろうだから理解できない」と思っていたが、そうではないことがわかり、親への見方が変わった。
・ その分は、自分でいろんなことに興味を持って、勉強していこうと思った。
・ ふつう
・ よく分からない。変わったような気もするし、変わってないような気もする。
・ ・・・
考察
親を低く見てしまったと答える人は半分以下の18人で、どちらかといえば少数派だった。その人たちに「どういう点に関してそういう思いを抱いたか」と尋ねると、日本語や文章力の不足、情報の不足やそこから来る「常識」の不足、学力、生活水準などが挙がった。これらは、日本語が苦手な他のマイノリティの親(たとえば、中国帰国者や日系ブラジル人などのケース)についても言えることではあるが、やはり、「聞こえないこと」を取り巻く環境とも密接に結びついている面もある。そのため、大人になってそうした背景を知るようになるにつれ、親を低く見ていた人でも、そのような見方を変えていく人が多いようだった。
質問34 親が聞こえないとか、自分の体験について、自分以外のコーダやきょうだいと深く話したことはありますか?
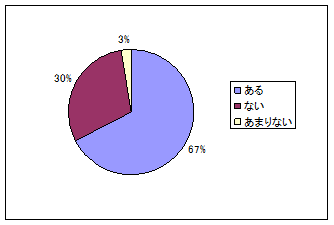
(「ある」と答えた人に対して)そういうことについて話したのは、自分が何歳ぐらいの時ですか?
|
|
N=27
|
|
15未満
|
2
|
|
15-20未満
|
5
|
|
20-25未満
|
9
|
|
25-30未満
|
2
|
|
30-35未満
|
3
|
|
35-40未満
|
0
|
|
40以上
|
2
|
|
成人してから
|
2
|
|
ここ数年
|
1
|
|
無記入
|
1
|
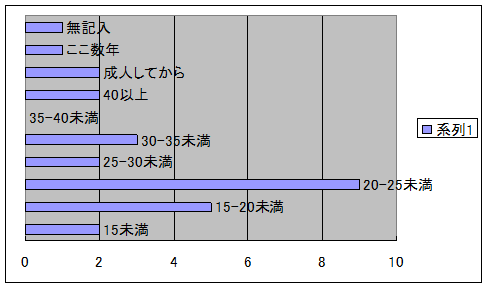
考察
回答者の3分の1近くは、親が聞こえないとか自分の体験について他のコーダやきょうだいと深く話した経験は「ない」と答え、3分の2が「ある」と答えた。「ある」と答えた人の中では、若い時期に、そういう話をコーダ同士で共有したことがある人が多く見られた。これは、日本全体の聞こえない親を持つ聞こえる人々を考えた時にはまだまだ珍しく、コーダの一般的な体験ではないと思われる。やはり、「コーダの会」を中心としてアンケート協力者を募集したということに由来するものであろう。
注目したいのは、10代後半から30代というのは、進学や就職、転職、結婚、出産など、人生に大きな影響を与える選択や出来事を経験する時期でもあるという点である。次の質問に見るとおり、コーダ同士で話すことは、ある意味で自分自身を整理する側面も持っており、それは、これらの具体的な選択に影響を与える面もあるのではないかという気がする(←インタビュー結果からは、職業選択や結婚について、それを裏付けるような話もかなり出てきている)。
質問35 自分以外のコーダと話すことは、自分にとってどういう意味がありましたか?
<自分を振り返るよい機会になった>
・ 自分を見つめ直すきっかけになった
・ 一度立ち止まって、自分のこれまで歩んできた道のり、人生(大げさですが)をきちんと振り返る良い機会になりました。また、自分の中にある、いわゆる「ろう文化」と言われる習性、習慣、感覚など知ることが出来て…もっと自分や両親を観察してみたいなぁ、なんて思ったり。
・ 「コーダである」ことがその人に与える影響について客観的に考えるようになりました。自分の性格や行動を「コーダだから」と自覚してふり返って考えるようになったのはこの時からです。
・ 自分で「私って変かも?」と思っていたことが、「codaだから」だと分かり、自分を好きになれた。又、自信が持てるようになった。
・ カルチャーショックだった。今まで自分の家だけだと思っていた事が、コーダでは当たり前の感覚のものだったとか、そうゆう事を知れたのが嬉しかった
・ 自分の整理ができた。
・ 新しい自分の発見。他のコーダと自分を比較して、冷静に親を見れるようになった。
・ とても重要な体験。発見。
・ 自分がいかに手話を理解していないかを感じる。手話を勉強したいと思わせる。
・ とても参考になります。
・ アイデンティティの確立の促進。
・ 聴障者と健聴者の違い(ギャップ)を把握すること
<安心する、嬉しかった、共感が持てる、仲間意識がある>
・ 同じようなバックグラウンドを持つもの同士なので、なんとなく…ものすごく近い存在の人たちと接しているような気がして…安らぐ
・ 気持ちを分かってくれて安心した。
・ 価値観の共有を前提として愚痴や悩みを話せる、疎外感をなくす
・ 自分だけではなく、周りに同じような環境で生活をしている人がいるんだなという、安心感や一体感がある。
・ どこか心地良かった。自分以外にも同じように感じる人がいた
・ 同じ立場(コーダ)である人が身近にいて癒された。
・ 同じ立場の友達。
・ 仲間意識の築き
・ 単純に嬉しかったです。仲間意識みたいなものはありますかね。
・ 環境が別でも境遇は同じ。仲間との意識はありました。
・ 妙な嬉しさがあった。学校の友達との間では決して話に出なかったような些細なトピックを共有でき、分かり合えることが素直に嬉しかった。「他とは違う」という意識が薄れていくような気がしたかもしれない。
・ 同じ体験をした人たちと会うことで、普段味わえない「共感」を得ることは大きかった。
・ 共感が持て、本当の意味で自分を理解してくれてるようなきがした
・ 心が自由であった。
・ 楽しい共通認識
<いろいろな感情が湧きあがる>
・ 自分は特別じゃないんだとホットしたし、ちょっと前の自分を見ているようで恥ずかしくなるときもある
・ 皆と話すと同じ点を見つけ、楽しくなり、又、両親の事を話せると喜びがわきます。
・ ホッとする。楽しくなる。おもしろい。勇気が出る。がんばろうって気持ちになる。がんばれって気持ちになる。励みになる。むかつく時もある。とにかく自分の色んな感情が湧き起こる。
<コーダにもいろいろないる人がいることを知った>
・ 自分とは全く違う思いをしているコーダがいることにびっくりした。親を恥ずかしく思っていたり、手話が嫌いだったりするコーダが思っていたより多くいて、自分が例外的であることを知った。
・ うちは珍しいんだ、という意識を改めて感じたが、それを理解し合える仲間がいることへの驚きがある。
・ 最初はコーダの中でも自分は特異だと感じた。次第に、共通のこともあり、違うこともあり、結局は人を枠にはめることはできないものだと思うようになった。
・ コーダでもいろんな状況の人(手話の理解度、両親との関係、親が聞こえないということから生まれる社会の見方など)がいることを知り、自分もその一部であると感じた。
・ コーダにもいろんな人がいるんだなって思った。自分が通訳しなければいけない!!と自分自身に言い聞かせているコーダがいて、親もそのコーダにかなり依存していて、いろんなことに消極的。私の家では、どちらかというと通訳は通じない時だけ、それ以外は頑張って自分でコミュニケーションとってという、突き放した感じだったので、親はいろんなことにチャレンジして積極的になり、仕事をしたり車に乗ったり出来るようになった。親に冷たい事してたかなって思った時期もあったが、依存されて消極的になるよりはよかったと思った。そのように同じ環境でもいろいろあるんだということがわかった。
・ コーダだからといって全て共感できることもないとわかりました。
<意味があるとは思わない>
・ 特に何か意味があるとは思いません
・ 特に意味はないと思う。多少の親近感があるかも。
・ 特に意味なし
・ 特になし
・ コーダとして接することなく友達として接していた。
<まだわからない>
・ そのことについて、深い話をしたことがないため、わかりません
・ まだ分からない。姉としかまともに話をしたことがないので。
・ コーダという言葉をつい最近知ったので!!
<その他>
・ コーダ同士で話しをしたい人がたくさんいると思った
・ 自分の体験が役立つならと思い
考察
多くの人が、コーダと話すことにプラスの効果を見出していた。それは、直接的には、自分だけではないという安心感や話が通じることへの心地よさ、共感したりしてもらえたりすることへの嬉しさとして感じられていた。インタビュー調査のほうでは、コーダと話すことに関して、「普通の人だと、「あー、そうなんだ」で終わってしまう。そうでなくて、「あ、そうだよね」と言ってもらえるのは大きい」ということを語った人が複数いた。それは、コーダであることにまつわる話は、普段は訊かれる機会があまりなく、たとえしたとしても聞こえる人が相手だと、盛り上がらずに終わってしまったり誤解されたりしてしまう(「大変」というふうに捉えられるなど)という状況を背景にしている。また、コーダであることに関する話は、ろう者に対してもしにくいようである(たとえば、「うちの親ってこうなんだよ~」と話した時、コーダならその発言の裏にある親への愛情も汲み取ってくれるが、ろう者から見たら、単に聞こえない親を批判しているというふうに見えてしまうかもしれないという恐れがあるようだ)。コーダ同士なら笑い話になるところが、聴者が相手でもろう者が相手でも重くとらえられすぎてしまうということが、コーダの話が表に出てきにくい要因として働いている。
また、コーダ同士と話をすることは、自分自身を整理したり、自分と親との関係を見直したりすることにも効果をもたらしていた。他のコーダとの共通点を知ることは、それまで「自分だけ変」と思っていたことが、コーダであるゆえの環境的なものに由来する部分もあるのだという発見につながっていた。逆に、他のコーダと自分の違いは、親が聞こえないという条件でもいろいろと違いがあるのだという認識となり、自分はどういう状況にいるのかを客観的に把握する手がかりとなっているようだった。
しかし、その一方で、コーダと話すことに「特に意味があるとは思わない」という意見もあったことは、付記しておきたい点である。
質問36 聞こえない人のやり方と聞こえる人のやり方は違うとか、「ろう文化」といった情報を知っていましたか?
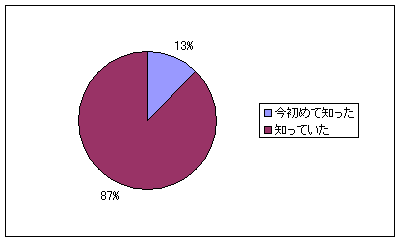
聞こえない人のやり方と聞こえる人のやり方は違うとか、「ろう文化」という情報を知ったのはいつですか?
|
小学生期
|
4
|
|
中高生期(12-18歳)
|
6
|
|
高校卒業後~20代前半(19-25歳)
|
13
|
|
20代後半~40歳未満(26-39歳)
|
4
|
|
40歳以上
|
2
|
|
今初めて知った
|
5
|
|
その他
|
2
|
|
わからない
|
1
|
|
無記入
|
4
|
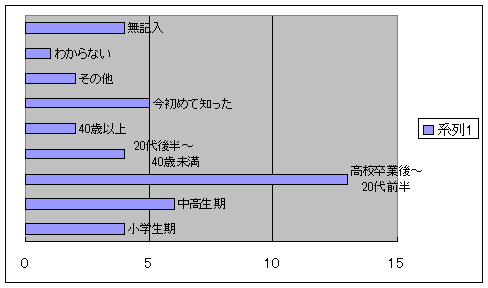
「その他」の答え
・ 今から10年ぐらい前
・ つい最近
書き込みのある回答
・ ろう文化というよりはろう者の癖みたいなものはあるなぁという程度です。親以外のろう者と関わるようになってからなので、中学生くらい?
・ a.「聞こえない人のやり方と聞こえる人のやり方は違う」ということは、小学生の頃から、地域のろう協の行事に参加するときとかになんとなく感じていた。b.「ろう文化」という概念を知ったのは、18歳のとき、大学の生協書籍部で「ろう文化」の本がたまたま目に留まり、立ち読みしたのがきっかけ。(←「小学生期」と「高校卒業後」の両方にカウントしました)
(「知っていた」と答えた人に対して)どのようにして知りましたか?
<ろう者から聞いた>
・ Dプロのメンバーの方たちと知り合って
・ Dプロに出会って
・ D―プロを通して
・ 大学の手話サークルに入って同年代のろう者と交流を持った時に知った
・ 同世代のろう者と付き合うようになって
・ ろう者の友達と話などして。
・ ろう者の話しから
・ ろうの姉から聞いた。
<CODAの友人やきょうだいから聞いた>
・ CODAと話などをして。
・ 友達から聞いた
・ 姉から聞いた
<手話の勉強をする中で知った>
・ 手話を勉強しはじめて
・ 手話の学習を始めてから
・ つい最近。手話学習を経て。
・ 手話の専門学校に行ったり、聾文化などの講演会に参加したりして。
・ 通訳者養成学校に入学して授業で知る
・ 現在の学校で、学んで知りました
・ 地域の手話講習会のなかでそういう話がろう者からされた
・ 講習会で教わった。自然に家でやっていることもあった。
・ 手話講習会
・ 手話講習会や手話サークル
・ サークルや講習会で。
<本を読んだ>
・ 同時期に大学の図書館にあった「ろう文化」という本を読んだ
・ 聾文化宣言という本
・ 本を読んで
<以前から知っていた>
・ 小さい時から親に聞かされていた。
・ 親と一緒に米内山さんの劇を見に行った時にパンフレットに書かれていた文章の中に「ろう文化」と書かれていたと思う。
<その他>
・ 自分が手話通訳として働きだし、他の通訳の方がふえはじめてきた頃
・ 進学して、研究室に入ったことをきっかけに
・ ボランティアで、両親以外のろう者と接してから、聞こえる人のやり方と違うことを改めて感じてから(家族とのやり取りは、自分にとって日常なので、改めて違うと感じることはあまりなかったので。)
・ 当時の両親の友人である手話学習者より、いろいろと教えてもらうことができた
・ 情報に疎く、事柄や事案について誤解や間違いがある。
考察
全回答者のうちの35人は、聞こえない人のやり方と聞こえる人のやり方は違うとか「ろう文化」という情報を知っていた。これほど多くの人が知っているということからも、今回のアンケートの回答者は、コーダの全国的な平均よりも、手話やろうの世界に関わっている人に偏っているということは言えそうである。
こうした情報を知ったのは、高校卒業後~20代前半である人が最も多く、そのプロセスとしては、「手話の勉強を通して」と「ろう者から聞いた」という回答が多く挙げられた。また、本を読んだり「コーダから聞いた」という答えもそれなりにあった。このような情報や考え方は1990年代前半に日本に紹介されたものであるため、親から聞くという形で伝えられるのではなく、体系的な手話学習や本で知識として教えられたり、両親よりも若い世代のろう者やコーダとのつきあいの中からもたらされたりしているというのが見てとれる。
質問37 「コーダ」という言葉を知った経緯について教えて下さい。
<日本で初めてコーダの会が結成された時に参加して>
・ 1995年、ミリー・ブラザー氏が来日して、コーダが集まったところに出席して
・ Dプロメンバーの方から「ミリーさんというアメリカのCODAが来日するよ」と
・ D-プロが(確か10年前になると思いますが)アメリカでコーダという組織を最初に創設した女性を招待して講演会を
・ コーダ結成式の時に参加して
<本を読んで>
・ 「ろう文化」という本を読んで
・ ろう文化宣言の本をみたとき、その中にコーダの人の文が載っていた
・ 上の質問の(b)の時(←18歳のとき、大学の生協書籍部で「ろう文化」の本がたまたま目に留まり、立ち読みしたのがきっかけ)に知った。
・ 『はじめての手話』という本のコラムを読んで
・ 大学で、ポールさんの『きこえない親をもったきこえる子どもたち』(題名、違っていたらすいません)を、偶然見つけて読んでから知った。自分のような立場には、「コーダ」という分類があって、それが研究の対象となることに、衝撃を受けた。
・ 友人がMother Father
Deaf(←『聞こえない親をもつ聞こえる子どもたち』の原書)という本をアメリカから買ってきてそれをプレゼントされ、ぱらぱら見ているうちにCODAということばが出てきて、知った。
<手話の専門学校で>
・ 手話の専門学校に行ったときに、学校のろうの先生が、私にお前はコーダか?と聞かれた時、初めてそういう言葉があるということを知りました。
・ 現在の学校で、そういう言葉があることを知りました
<手話サークルや手話講習会で>
・ サークルの人に教えてもらって。他のコーダと知り合えた
・ 手話サークルに行って、自分の親が聞こえないと話をした時に教えてもらいました。
・ 忘れましたが、おそらく講習会だと思います。
・ 大学の手話サークルに入った時にメンバーから聞かされた
<ろう者から聞いた>
・ 地元の聴覚障害者協会会長より紹介された
・ ろう者の友達が教えてくれた。
・ たまたま参加させてもらった「デフ・ファミリーの会」で自己紹介した際、木村晴美さんに教えていただいた(12~13年前)。「**の娘」という私から「codaの**」という私に生まれかわった瞬間で、とても衝撃的だった。呪縛から解放されたような感覚(親のために生まれてきたのではなく、「私は私でいい」)
<コーダから聞いた>
・ コーダに会って聞いた
・ コーダの友達から教わった
・ 都の講習会で、J-CODAのメンバーがいた。その人から「コーダ」というのだと教えてもらった。
・ 2~3年前、こころおとの武井君とのメールのやりとりをしていた時。
・ 数年前に、地元で一番交流のある「聞こえない親を持つ先輩」から教えてもらった。
・ ずい分前にコーダーが集まる会があり、その時知った。
<きょうだいから聞いた>
・ 「ろう文化」の話を聞いたときに、ろうの姉から聞いた。
・ 弟が世田谷福祉専門学校に通っていた時に私に教えてくれました。
・ まず姉が「コーダ」というものに興味を持ち、私にいろいろ教えてくれた
・ 姉から聞いてすなおに自分的に「カッコいい」と思った!!
・ 姉より最近
<その他>
・ 研究室の先生から、そういった話を聞かされて
・ 職場で出会った人に両親のことを話すと、君はコーダだなといわれその時知った
・ インターネットで
・ 今から10年前位だと思います。
・ 5年前の30歳ぐらい
<今知った>
・ 今まで知らなかった。
・ 初めて知りました。
・ 今知った!!?
考察
「コーダ」という言葉に関しては、前の質問で尋ねた「ろう文化」よりも、本という媒体や、コーダやきょうだいから聞く(外国のコーダから聞く場合も含めて)という形で伝わることが多いようである。「コーダ」は「ろう文化」と同時期に日本に紹介された概念ではあるが、ろう者や手話学習者の中では「ろう文化」ほど知られていない。調査者が今までに見てきた限りでは、おそらく、それには、「コーダ」のカタカナ表記や英語表記(CODA)が一般的にわかりにくい言葉であること、コーダは聞こえる人であることもあって手話学習の中でもおまけ的に扱われる傾向にあることが影響していると言えそうである。また、手話学習の場では、コーダは「聞こえない親を持っていること」を自分からはそれほど言わないという風潮もあり(「コーダ」と言うと手話がうまくて当たり前と思われるため)、「コーダ」という言葉の伝播は、本を読むという個人的な体験や、自分がコーダだと知っている人からの親しい個人的なつながりによる傾向がある。
質問38 「コーダの会」を知ってますか?(当てはまるものすべてに答えて下さい)
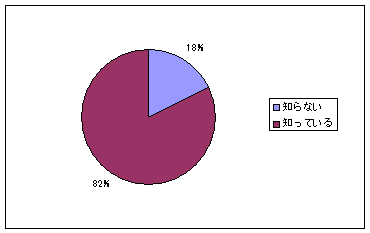
考察
知っていると答えた人が、全体の8割を占めた。これも、「コーダの会」のメーリングリストやメンバーの紹介によってアンケート協力者を募集したという、このアンケート調査のやり方に由来していると考えられる。日本全国で見た場合、このように「コーダの会」の存在を知っているコーダはここまで多くなさそうである。
「知っている」と答えた人の「コーダの会」への関わり方
|
|
N=33
|
|
知っている
|
6
|
|
知っている+メーリングリストに登録している
|
7
|
|
知っている+参加したことがある
|
6
|
|
知っている+メーリングリストに登録している+参加したことがある
|
14
|
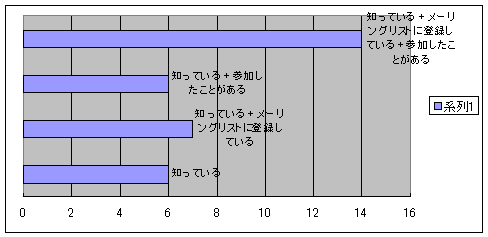
(「知っている」と答えた人に対して)どのようにして知りましたか?
<コーダの会が設立される時にいた>
・ 設立当時にいました
・ 結成式に参加して
・ 創設時のメンバーです
・ 1995年、ミリー・ブラザー氏が来日して、コーダが集まったところに出席して
・ ‘95にDプロ主催のオータムスクールで「CODAのつどい」に参加してから
<コーダから聞いた>
・ コーダの方に聞きました
・ コーダの知人に紹介された
・ 友人のコーダに紹介された
・ コーダの友人に声をかけられて
・ 知り合いのコーダに紹介されて
・ 知り合ったコーダからの紹介だと思います
・ 同じコーダの方からの情報で
・ 専門的な手話通訳養成機関に通っていた時にコーダの人に聞いた。
・ 学校の先輩からの誘いで
・ 手話講習会で一緒だったコーダから
・ 都の講習会受講生が会の人
・ 手話講習会のアシスタントの方が、メーリングリストに登録していたので
・ 連盟主催セミナーに倉持さんが出演され、そこに当時私の通っていた講習会の講師が見学しており、連絡先を聞き、私に教えてくれました
・ 田中清さんに教えて頂きました。
・ こころおとの武井君に紹介された
<きょうだいから聞いた>
・ 姉から聞いた
・ 姉から聞いた事がある
・ 弟から存在を聞いたくらいで詳しくは知らない
<手話サークルで聞いた>
・ サークルの人に教えてもらって。他のコーダと知り合えた
・ 養成学校入学前、手話サークルに見学に行った際に教えてくれた
<その他>
・ 友人の紹介で
・ 知人の紹介で
・ ろう者の友達が教えてくれた
・ 研究会等での情報交換で
・ 本を読んだ
・ NHK 聴覚障害者の皆さん
考察
「知っている」人の中では、メーリングリストに登録し、「コーダの会」の集まりに参加したことのある人が14人と多数派を占めた。メーリングリストに登録しているが集まりには参加していない人、集まりには参加したことはあるがメーリングリストに登録していない人、「知っている」とのみ答えた人は、それぞれ6~7人ぐらいだった。しかし、「知っている」とのみ答えた最後のグループの6人の中には、調査者の知る限り、以前は参加していた人が4人含まれている。このような人たちは、メーリングリストに登録せず、最近の「コーダの会」についてはあまり知らないため、今の「コーダの会」がかつてのJ-CODAの流れを引いたものであるのかが判断しにくく、「参加したことがある」に○をつけなかったのかもしれない。
「コーダの会」を知った経緯に関しては、他のコーダから情報を聞いたという答えが圧倒的に多かった。「コーダの会」は、「コーダ」という言葉の場合よりもさらに、コーダ同士の口コミを中心に情報が伝達されているという特徴があるようである。
※(「参加したことがある」と答えた人に対する)「何回ぐらい参加しましたか?」という質問に対しては、答え方が一様ではなく、あまりにもまとめられないため、省略しました。
質問39 同年代のろうの友達のつきあいはありますか。当てはまるものに○をつけて下さい。
|
同年代のろうの友達はいない
|
11
|
|
同年代のろうの友人とは会えば挨拶をする程度
|
10
|
|
同年代のろうの友人とは定期的に会う
|
9
|
|
プライベートでも、同年代のろうの友人とやりとりがある
|
21
|
|
同年代のろうの恋人/配偶者がいる
|
3
|
|
その他
|
1
|
|
無記入
|
1
|
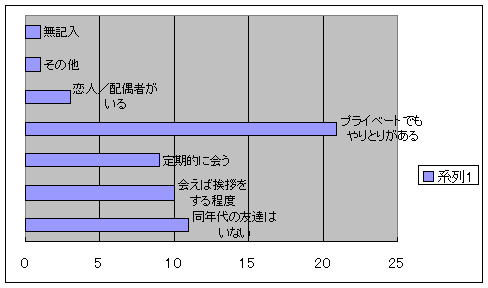
「その他」の回答者の答え
・ 地元にいたときはありましたが今はないです。僕が地元で洋服屋をしていたときのお客さん
考察
同年代のろう者とのつきあいに関しては、「プライベートでもやりとりがある」と答えた人が21人、「配偶者がいる」人が3人と、私的な領域でも関わっている人が多かった。また、「定期的に会う」は9人、「会えば挨拶をする」は10人など、個人的に深く関わるわけではなくても同年代のろう者と会う機会はそれなりにあることが窺えた。おそらくこれは、今回の回答者の中で、手話通訳や手話の学習、聞こえない人に関わる活動をしているコーダが多いこととも関係があると思われる。その一方で、回答者の4分の1は、「同年代のろう者の友達はいない」と答えている。聞こえない人や手話に関する活動をしていない人の場合には、同年代のろう者と親しくなる機会はかなり限られていると言えそうである。
質問40 同年代のコーダの友達とのつきあいはありますか。当てはまるものに○をつけて下さい。
|
同年代のコーダの友達はいない
|
10
|
|
同年代のコーダの友人とは会えば挨拶をする程度
|
5
|
|
同年代のコーダの友人とは定期的に会う
|
16
|
|
プライベートでも、同年代のコーダの友人とやりとりがある
|
20
|
|
同年代のコーダの恋人/配偶者がいる
|
0
|
|
その他
|
1
|
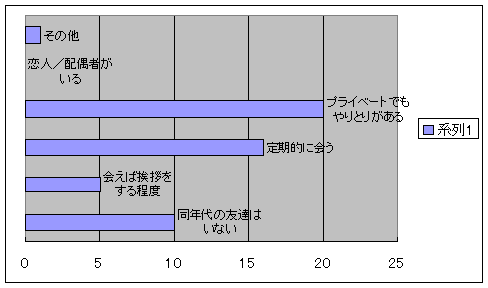
「その他」の回答者の答え
・ 特別な付き合いはありませんが手話の本を作るときにコーダで手話講師をやっておられる方に手話監修をお願いしました。
書き込みのある回答者の答え(( )内が書き込み)
・ 同年代のコーダの友人とは会えば挨拶をする程度(色々話します)
・ 同年代のコーダの友人とは定期的に会う(中学校の頃まで)
・ 同年代のコーダとたまに会う(コーダの会で会う、又はメールのやり取りをする程度)(→この回答は、集計にあたっては、「定期的に会う」と「プライベートでもやりとりがある」に振り分けました)
・ プライベートでも、同年代のコーダの友人とやりとりがある(CODAの会のメンバーがほとんど)
・ 同年代のコーダの友人とは定期的に会う(いっぱい)
考察
同年代のコーダとのつきあいは、同年代のろう者とのつきあいよりも、「定期的に会う」が多く(16人)、「会えば挨拶をする」というケースが少ない(5人)という結果になった。「プライベートでもやりとりがある」というのは、同年代のろう者と同じくらい(20人)だった。今回のこのアンケートの回答者は、コーダの会やろう者の教会(クリスチャンの親を持つ10代のコーダたちなど)といった場でつながっているため、「定期的に会う」機会がそれなりにあるようだ。しかも、コーダ同士ということで、会う機会が少なかったとしても短期間で盛り上がり、つきあいが深くなるという面もありそうである。しかし、調査者の参与観察やインタビュー調査も考慮するならば、こうした状況はかなり特殊で、全国のコーダの一般的な体験ではない。むしろ、今回の回答では4分の1に過ぎなかった「同年代のコーダの友達はいない」人が多数派なのではないかと推測される。実際、同年代のろう者の場合に比べて、「コーダ」と名乗りを挙げている同年代のコーダは人数的にもかなり限られており、特定の場を通して知り合ったコーダ同士が個人的に密なつきあいをしているというのが現状であろう。コーダの場合には、ろう者のように、ろう学校やろう者スポーツ団体、ろう協など、多方面で組織化されていないため、こうした状況になるのではないかと思われる。
質問41 異性とつきあう時、相手が聴者かろう者というのは意識しますか?
|
|
N=40
|
|
意識しない
|
30
|
|
意識する
|
9
|
|
その他
|
1
|
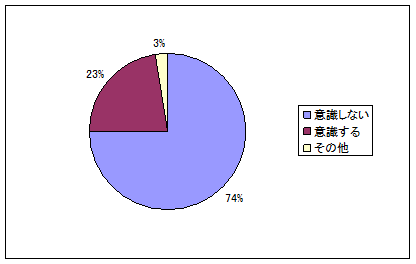
書き込みのあった回答
・ 「意識しないと思う(今までそういうことはない)」(←「意識しない」にカウント)
・ 「若い時はあまり意識していなかったが、つきあってみて、すべての事に深く話し合う事がない点がものたりなかった」。(←聞こえる人と結婚した既婚者の回答。どちらにも印をつけていなかったので、集計の時には「その他」にカウントした)
(「意識する」と答えた人に対して)どういう点で意識しますか?
・
ろう者だったら、色んな面で自分とは違うから意識する。聴者だったら私の生まれ育った環境や親に対して理解してくれるかどうかが大切なポイントだと思っている。
・
聴者ならろうの世界を理解されるかどうかを考える。ろう者なら特になし
・
ろう者は依存的などで親と同じ思いはしたくないから
・
頭の中では、聴者でもろう者でも私の気持ちを理解してくれる人もいるだろう、してくれない人もいるということは分かっている。でも、母や父とのコミュニケーションにおいて嫌な思い出があるせいか、ろう者の人とはつきあいたくないと思う。
・
めんどいから
・
コミュニケーションがとれるのかどうか。
・
むぅ~…。
ろう者とつきあうことは想像できますか?
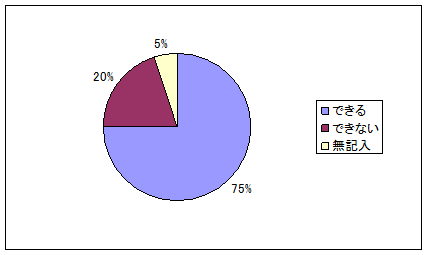
※「無記入」の2人はどちらも既婚者。そのうち1人は、質問39においてろうの配偶者がいることを書いている。
書き込みのあった回答
・
できない(前の質問で意識しないと書きましたが…現実に考えてみると想像できないです)
・
できる(厳密に言うと、できるが現実的ではない)
コーダとつきあうことは想像できますか?
|
|
N=40
|
|
できる
|
32
|
|
できない
|
4
|
|
その他
|
1
|
|
無記入
|
3
|
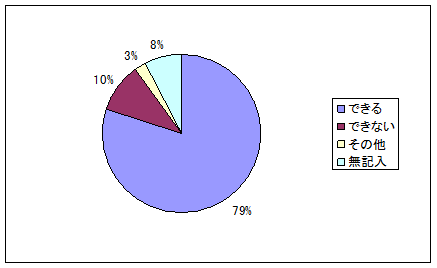
※「無記入」の3人のうち、2人は既婚者。そのうち1人は、質問39においてろうの配偶者がいることを書いている。
書き込みのあった回答
・
できると思う!?
・
できる(厳密に言うと、できるが現実的ではない)
・
できる(でも非現実的。まわりにあまりcodaがいないから)
・
今のところは、どちらとも言えない(←「その他」にカウント)
考察
相手が聴者かろう者を意識するかどうかという質問に対して、回答者の4分の3は「意識しない」と答え、「意識する」と答えた人は少数派であった。「意識する」と答えた人たちの「どういう点で意識するか」に関する記述を見ると、相手が聴者の場合はろうの世界を理解してくれるかどうか、相手がろう者の場合はコミュニケーションの難しさや聞こえる自分との違い、依存されるかもしれないという心配が、考慮する点となっていた。
ろう者との交際を「想像できる」と答えた人は30人、「想像できない」と答えた人は8人だった。コーダとの交際は「想像できる」が32人、「想像できない」が4人、「どちらとも言えない」が1人だった。どちらも「想像できる」が多数派だが、「想像できない」という答えは相手がコーダの時よりもろう者の時のほうが多かった。
しかし、組み合わせで見ていくと、「ろう者との交際は想像できないがコーダとの交際は想像できる」という組み合わせで答えた人は5人いるものの、逆に「ろう者との交際は想像できるがコーダとの交際は想像できない」と答えた人も2人いる。その他、「ろう者との交際もコーダとの交際も想像できない」と答えた人が2人、「ろう者との交際は想像できないがコーダとの交際は無記入」の人が1人だった。
さらに最初の質問も加えると、組み合わせとして圧倒的に多かったのは、「相手が聴者かろう者かを意識しないし、ろう者との交際もコーダとの交際も想像できる」という答えだった。
一方、書き込みでは、自分の気持ちとしては「相手が聴者かろう者かを意識しない」が、現実的には自分の身の回りにそれほどコーダやろう者がいないというギャップが触れられていた。調査者の参与観察やインタビュー調査の結果と考え合わせると、手話の活動に関わっているコーダの場合でも、同年代の異性のろう者とはそれなりに会う機会があるが、同年代の異性のコーダと知り合う機会はかなり限られていることが窺える。
質問42 聞こえないことに関する理解や手話に関する面で、結婚相手への希望はありますか?
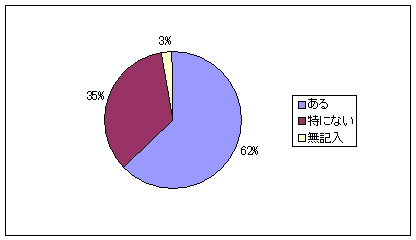
(「ある」と答えた人に対して)具体的な希望は?
<少しでかまわないから手話を覚えてほしい、ろう文化を知ってほしい>
・ 出来れば手話を覚えて欲しい(日常会話程度でかまわないので)、また、ろう文化についても知って欲しい
・ 簡単な会話ができる程度の手話を習得して欲しい。ろう文化を理解して欲しい。
・ 親と少なくとも日常会話レベルくらい手話で話せるような人。「ろう文化」の本を読んで欲しい。
・ 親と片言でも会話出来る程度の手話は身に付けて欲しい
・ もし手話を知らない相手であれば、手話を身につけて、自分の親と手話で意思疎通が図れるようになってくれたら嬉しい。
・ 自分も上手じゃないのであまり言えないのですが、少しは手話を覚えて親と直接話をしてくれる場面が毎回じゃなくても何回かはあったらいいなぁと思います。
・ 手話を覚えてほしい
・ 伴侶も手話ができる人が望ましい(少しでも)
・ できれば手話を学んで欲しい。また、子どもにも手話を使わせたいし、使わせることに賛成して欲しい。
・ 手話を覚えてくれるのが一番うれしいが、強制はできない。でもTV等でろう者の事が出ていたら、関心を持ったり興味を持ってくれたらうれしい。
<どんな方法でもかまわないので、親と直接話そうとする気持ちを持ってほしい>
・ 聞こえる、聞こえないではなく、心で会話してくれればいいです。その手段は片言の手話でも筆談でもなんでもいいです。
・ どんな方法でもいいけれど、できれば、母とちゃんとコミュニケーションをとれる人と結婚したいと思っている。
・ 手話ができなくとも、聞こえない人に伝えようとする姿勢を持って欲しい
・ たとえ手話はできなくても直接話す気持ちを持ってほしい
<聞こえる人の場合と同じように接してほしい>
・ 父母のことを、特別な目ではなくて、普通の目で見て欲しい。理解しようと思って欲しい。
・ 聞こえる人同士が理解しあおうと思うのと同じように、付き合ってほしい
・ 聞こえる人と変わらず敬ってほしい
・ 子供に遺伝したらとか、やっかいとか、(出来たら)思わないで欲しい。→ろう者と接することを普通に受け取って、楽しんでくれるような心の人がいいな・・・とは思う。
<理解してほしい>
・ 自分のろう者観や手話観に同意してくれなくていいから理解はして欲しいという思いはある。
・ 両親への理解と手話通訳という仕事の理解
・ 両親が聴覚障害者ということに理解がある人。
・ 理解してもらいたい
・ ある程度の知識と理解がほしい
<違いがあることをわかっていてほしい>
・ 外国人みたいにみてほしい。文化があり、違いがある事。
考察
全回答者の62%にあたる25人が、結婚相手への希望は「ある」と答えた。具体的にもっとも多かったのは、「できれば手話を覚えてほしい」というものだった。しかし、回答者のほとんどは、聞こえる人が手話を学ぶことの難しさもわかっており、「少しでもかまわないから」とか「日常会話レベルの」というように、やや控えめに希望を述べる人が多かった。また、「手話という方法でなくとも直接聞こえない人と話をしようとする態度を持ってほしい」、「聞こえないからといって特別視するのではなく聞こえる人の場合と同じように接してほしい」という意見も見られた。
質問には「聞こえないことに関する理解や手話に関する面で」という言葉が入っていたこともあって、ほとんどの場合、これらの希望を書く時に結婚相手として想定されたのは「聞こえない人とあまり接点を持ったことのない聞こえる人」であったようだ。このような一般的な聴者が結婚相手としてイメージされたという点には、それが社会の多数派であること、また、今回のアンケート回答者の年齢層が比較的若く今の段階では未婚の人が多いということも関わっていると思われる。しかし、実際には、質問39にある通り、回答者のうちの3人は聞こえない人と結婚しているという状況があることにも、ふれておきたい。
質問43 人工内耳についてどう思いますか?
|
よい技術だと思う
|
5
|
|
特になんとも思わない
|
9
|
|
あまり印象はよくない
|
16
|
|
否定的な印象がある
|
10
|
|
その他
|
2
|
|
無記入
|
1
|
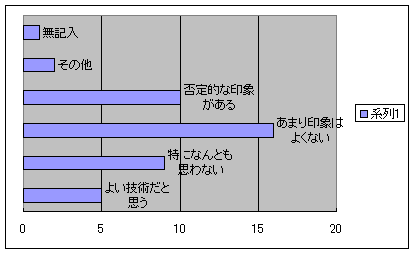
「その他」の答え
・ ゴメンなさい。知識が全く無いので、当てはまる項目がないです(汗)
・ 人工内耳がわからない
考察
人工内耳については、「否定的な印象がある」と答えた人が10人、「あまり印象はよくない」と答えた人が16人だった(1人の回答者がこの両方を書いているケースも3つあった)。人数で言えば、過半数以上の23人が、人工内耳に対してマイナスの印象を持っていることがはっきりと出た。中立的な立場をとった人が9人、プラスに評価したのは5人だった。
体内に機械を埋め込む他の技術(たとえば心臓を補助するためのペースメーカーなど)については、どう思いますか?
|
よい技術だと思う
|
18
|
|
特になんとも思わない
|
15
|
|
あまり印象はよくない
|
4
|
|
否定的な印象がある
|
3
|
|
その他
|
1
|
|
無記入
|
1
|
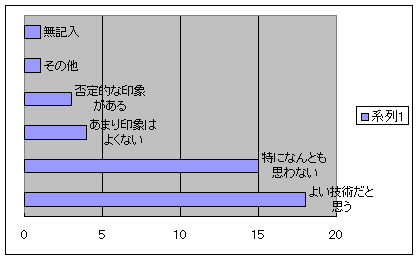
「その他」の答え
・ (人工内耳と)同等には考えられない
考察
ペースメーカーなどの技術をプラスに評価した人は18人、「特になんとも思わない」人が15人で、マイナスに捉えた人は少数だった。
上の2つの質問を合わせた結果
|
|
N=40
|
|
人工内耳もペースメーカーもよい技術だと思う
|
4
|
|
人工内耳もペースメーカーも特に何とも思わない
|
5
|
|
人工内耳もペースメーカーもマイナスの印象がある
|
7
|
|
ペースメーカーよりも人工内耳の評価が低い
|
19
|
|
その他
|
4
|
|
無記入
|
1
|
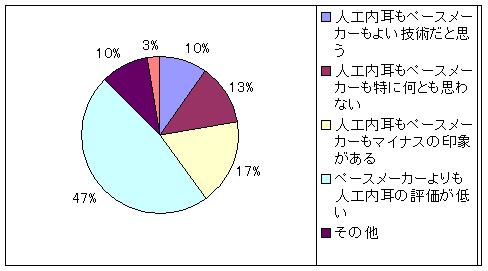
書き込みをした人の答え(( )内が書き込み)
・ 人工内耳:あまり印象はよくない(が、仕方はないか、とも)
ペースメーカー:あまり印象はよくない(が、必要な技術であると思う)
・ 人工内耳:あまり印象はよくない
ペースメーカー:よい技術だと思う(ペースメーカーであるならば、生きていくのに絶対必要だから)
・ 人工内耳:あまり印象はよくない
ペースメーカー:よい技術だと思う(本人に合うなら。)
考察
上の二つを組み合わせてみた結果、人工内耳とペースメーカーの両方に同じ態度を示した人が16人いた。その内訳は、人工内耳もペースメーカーも「よい技術だと思う」と答えた人が4人、両方とも「特に何とも思わない」と答えた人が5人、両方とも「あまり印象はよくない」「否定的な印象がある」と答えた人が7人だった。この16人は、人工内耳もペースメーカーも同じ医療技術として捉え、体内に機械を埋め込む技術そのものを評価したり否定的に見たりしていると言える。
気になるのは、人工内耳に対する態度とペースメーカーに対する態度が明らかに異なる回答者である。人工内耳に比べてペースメーカーを高く評価した人は、前回答者の半数近い19人にのぼった。その内訳は下表のようになる。
|
|
N=19
|
|
人工内耳はマイナスの印象があるが、ペースメーカーはよい技術だと思う
|
12
|
|
人工内耳はマイナスの印象があるが、ペースメーカーは特になんとも思わない
|
5
|
|
人工内耳は特になんとも思わないが、ペースメーカーはよい技術だと思う
|
2
|
「その他」に分類される4人に関しても、人工内耳をペースメーカーと「同等には考えられない」と書き込みをした人(人工内耳は「否定的な印象がある」)が1人、人工内耳が何か「わからない」または「知識がない」と答えた人(ペースメーカーはそれぞれ、「特になんとも思わない」「よい技術だと思う」と回答)2人が含まれる。
これらを考え合わせると、今回のアンケート回答者の中には、医療技術全般はある程度評価しながらも、人工内耳についてはマイナスの印象を持つ人が、かなりの数存在していることがわかる。
もし自分の子どもが聞こえなかったとしたら、人工内耳を
|
|
N=40
|
|
つけさせたいと思う
|
4
|
|
つけさせたくない
|
23
|
|
その他
|
12
|
|
無記入
|
1
|
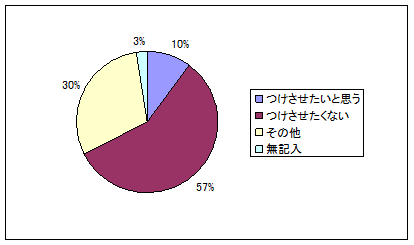
※「つけさせたくない」には、「あまりつけさせたくない」も含めてカウントしました。
「人工内耳をつけさせたいと思う」理由
・ やはり耳が聞こえた方が便利だと思うので
・ 聞こえた方が人生より楽しめると思うから(←人工内耳のことを「初めて聞きました」という書き込み付き)
・ 聴こえた方が安全だから。
・ 特別意識を持たせたくない
「人工内耳をつけさせたくない」理由
<人工内耳のリスクや代償、不安定なアイデンティティへの懸念>
・ つけさせたことの代償がどれだけのものなのか、まだ自分では見出せないのでつけさせようとは思わないが、ある程度の年齢になり本人が望めば反対はしないと思う
・ 変なリスクを背負ってまで、無理に聞こえるようにしなくても良い
・ ろう者にも聴者にも入れない人工内耳の子を見てきているのでそのような子には育てたくないという思いがある。
・ ろう者としても健聴者としてもアイデンティティがもてなくなりそうだから。親としてもどのように教育したらいいかわからなくなりそうだから。
<聞こえない子や「聞こえないこと」を否定したくない>
・ 人工内耳をつけさせることによって、聴覚障害者の子供を否定しているように感じるから。ある意味、人工内耳も整形のように感じる。
・ ろうを否定する事ではなく、そのままを受けとめたいと思う。しかし、(聴覚障害が)軽く、聴者に近いのであれば、補聴器等も使用する。
・ 聞こえないことに対する否定的な考えを持って欲しくない。聞こえないこととは、私自身は、一つの個性だと思うので。しかし、その子がつけたいと考えるのであれば、つけると思う。
・ 「聞こえない子供を聞こえるようにしたい」という発想がまず浮かばない。人工内耳を付けたからと言って完全に聞こえるようになる訳ではないし、中途半端になるだけ。ただ、いつの日か人工内耳の機能がもっと良くなって、聴者と変わらないだけの聴力を手に入れることが出来、なおかつ子供が「付けたい」と切に望むのであれば考えるかも。・・・難しいですね。
<自然なままがよい>
・ ろうに生まれたことはその子の個性で運命だから、たとえ親であっても人工的にどうこうしてはいけないと思う。
・ 境遇を受け入れ、自然体で生きていくべき。デメリットが大きい。人工内耳をつけるだけのメリットが感じられない。
・ 自然が一番
・ 自然に生きていくことが大切だと思う。
・ 神様の作ったものをありのままに受け入れたい
・「ろう」のままがいい
<手話やろうの世界の肯定的評価>
・ 手話があるから
・ つけてもたいして変わらないし、ろうの世界も楽しいものがあるし。
<本人の意志の尊重>
・ アメリカでは16才で自分で判断して手術を決めるとの事で、そうしていきたい
・ 本人の意志に添いたいとは思うが
<少数派であることへの懸念>
・ あんまりいないから
「その他」の理由
<本人の状況(聞こえない程度・原因)による>
・ 本人の状況を見て考えたい
・ 聴力レベルや原因による。今は、正確な情報や知識を私自身が持ってないから。効果や長所、短所によると思う。
・ 聞こえない程度によります。かなりの効果があるのであればつけても良いと思います。
<可能性の見込みがあれば検討する>
・ 人工内耳をつけることにより、かなり有益と見込めるなら、前向きに検討します。
・ 凄く考えるだろうけど、可能性が大きいのであれば考えるかも。
<人工内耳の技術水準が上がり手軽になれば検討する>
・ 今の技術水準では、つけたいとは思わないが、眼鏡をかけるのに近い感覚(というのは極端だとしても、それくらいの手軽な感覚)で手術が行えるくらいまで技術が発達したら、つけたいと思うのではないかと思う。少なくとも今の社会では、耳が聞こえた方が聞こえないよりは「便利」であることは事実だと思うので、容易に/確実に聴力を獲得させられる手段があれば、眼鏡をかけるのと全く同様の理由で、それを利用したいと思うのではないかな、と思う。ただ、現在の技術水準はリスクが高すぎると思うので、現段階では避けたいと思う。
<どちらがよいのか迷う>
・ その時にならないとわからない。その子にとって聞こえる環境の方がよいのか、聞こえない環境の方がいいのかわからない
・ どちらともいえない。その子にとって世界が広がるのであればいいと思う反面、未だ人工内耳に対しての理解が聴障者に得られていないことでいじめにあったりするならば、あえてつけさせようとは思わない。子供が強く希望するなら話は別。
<本人の意志の尊重>
・ 子供が希望するなら、つけるかも?子供が希望しないのにつけようとは思わない。
・ 本人にまかせると思う
<わからない>
・ わからない。人工内耳がわからないから。
<子供を持つということそのものがまだ実感できない>
・ 未婚なので、子供を持つということ自体、まだ実感できない。想像できない。
考察
回答者の半数以上の23人が「つけさせたくない」と答え、4人が「つけさせたいと思う」と答えた。回答者の3分の1近い12人は「その他」の答えを選び、態度を留保した。人工内耳を積極的に評価する人が10分の1に過ぎないということ自体、一般の聞こえる人の態度とは明らかに異なっている(調査者は大学で授業を担当する時に、必ず人工内耳の問題を取り上げ、「ろう文化」やろう者側からの見方も提示して、一般の聞こえる学生さんに「もし自分の子が聞こえなかったら人工内耳をつけるかどうか」を考えさせる。こうした学生さんは、「ろう文化」を尊重したいという気持ちは持っているものの、人工内耳に関しては医療技術として支持する態度を見せることが多く、自分は聴者なのでやっぱり自分の子供が聞こえなかったら人工内耳をつけさせようとすると思うという感想が多くなる傾向にある)。
「人工内耳をつけさせたくない」理由として多く挙がったのが、「自然のままがよい」という理由と「人工内耳のリスクへの懸念」、「聞こえない子を否定したくない」という思いだった。また、手話やろうの世界への肯定的な評価から、わざわざ聞こえるようにしなくてもかまわないと答えた回答もあった。人工内耳をつけることへのリスクは、一般的には、費用や手間(通院や機械の故障など)、手術の際の危険性が挙げられることが多いが、今回のアンケートでは、ろう者としても聴者としてもアイデンティティが見出せなくなるという点にわざわざ言及している人が複数いた。しかし、「つけさせたくない」と答えた人も「何が何でも反対」というわけではなく、もし本人が希望したら受けさせるかもしれないという余地を残していた。
質問44 自分としては、聞こえない親を持つことの特性とは、どういうことだと感じていますか?
<二言語・二文化を持っている>
・ バイリンガル
・ バイリンガル&バイカルチャー
・ 二つの文化に接し、二つの言語に接するということによって単に手話や聾文化を知るだけでなく、日本語や聴者の文化についても知ることができたと感じている。その意味で、ろう者の両親のもとに生まれたことを感謝することはあっても、それを嫌悪する気持ちは少しもない。
・ 日本語以外にもうひとつ別の言語が習得できた。又、聴者文化、聾文化を知ることができた。
・ マイノリティの意識がある。2文化を持つことができる。
・ 二面性
・ ポジティブに考えるなら、自分の生活の一部が聴障者でもあり健聴者でもある。二つの世界を行き来し、橋渡しをする。二つの言語を自由に話せることにより世界が広がる。素晴しい友人もたくさん持てる。
・ 聞こえる世界と聞こえない世界の両方を背景に生きていく事
・ どちらの言語も世界も見られてお得。と、今は思う。
・ 手話で話せる違う世界へ飛べる空間を持てる。。。うまく説明できないです。。。
<複数の文化にまたがって育つことで、言語・文化・既存の分類の仕方などを相対的に見る視点を持っている、多様なものを受け入れる>
・ 言葉に関しては、日本語に対する苦手意識(i.e.語威力の少なさ;特に小・中学生の頃強かった)を持っていたりする一方で、中学校で英語を習い始めたばかりの頃はよく、周りの友達が「日本語にとらわれすぎているな」と思うことがあって、外国語への慣れは早かったように思う。こういう言葉への苦手/得意意識が混在するという不思議な感覚は、今思えば、家庭環境に起因しているのかもしれない。
・ 難しい質問内容ですね。基本的には日本に住む在日韓国人2世の方とか、在日ブラジル人2世の方とか・・・の思いとも似ていると思います。異なる文化の間で生きる事を学べる・・・。そして、自分のバックボーンを考えるきっかけとなる出来事が少しだけ早くくる環境。周りがろう者だけなら、なんにも考えなかったかもしれません。英語のLとRの発音の違いがわからないように、絶対音感がある人とない人の違いのようにささいな違いとしか思わなかったかもしれませんね。それくらい、今は違いを感じなくなってしまいました。(笑)親自身が聞こえた事がないから、聞こえたいとは思わないって言っていることも関係していると思います。
・ 2つの文化の狭間
・ 一般の聞こえる人たちよりも、社会の多様性を受け入れやすい性格になったと思う。
・ 異なる文化を共有する特性がある。健聴者で育った健聴者とはどこか異なる気がします。
・ 気持ちを表現する事の楽しさや難しさを若いうちに考え、感じ、知れたと思います。声も手話もそれはただの表現手段であり、大切なのは心なんだと知る事が出来ました。僕は健聴者という人種ではなく、聞こえない人はろう者という人種ではないという事。一人一人がそれぞれの特徴を持った人間であるという事。
・ 障害者全般に対して、構える事なく自然でいられる。
<洞察力やコミュニケーション能力に長けている、視覚が鋭いなど>
・ 顔色や声等でどんな方かの判断ができろう者よりも五感が鋭い様な感じです
・ 人の表情を読みとったり、“ことば”や“言語”ではないところで、人の心情を詠みとる能力に長けている気がする。
・ 洞察力がすごい
・ 今まで何も考えずに過ごした為、特性と言われるとピンと来ないが、感受性が豊かとか、視覚が鋭いとか言われるのは、コーダ故の特性なのかな…?と最近少しだけ思う様になった
・ 特に意識して考えたことはない。今、思いついたのは…コミュニケーション能力に長けていること
<貴重な体験をしている、ラッキーである>
・ 日本語と違う魅力ある言語を話す、一般の人には得がたい貴重な機会に巡りあい、恵まれたこと
・ これまでの言葉では語りつくせない程の体験は貴重なものであり、少しでも手話が出来る事でろうの方とコミュニケーションがとりやすい。交友関係の幅はこれによって広がっているし、これからも何かしら、自分から広げていきたい。
・ ラッキー
・ 良い(笑)
・ 良い
・ 良い(スマイルマークとハート3つ付き)
<親に感謝している>
・ 聞こえない人から受けた恩は聞こえない人へ返していくべきものだと思う。最高の宝物をくれた親に感謝しています
・ 現在は両親のお陰で手話通訳・手話指導・講演等、私の生活すべてに関わり多くの体験や人との出逢いがあって、本当に充実した生活を送っています。両親には感謝!!感謝です。子どもの頃いじめられた経験も、両親がいたお陰で乗り越える事もできました。いわゆる2つの文化を持つ事ができました。姉達に比べ、いい時代に生を受けたのかもしれません。
・ 私はコーダとして生を受けた事に本当に幸せに思っています。両親は5人の子供 をきちんとしつけ、ろうである事に何もひけめを感じない親でした。今は亡くなりおりませんが、今でも尊敬するのは親が一番です。
<親が聞こえないことに由来する性格や行動があるように思う>
・ 聞こえる親の家庭環境がどういうものかわからないので想像になるが、おそらく、通訳等で小学生の頃から親に「頼られる」という経験はユニークなのではないかと思う。子供ながらにどこかで常に責任を感じていたり、親に困ったところを見せてはいけない、という意識があったように思う。単に個人的な性格の問題かもしれないが、自分や人に弱みをみせたり甘えたりするのが苦手なところがあるのだが、もしかしたら、幼少期のこういった経験が関係しているのかもしれない。
・ 素直、すぐに人を信用する、他人の気持ちになって物事を考えられる、「自分が1番でないといやだ」と思う気持ちがまったくない。たいがいのことは自分から折れて物事を片付ける、しゃべるのが苦手、1人が好き
・ 聞こえない世界の限られた情報の中で育ったろう者に育てられた事により、偏った性格になりがち。(今は、たくさん情報を得られる機会が増えたがそれでも、自然に耳から入ってくる情報には負けると思う。)短気、思い込みが激しい、感情の起伏が激しい。
・ 状況を説明するのが上手。演技力がある。
<「聞こえないこと」が身近>
・ ろう者が安心して話して下さる。ろう者が私に対しての心を開いて下さると感じています。
・ ろう者や、聞こえないこと、手話を身近に感じる。特別視しない。親しみを感じる。
・ 聞こえないことに対する否定的な考えがあまりない。日常のこととして、受け入れている。
<自分にできることをしようという意識がある>
・ ろう者と聴者の仲立ちとしての役割を持てるのではないかという可能性を感じる。
・ 多数者になかなか理解されない時もあるので、そうした人たちに、自分の言葉で伝えようという意識がある。
・ 「宿命」ではなく「使命」
・ 自分磨き
<特に意識していない、普通だと思っている>
・ 深く考えた事がないので普通だと思っています。
・ 世間と比べてどーのという事は今まで一度も意識した事はなく、格差的なもの差別的なものも感じた事はない。自分としては、他の家族との違いを感じた事もない。物心ついた時から家族にろうあ者がいる人はそんなもんじゃないでしょうか?
・ 特に意識してない。
・ 特に今は何も感じていない!?
・ 特になし
・ 以上のような特性がある(→ろう者や聞こえないことを身近に感じる、多数派に対して自分の言葉で伝えようという意識を持つ、ろう者と聴者を仲立ちできるのではないかという可能性を感じるなど)とは考えるが、大部分は、多くの聴者と変わらないと思う。+α・親子の繋がりの強さを、多分感じることが多いかもしれない。
<わからない>
・ わからない。ずっと考え続けるのでは
・ 自分では分からない。多分、家族への執着というか依存というか、愛情というかはもしかしたら他の友人よりも強いのかもしれないが、友人間において家族に対する想いを話題にすることは日常的にはあまりないので、比較のしようがないからだと思う。また、そういった特性が、コーダだからなのか、それとも個人の性格の違いなのかの判断が自分ではつかないということもある。
・ ?
考察
この質問に対しては、二言語使用や二文化体験、文化を相対的に見る視点や多様性を受け入れる点など、複数の文化にまたがって育つことを肯定的に記述した人が多かった。その背景として、手話を言語として捉える「ろう文化」の考え方を多くの回答者が知っており、しかも「文化」という視点で自分の体験を振り返ることをある程度の納得がいくものとして受け入れているということが言えそうである。
一方で、「文化」という言葉を使わずに、洞察力やコミュニケーション能力に優れていることに触れた人たちもいた。ろう者は「物事を見抜く力がある(手話で言えば「目が高い」)」とよく言われるが、コーダは親からそうした視覚的な洞察力を受け継ぎ、なおかつ聴者としての感覚も察知できるため、言葉に出されない思いを敏感に汲み取ったりそれに気づいたりすることが多いのかもしれない。その他、コーダであることで貴重な体験を得ることができたとか、親が聞こえないことに由来する性格や行動があるように思うといった記述もあった。また、コーダへのインタビュー調査では、「コーダはがんばっている人が多いと思う」という発言が複数の人から挙がった。しかし、「特に意識していない、普通だと思っている」といった答えが一定数あったことにも注意を向けておきたい。こうした答えは、特別視されることへの違和感として出された面もありそうだが、本当に何も意識していないという意味で出てきているとも考えられる。
まとめ
今回のアンケートを通して明らかになったのは、コーダの思いは子どもの時と大人になってからとではずいぶん変わってくる面があるということである。コーダは、聞こえない親の「あたりまえ」と聞こえる社会の「あたりまえ」の両方にふれて育っていくため、ある程度の年齢になると、そのバランスをとるのが難しくなることがある。ごく幼い頃は、自分の置かれている環境を「普通」だと思っていても、成長するにつれて聞こえる人々とのやりとりが増え、自分や自分の家族が「特殊」と見られていることを意識するようになっていく。また、自分に向けられている期待や偏見なども察知するようになる。こうした状況では、時として感覚的なものや感情的なものが先行し、苛立ちや面倒くささ、不全感、違和感、恥ずかしさ、聞こえる人や聞こえない親への反発が感じられることもあるようである。しかし、思春期には、トラブルや感情のもつれは認識しても、その解決のために何をどうほぐせばいいのか充分に整理するのが難しい。自分の家族や生い立ちをある程度客観的に見ていくことができるようになるのは、より広い社会の中で、さまざまな経験を積み、聞こえる人にも聞こえない人にもいろいろな人がいることを知ることを通してのようである。また、聞こえない世界のこと(手話が言語であること、聞こえない人には聞こえる人とは異なるやり方があること、ろう教育のあり方など)を知ったり、他のコーダの話を聞いたりすることも大きな役割を果たしているようだ。そのようにして、自分の思いや親の行動の「意味」を自分なりに見出し、それを言葉で語るようになっていくのかもしれない。全般的に、手話に対するいいイメージが世間でも広まっている今日では、コーダが自分のルーツと向き合う機会も以前に比べて増えている。もちろん、それを経た後にどのような道を選ぶかは個人の自由である。しかし、そのように向き合う機会を持つことによって、コーダ個人にとっての視野は広がり、納得の度合いも高まっていくのではないかと思われる。
さらに、上記のこととも関連することではあるが、今回のアンケートでは、コーダが子どもの時に、その状況や年齢に合った環境があまり整えられていないということも浮き彫りになった。具体的には、親との会話以外に手話の語彙や言い回しを増やしていく機会が少ないこと(それは子供向けの持続的な手話学習の場がないことや、同年代のろうの子どもたちとのつき合いがあまりないことも含む)、年齢の割に難しい内容を通訳しなくてはならない時があること、聞こえる大人がコーダに安易な同情や特別なまなざしを向けるのを問題視する風潮がないこと、コーダがコミュニケーションの不全感を持った時にそれを解消する方法が提示されないことなどがそれにあたる。コーダの子どもがコーダの大人と知り合う機会があまりないことも、改善するべき点であろう。コーダの家族体験は、コーダ個人の大きな部分を占めているにもかかわらず、普段はなかなか話す機会がない。それは、話してもまわりの共感を得にくかったり、重く捉えられすぎて誤解を招いてしまったりする。そうしたひずみは、少しずつたまっていき、思春期に大きくなるようだ。思春期は、同年代の友人との関わりや親への反抗を通して自己を形成していく時期である。そのようなことを考えると、コーダがもっと子供のうちから、親が聞こえないということに関しても、他者の共感を得たり、親が聞こえないケースでもいろいろあると知ったりしていけるようなしくみを作っていくことは、大きな意義がある。たとえば、「コーダの会」が発展しているアメリカなどでは、年齢のまだ低い子どものコーダのために、「CODA
KIDS(コーダの子供たち)」という組織も作られ、その年齢のコーダに合わせたサマーキャンプやイベントが開かれている。コーダを育てている若いろうの親と成人コーダが一緒になって、未成年コーダの環境を整えていくこうした試みは、今後、日本でも設立していく価値があるのではないだろうか。
おわりに
最後に、このアンケート調査にご協力下さったすべての方々にお礼を申し上げます。アンケートにお答え下さった方々、質問作りを助けて下さったインタビュー協力者の方々、アンケート配布に尽力して下さった方々、そして、このアンケート調査に意義を見出し支援して下さった方々。修士論文の頃からこのテーマで研究することを温かく見守って下さった東京大学大学院教授竹内信夫先生にも、感謝の気持ちでいっぱいです。コーダ、ろう者、聴者、さまざまな立場を超えたこうした方々のお力がなければ、この報告書を仕上げることはできませんでした。この報告書が、読んで下さった方々の何らかの役に立てれば、無常の喜びです。
澁谷智子
コーダに関する参考文献(日本語で読めるもの)
<コーダが書いたエッセイなど>
星野正人,1996,「CODAから見たろう文化」『現代思想 (総特集 ろう文化)』1996年4月臨時増刊号,76~77ページ(=現代思想編集部編,2000,『ろう文化』青土社に再録).
丸地伸代,2000,「ろう者と聴者の間で――CODAという名のマイノリティ」『言語 (特集 子どものことばをどう育てるか)』2000年7月号,88~95ページ.
中村恵以子,1996,「Codaに目覚める」『現代思想 (総特集 ろう文化)』1996年4月臨時増刊号,379~381ページ(=現代思想編集部編,2000,『ろう文化』青土社に再録).
宮澤典子,2002,「母よ」中野善達・伊東雋祐・松本晶行編著『手でおしゃべり――手話への招待』福村出版,103~105ページ.
<コーダを扱った小説>
Greenberg, Joanne, 1970, In This Sign, New York: Henry Holt and Company.(=ハナ・グリーン著,佐伯わか子・笠原嘉訳,1997『手のことば』みすず書房.)
<コーダについての研究>
小久保壮太郎,2003,「聞こえない親を持つ聴者の諸相」世田谷福祉専門学校手話通訳学科平成15年度卒業研究.
Preston, Paul, 1994, Mother
Father Deaf: Living between Sound and Silence, Cambridge,
Massachusetts / London,
England: Harvard University
Press.(=2003,澁谷智子・井上朝日訳『聞こえない親をもつ聞こえる子どもたち』現代書館.)
澁谷智子,2000,「『ろう文化』と『聴文化』の間――コーダの文化論的考察」東京大学大学院総合文化研究科平成12年度修士論文.
澁谷智子,2001,「文化的境界者としてのコーダ:「ろう文化」と「聴文化」の間」『比較文学』第44巻,69~82ページ.
澁谷智子,2003,「コーダのバイリンガリズム」『言語 (特集 バイリンガリズムとしての手話)』2003年8月号,72~79ページ.
|