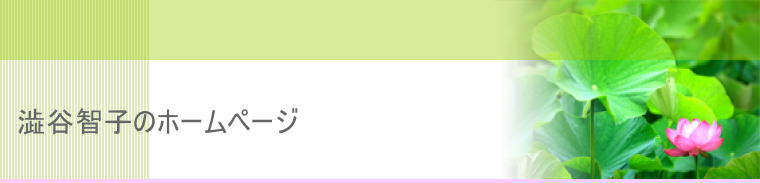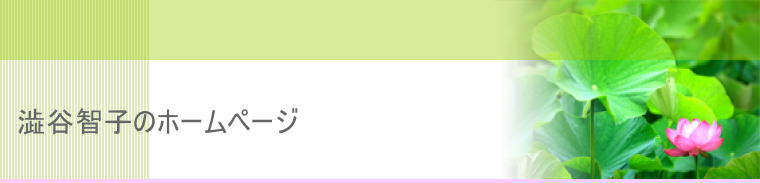|
|
埼玉県立大学 比較文化論 (2008年9月~2009年3月)
|
この授業では、「グロ-バリゼ-ション」「働き方」「家族」「身体」という4つの具体的な切り口から、比較文化的思考を養う。異なる空間や時代の社会のあり方との比較を通して、私たちが持っている文化的規範をより多角的に見ることができるようにするのが、この授業の狙いである。
「グローバリゼーション」に関するセッション(第1回~第4回)では、人や情報、仕事の国際移動の現状を扱う。こうした議論をふまえ、「働き方」と「家族」に関するセッション(第5回~第12回)では、日本や他の国の事例を通して、若者と仕事、働き方の形態、反貧困の動きなどを考察する。また、仕事と生活が密接にかかわっていることを確認しながら、近代家族の成り立ち、親子関係、結婚、育児などについて学び、人と人とのつながりの意味を考える。「身体」に関するセッション(第13回~第15回)では、医療化する現代社会を支えている思考や文化的背景を検討する。特に、身体に介入する技術に焦点を当てて「自然」と「人工」の境界を考えるほか、今日の「障害者」イメージを作り上げている身体規範や能力主義について問い直す。
第1回 イントロダクション 文化とは何か?
授業説明、「文化」の定義
「盲人国」のケースから「異文化」問題を考える
第2回 「日本人」って誰?
芸能人のプロフィールを見ると…
国籍法、日本にいる外国人(オールドカマー、ニューカマー)
インドネシア人・フィリピン人看護師・介護士受け入れ
第3回 グローバル化する時代の人と仕事
海外へのアウトソーシング「人事も経理も中国へ」、言語と植民地、
介護現場の外国人労働者受け入れの背景
第4回 グローバル化する時代のケアワーク
働く在日フィリピン人介護士
ケアワーカーの労働環境「介護の人材が逃げていく」
第5回 働き方について考える
バイト先の労働問題
「派遣の広がり―3つの業界から」(派遣保育士などのケース)
感情労働とは何か
第6回 “溜め”について考える
若者の働くことに関する雑誌の増加
「何もしなかった」「冷めている」の背景
ケアワーカーを働き過ぎに追い込むメカニズム
溜めについて
第7回 ゲストによる講演 1 「競争社会の克服に向けて」
POSSE学生スタッフ川村さんと佐藤さんのお話
第8回 家族と仕事―近代家族の成り立ちについて
「近代家族」とは何か
子供期の発見
主婦の誕生
第9回 ゲストによる講演 2 「女性と仕事」
子育てと仕事のバランス。労働環境と職種、離職率、復職率
薬剤師の大谷さんのお話
第10回 個人化と人のつながり
社会保障を考える
「セーフティネット・クライシスⅡ 非正規労働者を守れるか」から
オランダのフレクシキュリティ法
第11回 個人化と人のつながり 2
年越し派遣村
生活空間の移り変わりに見る個人化の歴史
対面コミュニケーションと社会関係資本(『孤独なボウリング』)
社会関係資本と「婚活」
第12回 結婚や育児のあり方の国際比較
家族形成の国際比較(フランスとドイツの婚外子や同棲の考え方)
子育てアドバイスの国際比較
第13回 性を考える―セックス、ジェンダー、セクシュアリティ
クィアって何?(椿姫彩菜さんのケースを例に)、性をめぐる認識、
障害者の性
第14回 障害とは何か?
欠格条項と法改正(聞こえない薬剤師の早瀬久美さんの例)、
インペアメントとディスアビリティの区別
中途診断とラベル
何が「障害」と捉えられるのか(『みんなが手話で話した島』)
第15回 身体と技術
「イノセンス」
サイボーグ技術と感覚の変容
レポート課題(学生さんへのお勧め文献)
2009年度・2010年度の授業で扱ったその他のテーマ
・文化の流通とグローカライゼーション ①
海外での日本文化の受容(アニメや漫画)
・文化の流通とグローカライゼーション ②
海外での「日本」(映画、食品)、文化の模倣、様式の均質化と表面的な差異化、
土着化と逆輸入(てりやきバーガーやエキゾチックジャパン)
・グローバル時代のケアワーク
移動できる仕事とそうでない仕事
インドネシア人やフィリピン人の看護師・介護士の受け入れと課題、異文化間ケア
授業のページへもどる
|
|